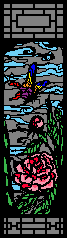 |
・・・・・・あれ? |
† The New Year’s Party †
―――― また、この日が来てしまった・・・。 悩み多き科学班班長、リーバー・ウェンハムは、心底嫌そうに眉をひそめながらも、被害を最小限に抑えるべく、今年も努力をはじめた。 「ふ・・・はぁぁ――――――ぁ・・・」 薫り高い茶を一服すると、リナリーは深く吐息した。 「つっ・・・・・・かれたぁぁぁぁぁぁ――――――・・・・・・」 彼女は、談話室の一番奥にあるソファの陰で、隠れるようにカーペットの上に座り、小声で呟いた。 この時期、彼女は黒の教団とは全く関係なく忙しい。 その原因は、主に・・・と言うより、全般が彼女の兄によるものだった。 「故郷(くに)にいるんだったらともかく、なんでイングランドに来てまで・・・・・・」 ぶつぶつと呟きながら、お茶請けのスコーンにクロテッドクリームをたっぷり乗せていると、 「リナリー!!!!見つけた!!」 悲鳴じみた声が上がり、ぎくりとして見上げると、ソファの上から、兄の長身が覆い被さるように彼女を見下ろしていた。 「コ・・・コムイ兄さん・・・・・・っ」 なんでわかったの、と問うと、 「こんなとこでジャスミンティーなんて飲んでるのはキミだけでしょ!」 匂いでわかるよ!!と、憤然と応じられる。 「なに一人で休憩してるのさー!!今日中にやってしまわなきゃいけないのにッ!!」 やたら焦った様子で、リナリーに立つよう促す兄に、しかし、リナリーは頬を膨らませてそっぽを向いた。 「なによ、さっさと始めないコムイ兄さんが悪いんでしょ!私の部屋はとっくに終わったわよ、大掃除!!」 イングランドに移り住んでも・・・いや、世界各地、どこに移住しようと、自身らの風習を変えない。 彼らも、そんな漢民族の一人だった。 西暦で数えられた新年には、非常に淡白だった彼ら兄妹だが、1月も下旬になると急にそわそわし始め、とうとう昨日から二人で大騒ぎを始めた。 いわゆる、(旧)正月前の大掃除である。 しかし、コムイの私室、執務室、及び研究室は、やたら広い上に主の性格もあいまって、凄まじく散らかっている上に、注意深く進めないことには、重要文書の紛失事件を引き起こしかねない。 そこで、班長を中心とする科学班メンバーとリナリーが、無理やり協力させられているわけだが、執務室はまだしも、研究室は危険すぎて入る気にもなれない。 「研究室だけは自分でやって、って、毎年言ってるじゃない!その代わり、お部屋の方は全部やってあげるからって! 私、コムイ兄さんのお部屋を掃除するのに、ほとんど一日かかったんだから!」 憤然と言うと、『立ち上がる気はない』と言わんばかりにスコーンに噛み付く。 兄の部屋の掃除にかかりきりで、まだ昼食も摂っていなかったのだ。 絶対拒否、の背に、しかし、コムイは同情を引こうと、情けない声を出す。 「そんなに冷たい事言わないでよ、リナリィィィー!! だって、ボクの研究室って広いんだもんー!その上、実験機材がものすごく多いんだもんー!! 試験管を洗うだけで、1年かかっちゃうよー・・・!! ねぇ、助けて、リナリーちゃーん!!」 「ふーんだ。使うごとに片付けない兄さんが悪いんだもん。リナリー、もう疲れたんだもん」 疲労と空腹から来る不機嫌は、そう簡単には収まらない。 少なくとも、手元にあるアフタヌーンティーセットを食べ終わらない限りは動きそうにない妹に、しぶとく懇願し続けていたコムイだったが、その目の端に、なにやら白いものが写った。 「カモ発見!!」 「え?」 喜々とした兄の声に、リナリーが振り返った時には、もうその姿はソファの上から消えていた。 「カモ・・・って、なにかしら??」 首を傾げつつも、彼女の興味はすぐにアフタヌーンティのサンドイッチに移ったのだった。 ティムキャンピーを頭にのせて、とことこと食堂に向かっていたアレンは、悪寒を感じて振り返った。 「ひぃぃぃっ!!コムイさん!?」 暗い廊下に白く浮かび上がる巨大な影は、彼にとって幽霊よりも恐ろしい科学班室長だ。 その彼にがっしりと両肩を掴まれて、アレンは身動きを封じられた。 「ヤァ、アレン君!ヒマかい?!ヒマだね?!ヒマだろうとも!!だって今日のキミには任務がない! サァ、ボクと一緒に来るがいい!!」 「いやですぅぅぅっ!!!」 廊下中に響き渡るような悲鳴も、しかし、無駄であることはわかっていた。 どれほど悲鳴を上げても、助けを求めても、鬼の室長から彼を救ってくれる者などいはしない。 「めんそーれマイ・ラボラトリィ!歓迎するよっ!」 「すっごくやな予感がするからいやですぅぅぅぅっ!!!」 「まぁまぁ、一緒にビーカーコーヒーでも飲もうじゃないかー!」 そう言って、コムイはアレンを小脇に抱えると、頭に乗ったティムキャンピーを振り落とさん勢いで研究室へとさらって行ったのだった。 「ふわぁ・・・・・・」 初めて扉の向こう側を見たアレンは、そのあまりの怪しさに、それ以上の言葉を失った。 妙な臭いがする。 薬品と錆びた鉄と石炭の煙、それらを酸に溶かしたような、言いようのない奇妙な臭いだ。 彼らに追いつき、扉の隙間をすり抜けるように入ってきたティムが、あまりの臭いに嫌がるようなそぶりを見せ、盛んにアレンに擦り寄ってくる。 「この部屋を、今日中に掃除してしまわなきゃいけないんだよ!」 「はぁ?!」 コムイの宣言に、アレンは頓狂な声を上げた。 「この部屋をですか?!」 決して狭くはない建物の、ワンフロアをぶち抜いた部屋である。 こんな大広間、王族の城にだってあるかあやしいほどだ。 視界を邪魔するものがなければ、はるばると見渡せるに違いないそこには、長大なテーブルがいくつも並べられ、その上には何に使用しているのか理解不能な、さまざまな実験用具が所狭しと並べてある。 「ここを掃除だなんて・・・なんでいきなりそんな決心をしちゃったんですか?!」 最早、いくつあるのか数える気にもなれない試験管やビーカーを見渡しながらアレンが絶叫すると、コムイはにこりと笑みを浮かべた。 「だって、新年を迎える前には、大掃除をする決まりなんだよー」 「新年なんて、とっくに迎えたじゃないですか!!もう2月ですよ?!」 「西洋ではねー。 だけど、中国の新年は明後日。今日はまだ、12月28日なの」 養父と死に別れて以来、師について様々な国を巡り、異文化に触れてきたアレンだったが、そんな彼にも知らないことがあったようだ。 しかし、コムイによって散々ひどい目に遭わされ続けてきた彼は、多少疑い深くなっていた。 「・・・・・・まさか、騙してないですよね?」 眉根をきつく寄せ、上目遣いに問うと、コムイは大げさに首を振って否定する。 「疑うんなら、神田君に聞いてみなよー。 日本は政府が無理やり西暦に変えちゃったけどさ、それまでは中国と同じ暦だったんだから。 明後日はなんの日だい?って聞いたら、正月だって教えてくれるよー」 って、任務に行っちゃってここにはいないけどねー、と、コムイは陽気な笑声を上げた。 「だからね、正しい中国人としては、今日中に大掃除を終えなければならないんだよ! そうしないと、ご先祖様に申し訳ないし、福も降りてこないからね!!」 「はぁ・・・・・・」 未だ疑いつつも、アレンは渡された洗剤とスポンジをおとなしく受け取る。 「でも、僕は科学のこと、何も知りませんよ?変なとこ触って、せっかくの実験を台無しにしちゃったら・・・・・・」 と、最終抵抗を試みたが、鬼の室長は動じなかった。 「だーいじょうぶ!今は大事な実験はしてないからねー」 「で・・・でも、危ない薬品とか触ったら大変じゃないですか?科学班の人達にお願いした方が・・・・・・」 と、更に抵抗を試みたが、 「科学班は今、ボクの執務室の方で手一杯なんだー。 そんなにヤバイ薬品は置いてないし、とりあえず、使用済みの試験管とビーカーを洗ってくれるかい?」 と、アレンを部屋の奥へ奥へと追いやる。 「シンクは各テーブルについているから、適当に使って!」 強引な室長に追い立てられて、アレンは仕方なく、使用済みの機材でいっぱいになったシンクに手をつけた。 同じ頃、コムイの執務室では、科学班のメンバーが、幽鬼のような顔色でリーバーの周りを漂っていた。 「はんちょー・・・これ、捨てていい文書ですかー?」 「ばかたれー・・・それは重要機密文書だー・・・!」 「はんちょー・・・・・・食べかけのチーズ発掘しましたー・・・・・・」 「そんなもんとっとと捨てろー・・・!」 「はんちょー・・・この賞味期限、日付が18世紀です・・・・・・」 「・・・・・・次の学会で発表しろー・・・・・・」 次々と指示を出しつつ、リーバーは室長の机の上を片付けていく。 年の一度の大掃除は、コムイがこの教団に来て以来の、年中行事になってしまった。 が、極端な話、一年に一度しか清掃を行わない部屋は、人外魔境の相を呈し、とても一日二日で片付くものではない。 それでも彼らが従順に従っているのは、少なくとも一年に一度くらい掃除をしてもらわなければ、重要書類が紛失する恐れがあるためだ。 コムイのためではなく、自身らの能率と心の平安のためにこそ行われる行事は、しかし、普段肉体労働に慣れていない彼らの身体を、無残に酷使するものだった。 「今年こそ、あの人に片付ける癖をつけてもらわないと・・・!!」 ぶつぶつと不満を漏らすメンバーに、リーバーは深く吐息して頷く。 「しかしまぁ・・・。実験室の掃除に駆り出されないだけマシだな。 みんなも知ってるだろ、あの薬品群・・・。下手にいじれば、毒ガスが発生するぜ」 彼の言葉に、メンバーは身震いして頷きを返した。 「あの部屋の試験管に触るくらいなら、俺は蛇の巣穴に飛び込むよ」 その言葉に、同意の声が各所から上がった・・・・・・。 班長をして、『触るくらいなら蛇の巣穴に飛び込む』と言わしめた、件の試験管を洗っていたアレンは、いつまで経っても終わらない数に、早速嫌気がさしていた。 「コムイさん、こんなにあったんじゃ、いつまで経っても終わりませんよ・・・って、なんて格好してるんですか?!」 アレンが見遣った先では、コムイが分厚いつなぎを着て、真ん丸い体型になった挙句、頭全体を覆うヘルメットをつけて、実験器具の間に蠢いていた。 まるで、ジュール・ヴェルヌの科学小説に出てくる、潜水服のようだ。 アレンの声が聞こえるのか、コムイはその状態で振り向くと、分厚いゴムの手袋で覆われた手を振った。 気にするな、と、ジェスチャーで示されても、到底無視できるものではない。 「でも・・・」 言い募ろうとするアレンを制するように、再び手を振ると、コムイはアレンが取り組んでいる試験管を指し示した。 いいから続けて、という、ジェスチャーでの指示に、嫌々ながら従う。 しかし、普通のガラス器を洗うだけならそう簡単に傷みはしないだろうスポンジが、試験管を2、3本洗う度にぼろぼろになり、5本目を洗う頃には厚手のゴム手袋に穴が開いて、その度にそれらを交換しなければいけないため、作業は遅々として進まない。 「コムイさーん!他に誰か、手伝ってくれる人はいないんですかー?!」 イライラと声を上げると、コムイはヘルメットに覆われた頭を振る。 「んもー!!」 しかし、人でなしの師匠の下で修行した経験のあるアレンは、若いながらも根性の据わった少年だった。 ティムキャンピーが、次々と差し出す新しいスポンジとゴム手袋を受け取っては、何百、何千と言う試験管、ビーカー、シャーレなどを洗って行く。 それら全てが終了した頃には、日付はとうの昔に変わっていた。 「ご苦労サマー♪ほら、ご褒美のビーカーコーヒーだよー♪」 そう言って、コムイはアレンが洗ったばかりのビーカーに、コーヒーを並々と注いで差し出す。 「・・・・・・せめて、紅茶にしてくれませんか・・・・・・」 アレンは、洗剤の臭いに酔いそうな頭をふらふらと上げて、死にそうな声を絞り出した。 何千と言う洗物をしたせいで、肩から下の感覚は既になくなっている。 「残念だけど、ボクの部屋にお茶っ葉なんてないんだよー」 「じゃあ・・・食堂に行きます・・・・・・」 「えぇー!せっかく淹れたのにー!」 「無理やり連行されて!重労働させられて!お腹空いたんです!!」 疲労と空腹は、人を苛つかせる最重要因だ。 アレンは絶叫すると、入ってきた時よりは、臭いも見た目も、随分ましになった研究室を後にした。 「注文お願いしまーす!!」 とうに日付の変わってしまった食堂に、人影はまばらだ。 しかし、昼夜なく任務を与えられる教団構成員のために、食堂は24時間営業である。 アレンが遠慮なく厨房のカウンターで呼ばわると、本日の夜勤料理人であるジェリーが、ひょい、と顔を出した。 「あらまぁ、アレンちゃん、どうしたの?いつもだったらお休みの時間でしょお?」 世話好きな近所のおばさんのような口調で言う彼に、アレンはげっそりと頷く。 「アフタヌーンティー前に、コムイさんにさらわれちゃって、今まで研究室の掃除を手伝わされていたんだ。 お願いです、ジェリー。なにか食べさせて」 哀れな子犬のような姿に、ジェリーは大仰な仕草で驚いた。 「アンタ、コムイの研究室にいたんですって?!」 彼の絶叫に、食堂に散らばっていた人々の顔が、ぎくりと強張る。 ぐったりとテーブルに突っ伏していた彼らは、コムイの執務部屋の片づけを終えた、科学班のメンバー達だった。 「そうですけど・・・何か?」 ただならぬ雰囲気に、アレンの顔も緊張を帯びる。 「何かって・・・アレンちゃん、ティムキャンピーをよくごらんなさい!!」 言われて、自分の頭の上に乗ったティムを取り上げ、見ると、羽や尻尾の先が黒ずみ、酸に侵されたように所々溶けていた。 「ティッ・・・ティム――――!!!」 痛そうに、弱々しく羽ばたくティムキャンピーを手に、おろおろするアレンに、ジェリーは落ち着くよう、声をかける。 「ティムは後で、科学班がなんとかしてくれるから!先にアンタよ、アレンちゃん!!防毒マスクはしてたの?!」 「防毒・・・・・・?」 言われて初めて、アレンはコムイの、怪しい格好の意味を知った。 「〜〜〜〜〜騙された・・・・・・!」 悔しげに顔を歪めるアレンに、同情の視線が降り注ぐ。 「――――っ全く、あのマッドサイエンティストはー!! アレンちゃん、アタシが特製の解毒メニューを作ってあげるから、今日からしばらくは、好きな物は我慢しなさい!いいわね!?」 「あっ・・・ありがとう、ジェリー!!!」 すっかり弱ったティムキャンピーを抱きしめたまま、アレンは厨房のカウンターで大泣きしてしまった。 翌日、自室を出たアレンは、嫌な思い出の詰まったコムイの研究室から目を逸らすようにして、急ぎ足で廊下を進んでいた。 と、彼の正面からリナリーが、大きな紙を何枚も抱えて、重そうに歩いてくるのに出くわしてしまった。 「おはよう、リナリー」 「あら、おはよう、アレン」 単に挨拶だけで済まそうとはせず、自然な動きで重そうな荷物をリナリーから取り上げる。 「これなに?きれいだね」 彼女が持っている紙は、広く厚目の紅い紙で、その上は金銀の紙で華麗な装飾がほどこしてあった。 「春連って言ってね、お正月にドアや部屋に貼るのよ。おめでたいことを呼び込めるように」 「・・・これも?」 アレンは、どう見ても可愛いとは思えない、不気味な笑みを浮かべた少年少女の絵を示す。 「そうよ。まぁ、貼るのは私とコムイ兄さんの部屋だけだから、気にしないで」 「・・・・・・手伝うよ」 本当は、コムイの部屋に入るなど、鳥肌が立つほど嫌だったが、レディ一人に大変な作業をさせるわけには行かない。 さり気なく、しかし、実は大変な努力をして発した言葉に、リナリーは嬉しげな笑みを浮かべて礼を言った。 「その『福』の字は逆さにしてね」 リナリーの指示に従って、アレンは二度と近づかないと誓った研究室のドアに『春連』を貼っていく。 「字を逆さにするの?なんで??」 漢字を見たことのない彼にとって、それは正位置であろうと逆位置であろうと、何ら意味を持つものではなかったが、わざわざ発せられた『逆に』という指示を不思議に思って問うと、リナリーはにっこりと笑って、アレンの手にした『福』の字を逆さにした。 「福が降りてきますように、っていうおまじないなのよ」 「へぇ・・・面白いね」 リナリーに笑みを返しながら、アレンは彼女と彼女の兄が使っている部屋のドアや室内の壁に『春連』を貼っていく。 「あ、これは僕にもわかるよ。コウモリでしょ?」 ハロウィーンに飾るような、コウモリの形に切り取られた紙を広げて、アレンが笑みを浮かべた。 「でも、お正月にコウモリ?あんまりおめでたくはないんじゃない?」 不思議そうに問うと、リナリーは軽い笑声を上げる。 「そうね、ヨーロッパでは不吉なイメージでしょうね。 でも中国ではね、蝙蝠の発音は幸福・・・Happyと同じ発音なの。だから、とてもおめでたいのよ」 「へぇぇ・・・」 「絵に描いてある子供も魚も・・・これは金魚、って言うんだけどね、あと、変な道具類も、みーんなおめでたい意味があるの」 「ふぅん・・・・・・」 とても感心した様子で、まじまじと手元の絵を見つめるアレンに、リナリーが笑みを深めた。 「そうだ。アレン君の部屋にも飾ろうか?」 「え?」 「コムイ兄さんがこれ以上、アレン君をいぢめませんように」 「・・・っよろしくおねがいします!!」 真剣な声でリナリーに迫ったアレンは、春連を力いっぱい握り締めてしまった。 更に翌日、アレンは朝からリー兄妹の姿を見かけなかった。 リナリーはともかく、その兄の姿を見なくて良い日の、幸福をしみじみと噛み締めつつ、ジェリー特製の解毒メニューを味わう。 今日は黒酢、黒胡麻、黒豆、黒米、黒松子に黒かりんの、黒食品尽くしだ。 それぞれの効能について、ジェリーより十分な説明を受けたアレンが、心づくしのメニューをありがたく食していると、廊下から爆薬の弾ける音、続いて、悲鳴が湧き上がった。 「な・・・何事?!」 硬直する人々に対して、エクソシストであるアレンの動きは素早い。 不審な音を聞いた、と思った瞬間に椅子を蹴って立ち上がり、廊下に飛び出していた。 「どうしまし・・・たぁぁぁぁぁぁぁっ?!」 彼の足元に飛んできた爆竹が、派手な音を立てて弾け、アレンが悲鳴を上げる。 「何するんですか・・・!!」 爆竹の飛んできた方向に抗議の声を上げると、むっとする硝煙の奥には、火と大量の爆竹を持ったコムイが、嬉しげに佇んでいた。 「しつちょー!!!室内で爆竹を使わないでくださいって、毎年言ってるでしょーが!!」 勇敢にも、最大の抗議の声を上げたリーバー班長の周りで、拍手が起こる。 しかし、言われた本人はどこ吹く風とばかりに嘯いた。 「だから、今年は廊下でやってるじゃないさー」 「廊下ででもやらないでください!!」 迷惑です!と、絶叫する班長に呼応して、激しいブーイングが起こる。 「正しい中国人としては、お正月は爆竹で迎えなければ・・・・・・!!」 「大掃除は手伝ってあげたでしょーが!!爆竹は諦めてください!!」 そうだそうだ、と、呼応する人々にコムイが何か、言い返そうとした時、 「いい加減にしなさい、コムイ兄さんッ!!」 彼の脳天に、リナリーの踵落としが炸裂した。 「兄さんの奇行のせいで、中国人全員が誤解されちゃうのよっ!爆竹禁止!」 「えぇ〜〜〜〜!!でも、リナリィィィィ〜〜〜〜〜!!!」 割れた頭から大量に出血しながらも、爆竹を離そうとしない兄から、リナリーは危険物を取り上げる。 「リーバー班長、ごめんなさい。 もう教団内で、爆竹遊びはさせませんから」 そう言って、ぺこりと頭を下げるリナリーに、リーバーはようやく肩の力を抜いた。 「兄さんを止めてくれてありがとうよ、リナリー・・・ついでにその人、早く療養所に連れていった方がいいぜ・・・・・・」 リーバーが指し示した先では、自らの作り出した血の海に半面を浸して、コムイがビクッビクッと痙攣している。 明らかに、ショック反応だ。 「えぇ。そうするわ」 言うや、リナリーは軽やかに踵を返し、兄の白衣を掴むと、未だ流れつづける彼の血を潤滑油代わりに、ずるずると引きずっていった。 「・・・ブラッディ・ロード・・・・・・・・・!」 あまりの恐ろしさに、今回ばかりは『手伝う』とも言えず、アレンはリー兄妹の姿を、硬直したまま見送った。 そして、とうとうこの日はやってきた。 旧暦『新年』である。 あまりにも恐ろしい二日間を体験したアレンは、この日は一体、何が起こるのだろうかと、朝から身を強張らせていた。 今日はできるだけ自室から出ないようにしようと決め、巣穴にこもったうさぎのように身を縮めていたが、問題は向こうからやってきた。 コンコン、と、ノックの音に、飛び上がらんばかりに怯える。 が、 「おはよう、アレン君」 と、続いて発せられたリナリーの声に、ほんの少し、緊張が緩んだ。 「体の具合でも悪いの?ジェリーが、食堂にも下りてこないって、心配してるよ?」 ドアの向こうで、リナリーの声が気遣わしげに低くなる。 悪いのは体ではなく、状況だ。 しかし、リナリー自身が問題なわけではないと思い直し、アレンは思い切って部屋のドアを開けた。 「あ、良かった。体調が悪いわけじゃないのね」 顔色は相変わらず悪いが、ちゃんと服を着て、しっかりと立っているアレンの姿に、リナリーが微笑む。 「うん・・・ただ・・・・・・」 コムイが怖くて、とは、とても言えず、アレンは言葉を濁した。 それを察したのか、リナリーは笑みを深めると、わざわざ食堂から運んできたらしいワゴンを指し示す。 「兄さんはまだ、療養所よ」 やりすぎちゃったみたい、と、リナリーが舌を出した。 「体調が悪くないんだったら、食べない?ほとんどはジェリーが作ってくれたんだけど、私も手伝ったのよ」 そう言って、にこやかに差し出されたトレイには、おいしそうな料理が所狭しと並んでいる。 「ありがとう・・・!お腹空いていたんです!!」 心から礼を言って、アレンはリナリーを迎え入れた。 彼の部屋は、他の部屋と同じく、そう広いものではなかったが、彼自身の私物が少ないため、ワゴンが入る余地は充分にあった。 「いただきまーす!」 フォークを手に取り、嬉しげに料理に手を伸ばそうとしたアレンを、しかし、リナリーがとどめる。 「ちょっと待って、アレン君!最初にこれを食べてくれる?」 そう言って彼女が差し出したのは、深めの皿に盛られた、白く柔らかそうな料理だった。 「なに?」 ほわほわと、優しい湯気を立てるそれに興味を引かれ、聞いてみると、『水餃子よ』と笑う。 「これだけは私が作ったの。食べてみて」 全く悪意のない笑顔に、アレンも笑って頷き、フォークを突き立てた。 ガツッと、妙に硬い音と感触がしたが、皿にフォークが当たったのだろうと、深く考えずに口に運ぶ。 「あ、この餃子は具の他に飴とかコインが入っているから、気をつけ・・・てって、言おうとしたのに――――!!!」 硬い金属を、無防備に噛んでしまったアレンが、口を押さえて椅子から転げ落ちた。 「アレン君、大丈夫?!」 リナリーが差し出した小皿に銀貨を吐き出したアレンは、既に涙目だ。 「な・・・っなんでコインが入ってるの?!」 「・・・・・・イングランドの、クリスマスプディングと同じよ。 おめでとう、アレン君。今年はきっと、ラッキーだわ」 「・・・・・・・・・・・・本当にそう思う、リナリー?」 アレンの、涙声の問いに、リナリーは答える事ができなかった。 ともあれ、この教団内で旧正月の時期を過ごす危険性を知ったアレンは、他のエクソシスト達を見習い、来年からは任務で教団の外にいようと誓ったのだった。 ・・・・・・それまで、彼がコムイかアクマによって、殺されていなければ。 Fin. |
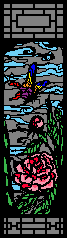 |
・・・・・・あれ? |