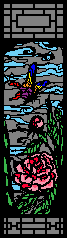†このお話はシャーロック・ホームズシリーズを元にしたパラレルです† 舞台は19世紀ですが、D.Gray-manの原作とは、ほとんど関係ありません。 頭を空っぽにして読んで下さいね |
19世紀ロンドン―――― 女王陛下のしろしめす大英帝国の首都として、世界有数の大都市となった地には、繁栄と退廃が同居している。 華やかな街の裏側では不可思議な事件も多く・・・ゆえに、『諮問探偵』を趣味とする彼を楽しませる依頼の、絶えることはなかった。 そう、その日の昼下がりにも――――・・・。 数日に亘る徹夜捜査ののち、ようやくベーカー街の下宿に戻ったコムイは、暖炉傍の肘掛け椅子によろよろと座り込んだ。 ぐったりとした彼の耳の奥では、今でも依頼主の甲高い声が響いている気がする。 早く犯人を捕まえて宝石を取り戻せと・・・可愛がっていたメイドを殺した犯人は八つ裂きにして犬の餌にしてくれると、中世の血を色濃く受け継ぐ夫人の真っ赤になった顔が、目を閉じても脳裏に浮かんだ。 「勘弁してよー・・・もぉー・・・」 クッションを抱きしめてうずくまったコムイは、疲労した身体を休めながらも脳内では冷静に証拠を並べる。 ・・・大して難しい事件ではないはずだった。 ロンドンに滞在している貴族の夫人が宝石を盗まれ、その際に彼女の忠実なメイドが殺されてしまったのだ。 夫人は・・・目をかけていたメイドが、宝石を守ろうとして犯人に殺されたと思っているが、メイド仲間に聞けばそれは『いい思い出』として墓に刻まれるべき勘違いでしかなかった。 事実は犯人の男に誑かされたメイドが、金に困った彼に夫人の宝石を差し出したものの、彼女よりも宝石に魅力を感じた男に裏切られて口封じをされたというものだ。 随分とイイ男だったようで、メイド仲間達は『少し運が悪ければ、殺されたのは自分だったかもしれない』と震え上がり、夫人に対しても硬く口を噤んでいた。 おかげでコムイも情報を得るのに苦労したが、彼女達の秘密を守ること、そして身の安全を保障することでなんとか聞き出した結果が・・・。 「また・・・伯爵・・・か・・・」 寝言のように呟いた言葉はクッションの中に篭って、外には漏れなかった。 「あんなあくどい盗みをするのは絶対あの人だよ・・・。 イイ男の特徴を聞く限り、ちょめ助君の店で見たティキ・ミックだしなー・・・。 宝石なんかのために女の子殺すなんて、全く・・・」 見下げたてた奴だと、コムイは足置きを蹴飛ばす。 クッションに顔をうずめたまま、パタパタと爪先でラグを叩くが、彼らを追い詰め、逮捕して宝石を取り戻す策が思い浮かばない。 下手に手を出して追い詰めれば、被害は軽く想定を超えるだろうし、運よく逮捕できたとしても、前回もそうだったように仲間の手引きで脱走されかねなかった。 「捕まえるんなら・・・まずは伯爵だ。 伯爵を潰さないことには・・・・・・」 彼の力は一体どれほどなのか、想像もつかないほど裾野が広い。 部下の数が多すぎて、彼へ手を伸ばすにはまだまだ時間がかかるに違いなかった。 「今回は・・・まずは宝石に集中・・・だね・・・」 きっと仇は取るからと、可哀想なメイドに詫びながら、コムイが眠りの園へ向かおうとした時。 「コムイさん!!助けてください!!!!」 大声で呼ばれたコムイは、驚いてラグの上に転がった。 「こんなとこで寝てないでー!起きてー!!」 胸倉を掴んだ少年にガクガクと揺さぶられ、却って意識が飛びそうになる。 「ちょ・・・放しなさい、アレン君!!」 乱暴な少年を押しのけて起き上がったコムイは、ぼんやりとした寝起きの目で彼の泣き顔を眺めた。 「なんでそんなに泣いてんの? お腹痛いならお医者さんにお行き」 「お腹痛くないですっ!!」 でも困っているんだと、アレンはぴすぴすと鼻を鳴らす。 「ラビが!! ラビが誘拐されちゃいました!!」 「は・・・?」 その言葉にようやく目を覚ましたコムイは、肘掛け椅子に座り直してアレンと、彼の背後で困惑げなリナリーを見つめた。 「最初からちゃんと話して」 「それがっ・・・今日、リナリーとデー・・・」 「ん?なんだって? ボクの!ボクの可愛い妹となんだってこのクソガキ?!」 「ふんぎゃっっ!!」 いきなり詰め寄られ、ぎゅっと鼻を抓まれたアレンが更に激しく泣き出し、リナリーが慌てて止めに入る。 「待って、兄さん!デートじゃないよ!」 あっさりと否定されたアレンが悲しそうな顔をしたことには気づかず、リナリーは続けた。 「春節用の飾りを買いに行きたかったから、道案内兼ボディガードでお買い物に付き合ってもらっただけ!」 「道案内~? この迷子癖が~?」 びしびしと乱暴に頬をつつかれ、アレンが気まずげに目をさまよわせる。 「いや・・・えっと・・・確かに迷いましたけど・・・」 だがそのおかげでラビを発見したのだと、アレンがコムイに向き直った。 「ふぅん。どこで?」 「イースト・エンド!」 「このお馬鹿さんっ!!!!」 渾身のげんこつを受けて、アレンの頭蓋骨が陥没しそうになる。 が、コムイは目を回すアレンの胸倉を掴んでガクガクと揺さぶった。 「ボクの可愛い妹をあんな危ない場所に連れてくなんて! 何かあったらどうするつもりだったのこの馬鹿っ!お馬鹿っ!お馬鹿さんっ!!」 「兄さん!」 ぽこぽこと殴り続ける兄をリナリーが必死に止めるが、アレンの頭には既にたんこぶがアイスクリームのように重なっている。 「イタイー!!」 ぴぃぴぃと泣き声をあげるアレンへ、リナリーに羽交い絞めにされたコムイが憤然と足を踏み鳴らした。 「まだまだこんなもんじゃ足りやしないよっ!!」 「もう! 誘ったのは私なんだから、アレン君叩いちゃだめだよ!」 「誘ったの?!リナリーが?!」 「うん」 愕然とするコムイに、リナリーはあっさりと頷く。 「言ったでしょ、春節のお買い物がしたかったんだって。 私はずっとインドにいたから、春節の飾りがどんなのかあんまりよく知らないんだけど・・・ちょめ助さんが、この時期になると清国の人がやたら派手な飾り物を売り出すからそれじゃないかって、お店を教えてくれたの」 「ちょめ君めぇ・・・!」 今にも怒鳴り込んで行きそうにギリギリと歯噛みするコムイへ、アレンが首をすくめた。 「あの・・・それで、イースト・エンドに行くんなら、危ないから僕がお供しますって・・・」 「へぇぇぇ?! キミがなんの役に立ってくれたのかなぁ!この迷子癖!!」 「ぴぎゃんっ!!」 特別に強烈なデコピンをされて、アレンが仰け反る。 「もう!兄さん!! 話が進まないじゃないか!!」 アレンをいじめることに夢中で、ちっとも話を聞いてくれない兄に、リナリーが大声をあげた。 「お説教は後で聞くから、今はラビだよ!」 「あぁ、リナリーの安全に比べたら激しくどーでもいいから忘れてたよ」 とんでもなく酷いことを言って、コムイは渋面をアレンへ向ける。 「で?なんだって?」 「だから・・・ラビが誘拐されたんですっ!!!!」 たんこぶのできた頭と額をさすりながら、アレンも大声をあげた。 この日の朝、午前だけの授業を終えて遊びに来たアレンにサチコ・・・ちょめ助は日本のお茶を振舞ってやった。 そこには既にリナリーがいて、『清の春節ってどんなことするの?』と聞かれたちょめ助が首を傾げる。 「んー・・・。 正月の時期は日本と同じ・・・じゃないっちょね。 日本はもう、西洋の暦を使うようになったっちょから、旧正月になるっちょか。 欧州に渡る前、上海で乗り換えた時がちょうどその時期だったっちょが・・・日本とは全然違ったっちょ。 家だけでなく、街中に派手な飾りがされて、いきなり爆竹が鳴って・・・物凄くびっくりしたっちょね」 「ふぅん・・・。 日本って、清のお隣なのにそんなに違うんですねぇ」 不思議そうに言ったアレンに、ちょめ助はにんまりと笑った。 「アレン、そうは言うけど、フランスと英国は清と日本よりよっぽど近・・・」 「同じわけないじゃないですか!英国は欧州じゃないもんっ!!!!」 英国人ならば怒るとわかっていて言ったちょめ助が、楽しそうに笑う。 「おいら達から見たら、お前らなんて全く一緒だっちょ。 お前らがおいら達を見分けらんないようにな」 「あー・・・うー・・・・・・」 反論できずに顔を真っ赤にしたアレンの頭を、ちょめ助はからかうようにくしゃくしゃと撫でた。 「港に行けば向こう岸にフランスが見える英国だって、言葉も習慣も違うっちょ。 対岸も見えないおいら達が違わないわけがないっちょよ」 場所によるけど、とは一応言い添えたちょめ助に、眉根を寄せたリナリーが首を傾げる。 「せっかく兄さんと一緒に暮らせるようになったんだし、清のお正月ってのをやってみたいんだ。 だけど兄さんたら・・・」 何かの事件だとかでもう何日も外出していて、春節のことを聞ける雰囲気ですらなかった。 「ふぅん・・・。 それでおいらんとこに来てくれたんだっちょか。 でもなぁ・・・」 と、ちょめ助は困惑げに店内を見回す。 「ウチは和雑貨の店だから、清のものは置いてないんだっちょ」 「そっかぁ・・・・・・」 がっかりと肩を落としたリナリーに慌てたちょめ助が、『でも!』と外へ目をやった。 「清国人が大勢住んでる場所があって、この時期になるとやたら派手な飾り物を売り出してる店があるから・・・そこに行くといいっちょ!」 「それ、どこ?!」 「えぇと、港の近くのー・・・」 荷を引き取りに行く時に通りかかったことがあると呟きながら、ちょめ助はティーテーブルに地図を広げる。 「ううん・・・! 地図じゃよくわかんねぇけど、この辺りだと思うっちょ」 彼女が指先で指した場所を見るや、お茶を飲んでいたアレンが突然むせ返った。 「わっ!びっくりした!!」 「なんだっちょ!!」 「びっくりしたのはこっちです・・・!」 未だごほごほと咳き込みながら、アレンは涙目をあげる。 「イースト・エンドって言ったら、ロンドンでも指折りの無法地帯ですよ・・・! ちょめ助さん、そんな所に一人で行ったんですか?! そのまま外国船に乗せられて、売り飛ばされてたかもしれませんよ!!」 「えっ?!ほっ・・・ホントだっちょか?!」 真っ青になって震えだした彼女に、アレンは何度も頷いた。 「無事だったのはきっと、すごーく運がよかったからです! もう二度と一人で行っちゃだめです!! 荷を受け取る時は、多少費用がかかっても配送を頼んでください!」 「う・・・うん・・・!」 こくこくと何度も頷くちょめ助にほっと吐息したアレンは、地図を見つめるリナリーに眉根を寄せる。 「ダメですよ、リナリー。 危ないって言ったでしょ」 「でも・・・この辺なら前に神田と行ったことがあるよ。 別に平気だったけどなぁ?」 リナリーが笑みを含んで言うと、神田へ激しいライバル心を燃やすアレンがムッとした。 「そりゃ、あんな凶悪面が傍にいれば、人攫いだって遠慮しますよ!」 忌々しげに言った途端、リナリーがクスクスと笑い出す。 「凶悪面かなぁ? ねぇ、ちょめ助さん? 神田ってさー?」 「すっごいイイ男だっちょ あの良さがわかんないなんて、アレンてば目が悪いっちょね」 クスクスとからかうように笑われて、アレンが頬を膨らませた。 「美・・・美人はあっちかもしれませんけど、僕だって可愛いもん! それに!!」 女の子達の笑声が更に高くなって、アレンは憤然と首を振る。 「僕だって、ボディガードくらい出来ます!」 「じゃあ、アレン君と一緒に行けば平気だよね? 春節のお買い物に付き合って まんまと乗せられたアレンは、今更『ダメ』とも言えず、渋々頷いた。 「やったぁ 歓声をあげるリナリーに、アレンは深いため息をつく。 「気をつけて行って来るっちょよー 暢気なちょめ助に見送られて、二人は危険な街へと赴いた。 「バッカじゃないのキミ! むしろ馬鹿! なんでそんなに簡単に乗せられるかなァ!!!!」 「いてっ!いてっ!いててっ!!」 ピンピンと何度も鼻を弾かれて、アレンはコムイの魔手から逃げ惑った。 「そんでっ?! ラビはイースト・エンドにいたのっ?!」 「う・・・はい・・・。 リナリーが地図を辿ってくれたんですけど、あそこは・・・」 「あーんなとこでなんの地図が役に立つのさ! みんな好き勝手お店広げてるでしょ!!」 頷いたアレンに畳み掛け、コムイが憤然と鼻を鳴らす。 と、 「もう! アレン君が話すと兄さんが邪魔するから、続きは私が話す!!」 急いでいるんだと兄を睨んで、リナリーが続けた。 「私は一度行ったきりだし、ちょめ助さんも場所の確信があったわけじゃないから、二人で探しながら行ったの。 途中で道を聞こうにも、その辺にいるのはみんな怪しげな人達ばっかりで・・・あんまり人気のない所にも行けないし、ちょっと困ってたら・・・」 「古い建物の2階から、ラビが手を振ってたんです!!」 「ラビ?」 上から声が聞こえた気がして、見遣ったアレンの隣でリナリーも建物を見上げた。 「あ、ほんとだ。 よく聞こえたね」 見間違いようのない鮮やかな赤毛が窓を越えて、曇り空に映えている。 手を振るラビに手を振り返そうとして、部屋の中に引きずり込まれた彼に目を見張った。 「ラビ!!!!」 「今の・・・悲鳴?!」 短い声ではあったが、確かに切羽詰った声であったことに驚き、二人は建物へ駆け寄る。 壁と同化して見分けづらいドアを乱暴に開け、狭く暗い階段を登ろうとして、上から下りてきた若い男に止められた。 「どいてください!!!!」 駆け上がる勢いのまま押しのけようとするが、階段が狭い上に男は細身に似合わぬ力強さで、簡単に押し返される。 「どきなさいよ!! ラビ!!ラビ!!」 リナリーが甲高い声で呼びかけるが、ラビが出てくる様子はなかった。 なおも階段を登ろうとする二人に男が早口に何か言ったが、アレンには聞き取れない外国語だ。 しかし、 『上にいたのは確かに私の友達だったわ!そして彼の従兄! あなたラビをどうしたの!』 リナリーに同じ言語で言い返されて、彼が一瞬怯んだ。 その隙に二人は無理矢理彼を押しのけ、2階へ至る。 「ラビ!!」 狭い部屋の中はがらんとして、絞められたばかりらしい豚とガチョウを乗せた台車が隅に置いてある他は、荷物らしい荷物はほとんどなかった。 しかし板張りの床の上には粗末な布がかけてあり、もぞもぞと動いて人一人が寝転んでいるように見える。 「ラビ!!」 確信を持ってアレンが粗末な布を取り去るが、その下から現れたのはラビではなく、艶のないボサボサの白髪と乾いた土気色の肌に深い皺を刻んだ老人だった。 弱々しく半目を開けた老人は、震える手を半ば上げ、意味を成さない呻きを上げながら横たわっている。 「あれ・・・?」 「お嬢ちゃんには言っただろう」 二人の後ろから、さっきの男が声をかけた。 「ここにいるのはアヘンでボロボロになったジジィと食材だけだってな」 意外に流暢な英語で言われて、アレンは困惑げな顔を彼へ向ける。 と、彼は分厚いメガネの奥の目に飄々とした笑みを浮かべ、もじゃもじゃの黒髪を掻いた。 「ここは阿片窟の2階だぜ? 真っ当な坊ちゃんと嬢ちゃんが来るような所じゃねぇよ。 さっさと出て行きな」 「でも!!」 「確かに見たもの!!」 強情な二人にため息をついて、彼は狭い部屋を指す。 「じゃ、好きなだけ調べればいいだろ。 ただし、台車の上のガチョウや豚は大事な食材だから、下手にいじるなよ。 それにそこのジジィはアヘンが切れるといきなり凶暴になるぜ? 襲われたくなきゃ、あんまり触らないことだ」 未だ口の奥からもごもごと、わけのわからない呻きを漏らす老人を本能的に遠巻きにしながら、二人は台車のガチョウや豚も避けて、今にも抜けそうに軋む板張りの床や壁を念入りに調べた。 しかし、元々荷物などほとんどない部屋に、大柄なラビが隠されるスペースなどあるわけがなく、悔しげに唇を噛む。 「さぁ、気が済んだなら・・・」 「・・・っもう一つあるわ!!」 男がずっと背にしていた窓を見て、リナリーが大声をあげた。 「この格子・・・外れるんじゃないの?!」 窓の向こうは海で、吹き寄せる潮風が鉄の格子を散々に傷めつけている。 男が気まずげな顔をした瞬間を見逃さず、二人は駆け寄って彼を押しのけた。 格子に手をかけると、それは思った通りあっさりと外れて、身を乗り出せば浅瀬にジャケットが打ち寄せられている。 「あれ・・・!」 「ラビのジャケットですよ!!」 一斉に振り返った二人を、男が睨み返した。 「お前ら・・・」 二人へ向かって歩を踏み出した途端、危険を察したリナリーがポケットから警笛を取り出し、思いっきり吹く。 「わっ!!」 傍らにいたアレンも驚いて耳を塞ぐと、途端に表が騒がしくなった。 「ちっ!警官か・・・!」 治安の悪い地域では、大勢の警官が頻繁に巡回しに来る。 笛で彼らを呼び寄せたリナリーは、どやどやとあがって来た警官達に事情を説明した。 その簡潔で論理的な説明に危機を察知した巡査が急いで上司を呼びに走り、間もなくやって来た若い刑事に、アレンとリナリーは顔を引き攣らせる。 「リンク・・・!」 「敬称をつけなさい、生意気な」 スコットランド・ヤードの厳格な刑事は、そう言って二人を睨んだ。 「Jr.がここで行方不明になったと。 そして、彼のジャケットが浅瀬から見つかったと・・・なるほど、格子を外せば彼一人くらい、簡単に放れそうですね」 錆びた格子の向こうを見遣ったリンクに、巡査の一人が海から引き上げたジャケットを差し出す。 「・・・ふむ。 では彼と・・・そこの老人も逮捕及び拘留しましょう。 署で話を聞かせてもらいますからね」 「ちっ!」 舌打ちした男が警官達に囲まれて連行され、老人も担架に乗せて運び出された。 その後に続こうとするリンクを、アレンが慌てて止める。 「ラビは?!ラビの行方は捜してくれないんですか?!」 と、 「彼らから事情を聞くことで探索の筋道を立てます。 君達はいつまでもこんな場所にいないで、早く家に帰りなさい」 すげなく言われて、アレンが食い下がった。 「早く探さないと、ラビが・・・まだ生きてるかもしれないのに、死んじゃったらどうするんですか!!」 「ではどこをどう探せと?」 ムッとしたリンクに問い返されて、アレンが困惑げに黙り込む。 そんな彼を押しのけて、リンクは鼻を鳴らした。 「この辺りは浅瀬で、見る限りJr.が沈んでいる様子はありません。 君達が彼を見てすぐに駆け込んだと言うのが事実なら、この窓からボートにでも投げ落とされて、どこかに運ばれたのでしょう。 それは今から尋問します」 「それじゃあ遅いかもって言ってるんじゃない! なによ!頭でっかちのわからずや!!!!」 リナリーの甲高い声に、リンクは眉間に深く皺を刻み、彼女を睨みつける。 「捜査には手順と言うものがあります。 それを知らない小娘は黙っていなさい」 冷たく言うや、巡査達を率いて階段を下りていくリンクの背に、リナリーは思いっきり舌を出した。 「行こう、アレン君! 兄さんに捜査を頼むんだよ!」 「・・・はい!!」 リナリーに手を引かれたアレンは、まだ希望が残っていたことを思い出して大きく頷く。 「そして・・・急いでここに来たんです!」 真剣な目で詰め寄られて、コムイも深く頷いた。 「そんじゃ、行こうか」 「はい!!」 「私も!!」 素早く着替え、ドアを開けたコムイにアレンが続き、リナリーも続こうとした所で止められた。 「なんでっ!!」 「危ないからに決まってるでしょ!!!!」 長身の兄に詰め寄られて、リナリーは思わず身を仰け反らせる。 「こんな気軽に危ないことするんだったら、今後はボクかジェリぽんの許可なしに出かけることを禁じちゃうからね!!」 「えぇー・・・!!!!」 不満げな声をあげたリナリーが、『昔は・・・』と言いかけた途端、コムイの目が吊りあがった。 「もう、以前みたいな危ないことはさせないってゆってるんですっ! ジェリぽーん!!ジェリぽん!! リナリーが悪い子だよー!!!!」 階下へ向けて声をあげると、飛んで来たジェリーの前でリナリーが首をすくめる。 「――――・・・ってわけだから、リナリーを絶対!外に出さないで!お願いしたよ!」 「えぇ! 任せておいてん!!」 手早く事情を説明したコムイに大きく頷いたジェリーが、サングラス越し、怖い目でリナリーを睨んだ。 「さぁアレン君! 行くよ!!」 「は・・・はい!」 リナリーの恨みがましい目に見送られて、アレンがコムイに続く。 表通りで拾った辻馬車に乗り込むと、コムイは御者に『スコットランド・ヤードへ』と命じた。 「あ・・・あの、コムイさん?! 現場はそこじゃなくて・・・」 慌てるアレンに頷き、彼は肩をすくめる。 「もちろん知っているとも。 でも、君が初めて行った場所の案内を正確にできるとは思えないからね。 無駄に時間をかけないためにも、リンク君に正確な現場の状況を聞いて、ついでにヤードに収監されている容疑者に接見って流れだね。 ヤードには今までも恩を売っているから、きっとボクのお願いを快く聞いてくれるさ」 淡々と言ったコムイは、スコットランド・ヤードに入るや、歓迎こそされなかったものの邪魔されることはなく、リンクから正確な現場の住所と容疑者への接見を認められた。 「あなたは部外者なのですから、手短にお願いしますよ」 嫌味を忘れないリンクに釘を刺されたコムイは、にこやかに笑って頷く。 「ラビがみっかったらキミの手柄にしてもいいからさ、快く協力しておくれよ。 ―――― さぁて、容疑者の青年ってのは一体・・・」 案内の巡査の後について、二人が留置場へ入った時だった。 鉄格子の並ぶ狭い廊下の奥から、爆音と爆風が吹き寄せる。 「な・・・?!」 来た道を押し戻されながら、辛うじて爆煙の向こうを透かし見れば、曲がった鉄格子をすり抜けた囚人が壁に開いた穴を抜けようとしていた。 「待ちなさい!!!!」 コムイの声に振り返った男が、にんまりと笑って分厚いメガネを外す。 「あいつは・・・!!」 愕然と目を見開くコムイに向けて前髪を掻きあげた彼は、メガネを放って手を振った。 「ティキ・ミック!!」 「アテ・ローゴ、名探偵 陽気なポルトガル語を投げかけて、彼は壁の向こうへ消える。 「待て!!!!」 アレンが追いかけるが、崩落した壁や天井の石材に足を取られているうちに、外からまた爆発物が投げ込まれた。 「アレン君!戻っておいで!!」 「きゃあああああああ!!!!」 コムイに言われるまでもなく、くるりと踵を返したアレンが悲鳴をあげて駆け戻ってくる。 「みんな逃げて!!!!」 格子に阻まれて逃げようのない囚人達は牢の壁にへばりつき、激しい破裂音に負けず神の名を呼びながら、うずくまって震えた。 が、ややして、 「・・・これ、爆竹だ」 音は激しいが破壊力はない花火だと気づいて、コムイがそっと様子を窺う。 「ちっ!逃げられ・・・」 「追いかけます!!」 花火なら問題ないと、飛び出そうとしたアレンの襟首をコムイが引っ掴んだ。 「おやめ、死ぬよ!」 「え?!でも・・・」 ただの花火じゃないのかと、訝しげなアレンにコムイは首を振る。 「あの犯罪集団を甘く見ちゃいけない。 彼らは目的のためなら、殺人なんかなんとも思わない冷酷な奴らだよ」 つい先程、脳裏に描いていた顔を目の当たりにしたコムイは、忌々しげに舌打ちした。 「なんだ花火か、って油断して、あの穴を抜けた途端に・・・本物の爆弾がキミを待ってるだろうさ」 「え・・・!」 唖然としたアレンの耳に、壁に開いた穴の向こうから警官達の騒ぐ声が聞こえる。 どうやら『爆弾』とか『近づくな』と喚いているようだった。 「後の処理は彼らに任せて・・・リンク君!リンク君はどこだい?!」 大声で呼ぶと、爆発事件に駆けつけたリンクが未だけぶる廊下の向こうから現れる。 「なんですか、探偵? 私は爆弾処理の指揮に・・・」 「今すぐ! 彼が潜伏していた場所に行って、その場の荷物を全て・・・床に転がる虫の死骸まで全部だよ! 残らず押収して来て! あいつの仲間が行く前に早く!!」 コムイのただならぬ様子に眉根を寄せたリンクが、珍しく反論も嫌味もなく踵を返した。 その背を見送りもせず、コムイはアレンの肩を叩く。 「じゃあボクらは急いで、もう一人に会いに行こうか」 「もう一人って・・・あのおじいさんですか・・・?」 怯えたように首をすくめるアレンに、コムイが小首を傾げた。 「怖いの?」 「怖い・・・って言うより、近づきたくないって感じでしょうか。 アヘンに侵されてるそうで、見てるだけで・・・」 アレンは言葉を切ったが、その表情から嫌悪感は拭えていない。 「そうだね。 キミみたいな若い子には、アヘン患者なんて気持ち悪いだけだろうね」 にこりと笑った彼の口調に、棘が含まれているのを敏感に感じ取ったアレンが黙り込んだ。 と、コムイはくしゃりと彼の頭を撫でる。 「ただし、彼はアヘン患者じゃないのかもしれないよ」 「え・・・?」 目を丸くしたアレンに、コムイは肩をすくめた。 「キミもリナリーも、その老人には近づかなかったって言うし、ちゃんと観察しなかったんじゃないかい? リンク刑事も、ティキ・ミックの尋問を終えた直後に爆弾騒ぎが起きて、今はボクの要請で出てっちゃったからね。 その老人は適当な場所に留置されてるだけで、誰も相手にしてないんじゃないかな」 妙に確信めいた口調で言って、コムイは爆弾騒ぎに大わらわの警官達から老人の居場所を聞き出す。 「やっぱり放置だって」 苦笑したコムイは、忙しい警官達の間を縫って大部屋へ向かった。 ティキのような容疑者と違い、軽微な罪人は大きな部屋にまとめて押し込まれている。 そんな賑やかな場所の隅に、彼は転がされていた。 「この人?」 「はい!」 大きく頷いたアレンの目の前で、老人は未だもごもごと呻きながら、震える手を半ばあげていた。 「あーあー、カワイソウに」 彼の前にしゃがみこんだコムイが、細かく震える腕を取る。 「アレン君、来てごらん」 「う・・・はい・・・・・・」 嫌悪感を拭えないままアレンが近寄ると、コムイは老人が纏う、粗末な服の袖を捲り上げた。 「え?!」 指先までちりめんじわの寄っている老人の二の腕は、まるで十代の少年のように滑らかで、筋肉もしっかりとついている。 「ワックスの一種だよ。 柔らかい蝋で、塗ってから乾くまで放置しておくと、皮膚上に老人のようなシワができるんだ。 キミも、マダム・タッソーなんかで見たことあるでしょ? ボクも変装する時にはよく使ってるよ。 そして・・・」 コムイは老人の襟元をくつろげ、鎖骨の辺りにあった継ぎ目に指を掛けた。 「ラビ、おっはよー 「ふえっ?!」 一瞬なにが起こったのか、老人の顔がボサボサの白髪ごと外れて、猿轡されたラビの真っ赤な髪が溢れ出てくる。 唖然として固まるアレンの前で、コムイがラビの猿轡を解いてやると、彼はまだ横たわったまま、ぜいぜいと大きく呼吸した。 「なっ?!なんっ・・・?!なにがあったの?!」 目玉が零れ落ちんばかりに目を見開いたアレンが、ラビを抱き起こす。 「コココココッ!!!!」 「鶏かい、キミは」 自分の名を呼べないアレンに笑って、コムイはラビの腕のワックスを剥がし、脈を取った。 「・・・睡眠薬か、あそこにあったんならアヘンかな。 意識が朦朧とする薬を飲まされてるみたいだから、リーバー君のところに連れてって、処置してもらおう。 運んで」 「はいっ!!」 力仕事をしない探偵の代わりに、アレンが自分より大きなラビを背に担ぐ。 「うう・・・重いぃー・・・!」 懸命に引きずって馬車に乗せると、すぐさまリーバーが開く個人医院へと運ばれた。 「すぐに胃洗浄だな」 コムイの話を聞くや冷静に頷いたリーバーが、ラビを処置室へ連れ込む。 途端に溢れ出した悲鳴をドア越しにハラハラと聞いていると、コムイに肩を叩かれた。 「アレン君、処置が終わるまではここにいてもしょうがないからさ、リンク君の所へ行って、『豚ちょうだい』って言っておいで」 「ぶ・・・豚・・・ですか・・・?」 何のことだろうと戸惑う彼に、コムイは大きく頷く。 「言えばわかるよ。 もうヤードに帰ってる頃だろうから、言えば快く渡してくれると思うなぁ」 言いながらコムイは、ぽふん、と手を叩いた。 「あ、そうだ! 胃袋はどうする?って聞かれたら、そっちでとっといていいよ、って言うんだよ」 「はぁ・・・」 わけがわからないながらも『早く行け』と急かされたアレンは、馬車に乗ってスコットランド・ヤードに戻る。 「あのー・・・リンク、戻ってますか?」 刑事部屋の前にいた警官に声をかけると、向こうから乱暴にドアが開いた。 「敬称をつけなさいと言っているでしょう、生意気な子供ですね!」 「リンク! あの・・・コムイさんから伝言なんですけど」 「探偵から・・・」 不機嫌な表情ではあったが、話を聞く姿勢を見せた彼に、アレンはコムイに言われた通りのことを言う。 と、 「・・・胃袋はどうしますか?」 コムイが言ったことをそのまま言われて、アレンはわけがわからないまま、首を振った。 「そっちで取っといていい、って言ってましたよ。 リンク、豚の胃袋って・・・おいしいんですか?」 何か特別な料理にでもなるのだろうかと、不思議そうなアレンに彼は鼻を鳴らす。 「なんでもありませんよ。 聞きたければ、探偵に聞きなさい。 それと、豚だけでなく・・・」 リンクがドアの向こうに呼びかけると、警官が台車に豚とガチョウを載せて持って来てくれた。 「買物伝票によれば、Jr.が買ったのは豚だけでなく、このガチョウもでした。 君、ガチョウの・・・」 「僕、ガチョウもお肉しか食べませんけど?」 おいしい料理になるなら別だけど、と、心底不思議そうなアレンにリンクが軽く頷く。 「では、早く帰ってディナーでも頂きながら、探偵にこの謎を解いてもらうのですね。 良い夜を」 「はぁ・・・」 リンクの様子を見る限り、警察側としては既に解決したことなのだろうと理解して、アレンは台車を受け取った。 「・・・・・・・・・なんなの?」 首を傾げながら馬車に乗り込んだアレンは、行き先を聞かれて反対側に首を傾げる。 「リーバーさんとこに行っても・・・こんなに捌ききれないよねぇ・・・」 か弱いミランダに、今から豚とガチョウを捌けと言うのは気の毒な気がした。 「だったらジェリーさんだな、うん。 ベーカー街へ行って下さい」 声をかけるや待ちかねた御者が馬車を飛ばして、間もなくコムイの下宿に着く。 「ジェリーさーん!ジェリーさーん!」 両手に豚とガチョウを抱えたアレンが、呼び鈴を押せずに大声をあげると、すぐにリナリーがドアを開けてくれた。 「どうだった・・・って、なにそれ?」 「わかんない」 豚とガチョウを指すリナリーに首を振り、アレンはよたよたとキッチンへ向かう。 暖かい部屋に入ると、既にいい匂いが漂っていた。 「うわぁ・・・ おいしそうな匂い・・・ うっとりとするアレンに笑顔を向けて、ジェリーは彼が抱えた豚とガチョウを受け取った。 「さっきコムたんから電話があって、事情は聞いたわん このお肉、アタシがラビに頼んでたものなのよねぇん・・・」 「・・・そうなんですか? 確かにリンクは、ラビが買った物だって言ってたけど」 一緒に渡された買物伝票をポケットから取り出し、彼女に渡すと、ジェリーは店主のサインを見て頷く。 「そうそう、このお店に仕入れを頼んでるから、学校帰りに買ってきてくれる?って頼んだのよん。 でもそのせいで、ラビが危険な目に遭うなんて思っても見なかったわん・・・大丈夫なのん?」 「はい。 コムイさんのおかげで見つけられて、今はリーバー先生の診療所で処置してもらってます。 大丈夫だからこの豚を取りに行けって言われたんですけど・・・じゃあ、ジェリーさんの所に持って来て正解だったんですね」 コムイの元へ戻っていたら二度手間だったと、アレンはホッとした。 「そうねん。 さすがにこれを持って行ったら、診療所を追い出されていたと思うわん クスクスと笑って、ジェリーは肉切り包丁を取り出す。 「さーぁ! 張り切って捌くわよん!!」 きらりと光る包丁を掲げたジェリーに、アレンが惜しみない拍手を送った時、ドアの向こうでリナリーの悲鳴があがった。 「リナ・・・?!」 狭い廊下に出ると、玄関の傍でリナリーが男に拘束されている。 「ティ・・・ティキ・ミック!!」 「おや? 俺の名前を覚えてくれたんだ、嬉しいね」 にこりと笑った顔は、とても邪悪な犯罪者のようには見えず、アレンは戸惑った。 しかし、 「このお嬢さんを目の前で殺されたくなければ、お前がここに運んだ豚とガチョウを渡してくれるかな?」 と、平然と言った彼に、アレンは顔を強張らせる。 「な・・・なんで・・・? あれはただのお肉でしょ・・・?」 なんでそんなものを欲しがるんだと、アレンが辛うじて問うと、ティキはムッと眉根を寄せた。 「ただの肉だと思うんならさっさと渡せよ。 じゃなきゃ、このお嬢ちゃんが冷たい肉の塊になるぜ?」 「渡さないわよっ!!!!」 気の強い声が真下から聞こえて、ティキは意外そうにリナリーを見下ろす。 「なんで? 命が惜しくないのか?」 普通の女の子なら、当然怯えて震える場面だろうに、彼女は険しい目で自分の首に腕を回す男を睨んだ。 「あなたがわざわざ取りに来たってことは、あれは犯罪の証拠なんだわ! しかもあの部屋にあった豚とガチョウなんだから、きっとラビを襲った理由でもあるんでしょ?! 豚とガチョウの胃袋に大事なものを隠してたのに、そうとは知らずにラビが買っちゃったんじゃないの?!」 「・・・・・・すげぇな、お嬢ちゃん」 見て来たようだと、ティキが呆れる。 「そ・・・そうなんですか?」 アレンも問うことで話を引き伸ばし、キッチンにいるジェリーが外部に連絡する隙をもたせようとした。 その思惑に気づかないのか、ティキは相変わらず、犯罪者には見えない暢気さで、おどけるように肩をすくめる。 「さすが、名探偵の妹だね。 その通り。 さる貴族のご夫人から高価な宝石を奪ったまではよかったんだけど、あのおばさん、ここの探偵に捜索を依頼してくれちゃってね。 警察だけなら撒けたのに、探偵に追い詰められちゃってさー・・・。 一旦は逃げ切ったんだけど、とにかくこのカッコじゃ・・・」 と、ティキは舞踏会に出ても人気者になれそうな、フォーマルな衣装を指した。 「すーぐ捕まっちまうと思ったの。 俺、前にあの人の助手にとっ捕まって、顔が割れてるしねー。 とりあえず変装して、証拠を隠しちまおうって、あれらに俺が盗んだ宝石を隠したんだよ」 ところが目測では、ガチョウの腹にだけ収まると思った宝石が意外と大きく、しかもたくさんあったためにガチョウの喉に詰まってしまった、と、ティキはため息をつく。 「もう、外からでも何か詰まってるな、って見えるくらい? こりゃーヤバイやーってんで仕方なく、豚に入れ換えようとしたら袋が破けていくつかガチョウの腹の中に落ちちまってさ。 予算オーバーだけど、豚とガチョウを一緒に買うか、って、肉屋の女将に言ったら・・・」 それはとっくに売約済みだと、もうすぐ客が取りに来るから店先に置いてただけで、アンタみたいなイイ男にはもっといい肉を売るよと、あっさり断られてしまった。 「間抜けね!」 「それは・・・俺も思うケド、はっきり言わないでくれるかな、お嬢ちゃん」 苦笑して、ティキはリナリーの首に回した腕へ力を込める。 「くっ・・・!」 浮き上がった身体をなんとか爪先で支えたリナリーが、苦しげに呻いた。 「リナ!!」 駆け寄ろうとするアレンを、ティキが睨んで止める。 「さぁ、事情はわかったろ、少年? とっととあの豚を・・・いや、腹ン中だけでいいや。 俺の宝石を渡しな」 しかし、アレンは激しく首を振った。 「おい・・・!」 目を鋭くしたティキに、アレンは急いで言い募る。 「持ってません!! 宝石は豚とガチョウの胃袋ごと、警察が押収しています! 僕がもらったのはお肉だけだもん!!」 「はぁっ?!マジで?!」 アレンが豚とガチョウを持って警察署から出て来たものだから、てっきりバレなかったものと思ってここまでつけて来たティキは、がっかりと眉尻を下げた。 「なんだー・・・とっくにバレてたんかよ・・・! あぁきっと俺、千年公にすげぇ怒られるんだ・・・!」 がくりと肩を落としたティキの腕の力がわずかに緩んだ瞬間、リナリーが彼のみぞおちに肘を叩き込む。 「げふっ!!」 たまらず屈み込んだティキの腕をすり抜け、攻撃に転じようとしたリナリーの腕を、アレンが背後から掴んで引き寄せた。 「リナリ、逃げ・・・!!」 「しゃがんで、アレンちゃん!!」 突如背後から言われて、反射的に床へ伏せたアレンの頭上を何かが通り過ぎる。 「へ?!」 真ん丸くなったアレンの目の前で、顔をあげたティキの側面にジェリーの膝が打ち込まれ、肘が頭頂に叩き込まれて、凶悪な犯罪者が一瞬で床に沈んだ。 「え・・・? 今・・・なにがあったの・・・・・・?」 早すぎてわからなかったと、アレンの背に庇われたリナリーが唖然とする。 と、ハムでも作るかのように手際よくティキを縛り上げたジェリーが、にこりと笑った。 「久しぶりだったけど、身体は覚えてるものねん アタシ、家がムエタイ道場やっててん、継ぐのが嫌で家出しちゃったのよねぇん 「ムエタイ・・・? ジェリーさんって、タイの人でしたっけ・・・?」 あまりのことに呆然として、どうでもいい事を聞くアレンにジェリーは手を振る。 「ウウン!アタシはインド人よん だからムエタイって言ってもタイの武術じゃなくて、インドから伝わった古式の方ねん ・・・まぁ、家出したのがちっさい頃だったから、ウチの流派がどうとか、実はあんまり覚えてないんだけどん 今は料理専門だと、ジェリーは愉快げに笑った。 「さぁさ、シメた豚さんは警察に引き渡しちゃいましょぉん アレンちゃん達が話を引き伸ばしてくれてる間に、ケーサツへ電話したからぁ・・・」 と、ジェリーが床に転がったティキを踏みつけて玄関のドアを開けると、通りをリンクが警官を引き連れてやって来る。 「こっちよぉん!早くぅ!」 ジェリーに手招かれたリンクが頷き、護送用の馬車を家の前に付けた。 「んもう! コムたんから事情は聞いてたんでしょぉん! 電話する前に来てよん!」 むぅ、と不満げに口を尖らせたジェリーに、リンクは無表情のまま会釈する。 「もちろん、ご連絡をいただく前に我々は待機していましたよ。 ただ、狭い室内に我々が殺到してもご迷惑かと」 「狭くって悪かったわねんっ!」 ジェリーは憤然としたものの、ロンドンの住宅事情はそこまで良いとは言えなかった。 部屋を広くするため、玄関から各部屋へ伸びる廊下は怖ろしく狭く、ちょっと体格のいい人間なら間違いなくつっかえてしまう。 この状況では警官が入ってこれないのも、仕方ないことだった。 「全く! か弱い女子供しかいない家に凶悪犯を入れて、何かあったらどうするつもりだったのよん!」 ジェリーの猛抗議に、リンクは薄く笑う。 「か弱い・・・女性ですか」 彼の視線に気づいて、ジェリーはティキを踏みつけていた足を気まずげにどけた。 「・・・さっさとこれ、連れてってよん! ウチは狭いから、こんなにおっきいのが転がってると邪魔なのん!」 リンクの言葉尻を取って、手を払う彼女に彼はわざとらしく肩をすくめる。 「ご協力感謝します」 「どういたしまして!」 「もう逃がさないでくださいねー!」 余計な一言を言ったアレンが物凄い目で睨まれて、慌ててジェリーの背中に隠れた。 どやどやと警官達が行ってしまうと、リナリーが訝しげに首を傾げる。 「なぁに? あの人、牢屋から逃げたの?」 「そうですよ。 警察署の壁爆破した上に爆弾仕掛けてて、凄かったです」 あっさりと頷いたアレンに、リナリーが呆れた。 「じゃあ、そんなことができる仲間がいるってことじゃない! 牢屋だって爆破できるんだもの、連行途中に馬車が襲われるんじゃないの?」 「えー・・・さすがにそれは・・・。 それを防止するためのあの人数でしょ?」 苦笑したアレンに、リナリーも『それもそうか』と頷く。 しかし残念なことに、リナリーの勘は見事に当たった。 この家を出た後、警察車輌が襲われ、護送中の犯罪者にはまんまと逃げられてしまったのだ・・・。 「また逃げられちゃったらしいよー」 新聞より早くその屈辱的な情報を得たコムイが、リーバーやミランダと共にラビを連れて戻って来たのは、すっかり夜も更けてのことだった。 「ラビ!もう平気なんですか?!」 「よかったっちょ!! 姐さんから聞いて、心配したっちょよー!!!!」 真っ先に駆け寄ったアレンとちょめ助に、ラビはげっそりとした顔で頷く。 「・・・あンのヤロウにいきなりとっ捕まって、アヘン飲まされた上に拘束されたにしちゃ元気さ。 胃洗浄だっつって、リーバーに胃までホース突っ込まれて中が空っぽになるまで吐かされたんで、すっげハラ減ってるけど」 「助けてやったんだ。 ありがたく思え」 じっとりと睨みながら恨み言を言うラビを、リーバーは鼻であしらった。 「それより、随分と賑やかっすね。 なんかのイベントだとは聞いてましたけど・・・」 「新年だよ! 中国とか、アジアのカレンダーでは、今日がお正月なんだって!」 部屋から顔を出したリナリーが言うと、お土産のお菓子を渡しながらミランダが、不思議そうに首を傾げる。 「アジアはカレンダーが違うんですか?」 「そうみたい」 見て、と手招かれた一同が入った部屋で、リナリーは壁にかかったカレンダーを指した。 「これ、兄さんが使ってるカレンダー。 西暦と陰暦が書いてあるの」 見てみると、見慣れた曜日と日付の下にもう一つ日付が打ってあり、更に記念日なのか、ミランダには模様にしか見えない文字も書かれている。 「不思議・・・。 見間違えたりしませんか?」 「大丈夫だよ、キミじゃあるまい・・・ウウン、なんでも?!」 リーバーに睨まれたコムイが慌てて口を覆った。 と、気の利くちょめ助が、すかさず間に入ってコムイの腕を引く。 「た・・・探偵! 知り合いの清国人に聞いて色々飾ってみたんだけど、どうだっちょか? 日本の提灯は基本、白だから・・・内側に紅いセロファンを貼って、紅く見せてみたっちょ」 満足してもらえるだろうかと、不安げな彼女の頭を、コムイが笑って撫でた。 「上出来だよ!即席とは思えないね!」 誉められて嬉しげなちょめ助が、壁際に寄せられたティーテーブルを指す。 「しゅんれん?って言うっちょか? 教えてくれたやつにいくつか分けてもらったけど、あれで足りるっちょ?」 「へぇー・・・これが『しゅんれん』なんだー・・・」 リナリーに『春聯を買いに行く』と言われて付き合ったものの、それがどんなものかは知らなかったアレンが、コムイより先に駆け寄って模様のような文字や見慣れない絵が描かれた紙、紅い紙の切り絵をパラパラとめくった。 「・・・変な絵。 なにこのキモチワルイ子供・・・悪魔みたいなのもいる。 あ、こっちはコウモリだ。 そして・・・でっかい魚!なんか太ってる!」 「酷い評価だなぁ・・・」 苦笑するコムイを押しのけて、アレンの隣に屈み込んだラビも、興味津々と紙の切り絵をめくった。 「アレン、こりゃ清国の縁起物さね。 子宝とか家内安全とか幸運や金運を呼び込むもんだな」 「ふーん・・・。 イースターの兎や卵みたいなもんか」 イースターにはデフォルメされた奇妙な兎が出回ることだし、これもそう言うものかとアレンは、大きく頷く。 「・・・って、なんでラビがそんなこと知ってんの? おじいちゃんに聞いたの?」 アレンが不思議に思って問うと、ラビは紙をめくりながら首を振った。 「今日、イースト・エンドにある清国人の店を通りかかったら売ってたんさ。 おもしろそうなもんばっかあったんで、店のやつに色々聞いた!」 得意げに鼻を鳴らすラビを、アレンは呆れ顔で見つめる。 「・・・そんな寄り道してるから、豚に宝石仕込まれちゃったんだよ・・・」 さっさとお使いを済ませていればこんな目に遭わなかったのにと叱られて、ラビは気まずげに顔を背けた。 「コ・・・コムイ! これ、シンボルばっかだぜ! 倒福は自分で書くんか?」 ちょうど視線の先にいたコムイに言うと、上から春聯を眺めていた彼が頷く。 「そうだね、どうも見当たらないみたいだし・・・ちょっと部屋で書いてくるよ」 「えぇっ?!自分で書くものなの?!」 しかも簡単に、と、リナリーが目を丸くした。 「あぁ・・・リナリーはちっちゃい頃に国を出ちゃったから知らないか・・・。 本当は春聯の切り絵だって、子供が遊びながら作るものなんだけどね」 少し寂しそうに笑ったコムイが、ポン、と手を打つ。 「じゃ、ここで書いてあげよう。 道具持って来るから待ってて」 そう言って、バタバタと部屋を出て行ったコムイはすぐに硯や紙を持って戻って来た。 「ゆ・・・床の上で書くんですか?」 こんなスタイルは見たことないと、ミランダが床に毛氈と紙を敷いたコムイをまじまじと見つめる。 「そうだよ! えへへー 注目を集めて嬉しげなコムイが、硯に墨を磨った。 「へぇー・・・そうやってインクを作るんですね。 変な臭い」 「いちいちうるさいなぁ、アレン君は! 悪い子にはお仕置きだ!」 「ひゃっ?!」 目にも止まらぬ筆捌きで、コムイがアレンの頬に猫のようなヒゲを書く。 「鼻も黒く塗ってあげようね ケラケラと笑うコムイが指したアレンに、皆が吹き出した。 「羽根つきで負けてもないのに、お仕置きが来たっちょね!」 「ハネツキ??」 アレンの顔に笑いながら、リナリーがちょめ助に首を傾げる。 「んーっと、こっちで言うバドミントンみたいなもんかねぇ?」 顎に指を当てて、ちょめ助がどうにかわかりやすい説明をと喩えを挙げた。 「羽子板って言うラケットみたいな木の板で、シャトルみたいな羽根を打ち合うんだっちょ。 羽根を落としたら負けで、お仕置きに顔に落書きされるんだっちょよ 正月の女の子の遊びだっちょね。 おいらの店にあるから、明日にでもみんなでやるっちょか!」 「それ、負けたらこんな風にされちゃうんですか?」 猫ヒゲを擦り落とさないようにと、両手をホールドアップの形に拘束されたアレンが、背後のラビを見上げる。 「じゃあ、ラビと勝負しなきゃ!」 「なんでそこで『じゃあ』になるんさ。 まぁ、面白そうだから受けて立つけどさ!」 「んもー!なんだよキミタチってばさー! せっかく目の前で書いてあげようって持って来たんだから、ちゃんとこっちを見なよー!」 あっさりと関心を別に移してしまった子供達に頬を膨らませて、コムイが筆を走らせた。 「ハイ、福!」 「む・・・難しい文字ですね・・・!」 自分には絶対書けないと、ミランダがまじまじと見つめる。 「ウフフ これを斜めの正方形で囲んで、雲の模様を入れてー・・・」 と、文字を飾り立てたコムイは、墨が乾くのを待って『福』の字を逆さまに壁に飾った。 「なぜ逆さまに?」 「天から福が落ちて来るんだよ。ココにね」 不思議そうなリーバーに笑って、コムイはぽんぽんと手を叩く。 「さぁ、子供たち! せっかく分けてもらったんだから、春聯を壁や窓に飾りなさいよ」 「はぁい!!」 彼らが手に手に春聯を持って部屋に散らばると、キッチンに続くドアからジェリーが顔を出した。 「飾り終わったら言ってちょうだい お正月のご馳走運ぶわよーん 「急いでやります!!!!」 アレンと腹ペコのラビが声を揃えたが、しかし、意地悪なコムイが次々と縁起のいい文字や絵を描いて、中々終わらせようとしない。 「んもー!!!! 貼るとこなくなっちゃったから終わっていいでしょ?!」 とうとう癇癪を起こしたアレンに笑って、コムイがジェリーへ声をかけた。 「もういいよーん!」 「はぁい 彼女の声と共にドアが開くや、カバーをかけた大皿からいい匂いが漂う。 「お肉の匂いだ!豚かな!!」 テーブルに皿を置くジェリーの手をわくわくと見つめるアレンが、カバーが取り去られた瞬間、こんがりと焼けた子豚と目が合って、ビクッと歩を下げた。 「ぶ・・・豚・・・・・・!」 「目・・・目が合ったっちょ!!目が合ったっちょ!!!!」 アレンの隣でちょめ助が、きゃあきゃあと悲鳴をあげる。 「ま・・・丸焼き・・・なのかな・・・・・・!」 ちょめ助よりは肉料理に抵抗のないリナリーが、こちらをじっと見つめる豚を見返していると、ジェリーがイタズラ成功とばかり笑い出した。 「びっくりしたでしょぉん これ、火考乳猪(カオ・ルウチュウ)って、広東の高級料理なのん 北京ダックと同じで、皮をカリカリに焼いて食べるのよん 後でお肉も出してあげるわねん そして、と、ジェリーはもう一つの皿のカバーも開ける。 「こっちは英国風ガチョウの丸焼きー 「嫌アアアアアアアアアアアアア!!!!」 また目が合ったと、大騒ぎするちょめ助に皆が呆れた。 「なんさ、日本ってのは、ガチョウの丸焼きも食わないんさ?」 「これは僕、平気です」 おいしそう、と、目を輝かせるアレンの隣からはとっくに離れて、ちょめ助は壁に懐いている。 「だ・・・大丈夫、サチコちゃん・・・? 日本の人って・・・お肉ダメなの?」 ちょめ助のあまりの怯えように、ミランダが優しく背を撫でてやると、彼女はがくがくと震えながら頷いた。 「きっ・・・基本、魚だっちょ!! さ・・・最近は、牛鍋を食べる連中も増えたけっちょ・・・丸焼きとか・・・!」 うずくまって泣き出してしまったちょめ助の頭を、ジェリーが優しく撫でる。 「じゃあ、顔はサチコちゃんに向けないであげるから、ちょっと食べてご覧なさいよん おいしいわよーぅ 「う・・・うん・・・」 ちょめ助が涙目をあげると、既に衝撃から立ち直ったラビとアレンがテーブルにたかっていた。 「俺、豚のせいで酷い目に遭っちまったんだから、真っ先に食う権利があると思うさね!」 「えぇー!! ラビを助けて豚をここまで運んだの僕じゃんー!僕が一番食べる権利あるよ! ねっ!ジェリーさん!!」 「ハイハイ ちゃんと切り分けてあげるから、ケンカしないのよん 騒がしい子供達にクスクスと笑って、ジェリーは客人達を見回す。 「さ まだまだ運んでくるから、みんなもテーブルに着いちゃってぇん エプロンを翻してキッチンへ戻って行ったジェリーは、すぐに大皿を持って戻って来た。 「まだまだあるからねぇん たんと召し上がれ テーブルに所狭しと並べられた美々しい料理の数々に、全員が目を輝かせる。 「さすがだよ、ジェリぽんー! ボク、故郷でだってこんなご馳走、見たことないや!」 手放しで誉めるコムイの隣で、リナリーは興味津々とカオ・ルウチュウをつついた。 「ねぇジェリー? お正月料理なの、コレ?」 「そう言うわけじゃないけどん、いつもお肉を仕入れてるお店から、子豚が1頭入ったけど買う?って連絡が来たから、挑戦しようと思って 味はどうだろうかと、小首を傾げたジェリーに全員が・・・ちょめ助までもが頷く。 「お・・・おいしいっちょ!」 「よかったん カリカリとした食感が気に入ったらしいちょめ助に満足げに頷いたジェリーが、コムイを見遣った。 「コムたん、本場の味と比べてどぉ?」 「本場よりも美味しいよ! ジェリぽん、天才!!!!」 「うん、確かにうまい・・・」 「おかわりっ!!」 黙々と食べるリーバーの代わりに、ラビとアレンが大声をあげる。 「あ、僕、ガチョウも食べる! ガチョウください 「ハイハイ 食欲旺盛なアレンへ嬉しげに笑いかけるジェリーを、リナリーがまじまじと見つめた。 「なぁに? リナリーもガチョウ欲しい?」 首を傾げると、 「それも欲しいけど・・・ジェリーってやっぱり、魔法使いなんじゃない? ただお肉を買いに行ってもらっただけなのに、なんで事件まで解決しちゃうの?」 犯人を捕まえたのもジェリーだし、と、彼女の正体を見抜こうとするリナリーに、ジェリーは笑い出す。 「それは偶然よぉ! アタシ、コムたんがなんの事件を追ってるかも知らなかったし、犯人を捕まえるためにラビを危険な目にあわせようなんて、ちっとも考えないわん!」 ねぇ?と笑みを向けられ、ラビは何度も頷いた。 「姐さんがそんなことするなんて、俺もちっとも思わないさ。 けど・・・なんであれが俺だってわかったんさ? あんな変装させられて、アレンだってわかんなかったのに」 不思議そうに問うラビに、コムイはにこりと笑う。 「それもある意味偶然だね。 彼を追い詰めかねて困っていた所に、キミの事件が現れたんだよ。 つまり、ボクが持ってたピースとキミ達が差し出したピースが合わさって、一つの事件になったってコト」 フォークを弄びながら、コムイは続けた。 「ティキは高価な宝石を大量に奪って逃げていたんだけど、彼自身にはさっさと宝石を売りさばく裁量なんてない。 だからきっと持ち歩いているか、どこかに隠してるんだろうと思って、彼本人を逮捕しようとしたんだけどね、これがまた、警察はあっさり撒かれちゃって。 ボクが仕事を頼んでる子供達は、捜索という面ではいい仕事をしてくれたんだけど・・・相手が相手だけに、向かわせるのはとても危険だったからね。 手控えてしまった隙に逃げられちゃった」 悔しげに床を蹴った音にミランダがびくりと怯え、コムイは慌てて謝る。 「そんな時に、アレン君が飛び込んで来たんだ。 始めは僕も、ラビが誘拐されたのは別の事件だと思って捜査に乗り出したんだけど、消えた場所がイースト・エンドってのが妙に引っかかって。 そしたら留置所であの男に会うじゃないか。 リンク君は間抜けじゃないから、逮捕後はきっと彼の持ち物検査をしただろうし、それで宝石が出なかったんならこりゃ、アレン君達が飛び込んだって場所に宝石は隠してあるなと。 アレン君もリナリーも、ラビを見つけて部屋に飛び込むまでに間はなかったって言うしね。 じゃあきっと、部屋に転がってたって老人がラビなんじゃないかなぁと思ったの。 ラビ、その辺の事情はキミから話してよ」 フォークの先を向けられて、ラビは顔をしかめた。 が、アレンやリナリー、ちょめ助からも興味津々と見つめられて、仕方なく口を開く。 「・・・姐さんのお使いで豚とガチョウを買ったはいいんけど・・・どっちもすっげぇ重くってさ。 馬車が拾える通りは遠かったし、荷運び人がいねぇかなってキョロキョロしてたら爺さんが寄って来たんさ」 「おじいさん?ティキじゃなくて?」 意外そうに聞いたリナリーに、ラビは頷いた。 「コムイとアレンは見たよな、俺が被せられてたすっげ精巧なマスク。 あれは元々、ティキが被ってて、ジジィの振りして俺に近づいて来たんさ」 そして彼は、イースト・エンドにふさわしい小金をせびるような態度で言ったそうだ、 『ついさっき大きな船が着いて、荷運び人は出払っている。 ウチに古い台車があるから、それでよければ持って行くがいい。 その代わり、酒代をくれないか?』 と。 「まぁ・・・あの辺りじゃよくあることだし、阿片窟が酒場を兼ねてんのも珍しくないからさ、つい、ついてっちまって・・・」 「油断したな」 しかし気持ちはわかると、リーバーが頷いた。 「うん、なんか・・・いざとなったら逃げればいいか、って思っちゃいますよね。 あんなおじいさんが相手なら」 ボサボサの白髪と深い皺の刻まれた土気色の肌を思い浮かべながら、アレンも頷く。 「そう、それであの阿片窟の2階に行ったら、フッツーに台車があって、それで安心しちまったんだよな。 金を払うから台車を下まで降ろしてくれるか、って豚とガチョウを持ったまま先に下りようとしたらさ、ジジィの背筋がいきなり伸びて、俺を引っつかんでさ・・・」 驚いたラビが、窓の外へ身を乗り出して助けを呼んだ・・・その場に、アレンとリナリーが居合わせたのだ。 「お前らが気づいてくれたのが見えたし、ちょっとホッとした途端に引き倒されて無理やりアヘンを飲まされて・・・意識が朦朧としてる間に猿轡されてなんか被せられて・・・それがきっと、あのマスクだったんさねー。 ジャケット脱がされたのは覚えてねぇな。 ただ、お前らが来て、騒いでたのは聞こえてたから、必死に呼んでたんけど・・・身体は自由になんねぇし、猿轡されてっからろくにしゃべれねぇし? 担架で運ばれた時、ようやく安心して意識を失くしたんだよな」 その後、目を覚ますとやはり床に転がされていて、必死に助けを呼んでいた所へコムイ達が現れたのだと言う。 「それにしても精巧なマスクだったよねぇ・・・。 私、あのおじいさんは・・・確かに気味が悪くって、あんまり近づきはしなかったけど、マスクだなんて思わなかったよ」 不覚だった、と悔しげなリナリーに、コムイが笑い出した。 「リナリーは、まだマダム・タッソー館を見てないのかい? この近所なのにさ」 「あぁ・・・蝋人形だっけ? 人間そっくりなんて気持ち悪いよ」 駅の側にある蝋人形館の看板を思い浮かべて、リナリーが眉根を寄せる。 しかし、 「あの存在を知ってたから、ボクはあの老人がマスクだって気づいたんだよ。 本当に精巧で・・・館には髪のサンプルだけでもすごい数があるんだ。 今度一緒に行こうか?」 普通の客とは違う見方をしているらしい兄に誘われて、リナリーはこくりと頷いた。 「じゃあ僕もお供・・・!」 「邪魔すんな!!」 敢然と挙手したアレンはコムイのデコピン攻撃に遭って、遭えなく沈む。 「コラッ!コムたん!」 「あぁ、うん・・・まぁ・・・・・・」 ジェリーに叱られて、コムイは気まずげに咳払いした。 「今回はお手柄だったよ、ラビ キミが誘拐されたおかげで、宝石は取り戻せたしね」 今頃はリンクが、夫人へ宝石の返却と事情を説明に行っている頃だ。 夫人は犯人を引き渡せとヒステリーを起こすだろうが、そこは彼のこと、うまく納得させるに違いなかった。 「お手柄を譲ってあげた、せめてもの代償だよね」 苦笑するコムイに、ラビは不満げに口を尖らせる。 「なんだい、誉めてあげたのにさ」 ご不満?と問われて、ラビは頷いた。 「全っ然!嬉しくねーさ!」 この事件・・・全てが仕組まれたものではなく、偶然だったのなら、自分に降りかかった不幸は全くもって純粋なアンラッキーだったということだ。 「アンラッキー・ボーイは俺じゃなかったはずなんに・・・」 じっとりと見つめられたアレンが、ガチョウの足を咥えたまま小首を傾げた。 「ラビ、アンラッキー・ボーイの称号なら、君に譲りますよ?」 「いらねーさ、そんなもん!」 真顔で言ったアレンにラビが反駁し、笑声が沸く。 「ともかく、今回は解決ねん みんな無事でよかったわん 「えぇ、本当によかった・・・! 彼・・・恐ろしい犯罪者なんでしょう・・・? コムイさんはお仕事だからしょうがないとしても・・・あなた達はもう、関わらない方がいいわ・・・」 不安げな目のミランダに見つめられて、ラビとアレン、リナリーが居心地悪げに身じろいだ。 「お願い・・・ね?」 更に言われて、仕方なく頷いた彼らにリーバーが呆れる。 「・・・お前ら、俺がゲンコツしてもちっとも聞かなかったくせに、ミランダの言うことは聞くんだな」 「北風と太陽じゃないのー?」 ケラケラと笑いながら、コムイはテーブルの豚にフォークを突き立てた。 「そうだよ、あんな下っ端には、一々関わらない方がいい」 にんまりと笑ったコムイに、皆の視線が集まる。 「狙うのは大元、千年公・・・伯爵だ!」 決然と言った彼に、アレンとラビが大きく頷いた。 「頑張ってください、コムイさん! 僕、お手伝いします!」 「俺も!!!!」 「お前ら約束はどうした!」 あっさりと願いを覆されて、がっかりするミランダの代わりにリーバーが声をあげる。 が、 「兄さんならできるよ」 にこりと笑って、リナリーが断言した。 「兄さんは・・・私を見つけてくれたんだもん。 だから・・・」 私もお手伝いする、と言った彼女には、コムイも渋い顔をする。 止めようと口を開いた彼を、ちょめ助が暢気に遮った。 「今年の抱負だっちょね!」 「ほうふ・・・?」 って何?と不思議そうなアレンに、ちょめ助が笑う。 「志のことだっちょ! 正月に『今年はこうするんだ!』って決意すんのは、日本じゃ普通のことだっちょ」 その言葉に、アレンの目が輝いた。 「じゃあ僕、一人前の少年探偵になる!」 「少年探偵に一人前があるんかよ!それを言うなら探偵だろ! 俺、今年は一人前の探偵になるさね!」 「アレン君やラビがなれるんだったら、リナリーなんかもう、一人前の探偵だもんね! 兄さんのお手伝いするんだ!」 ラビやリナリーも加わって、わいわいと騒ぐ様にコムイはもう、苦笑しかできない。 「じゃあ、ボクの抱負は・・・」 来年もこの面々で平和に正月が迎えられるように頑張ろうと、コムイは胸の中に誓った。 Fin. |