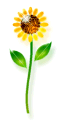8月9日。 数日間の任務ののち、本部に帰還したラビは、あくびを噛み殺しながら方舟の『扉』をくぐった。 「ただいまさー。 なー。報告書後でい?先に寝かせてー・・・」 目をこすりながら階段を下りたラビの頬に、ぷにっと柔らかい物が押し付けられる。 「なんさ?」 視界を塞ぐそれを押しのけると、すぐ傍にリンクの生真面目な顔があった。 「誕生日おめでとうございますJr.これは私からささやかではありますがプレゼントですお受け取りを」 早口にまくし立てたリンクを訝しげに見たラビは、歩を下げて彼が押し付けてくるものをまじまじと見つめる。 いつもよりずいぶんと小さくはあったが、白い髪と顔の傷、それにきかん気な銀色の目は間違いなくアレンのものだ。 「まーた科学班がやらかしたんさ?」 異常事態にすっかり慣れたラビの落ち着いた問いに、リンクは眉根を寄せて首を振る。 「長官のご命令でウォーカーの退行を試みたのですが、失敗しました」 「・・・なんでそんなことしたんさ」 ラビが呆れ返ると、リンクは軽く吐息した。 「以前、神田やワガママ小娘が身体だけでなく、記憶まで退行したことを長官にご報告したのです。 ならばウォーカーにも試して、有益な情報を得るようにと命じられたのですが・・・」 「・・・どうだったんさ?」 興味を引かれて問うが、リンクは残念そうに首を振る。 「神田もワガママ小娘も、偶然の配合でしたので、実用化は難しかったようです。 ホーキ頭に頼むなんて私のプライドが許さなかったため、ペック班長にお願いしたのも良くなかったのかも知れませんね。 常識人には作れない代物だったのでしょう」 「・・・常識人」 色々言いたげに薄い笑みを浮かべるラビに、リンクは咳払いした。 「まぁ、子供化しただけでも、彼が十分に優秀な科学者であることは証明できました。 しかしこの子豚・・・」 リンクが忌々しげに首根っこを掴んでぶら下げたアレンは、じたじたと暴れている。 「はなせはなせはなせ!!ぎゃああああん!!!!」 「この際、礼儀を教えてやろうとしたのに全く反抗的な子供で。 ただのうるさいクソガキの面倒を見るほど私は暇ではありませんので、明日が誕生日の君にプレゼントしましょう」 「なんさそれー!!!!」 ぐいぐいと押し付けられたアレンを抱えて、ラビが絶叫した。 「普段虐げられているのですから、この機に思う様いぢめて鬱憤晴らしでもするといいですよ。 では」 「俺そこまで悪い子じゃないさっ! ちょ・・・おい!リンクー!!」 あっという間に影さえも見えなくなったリンクの非情さに呆然としていると、『扉』から伸びるステップを軽やかに下りて来たブックマンが、スキップでもしそうな足取りで寄って来る。 「おや、可愛い子供だな。もらったのか?」 師ののんきな口調と大仰に小首を傾げる仕草に苛立って、ラビは舌打ちした。 「あぁ、もらったけど・・・アレンって時点で不幸のプレゼント決定さ!」 棘のある口調をしかし、ブックマンは笑い飛ばす。 「凶を転じて福となす。 よいよい♪」 上機嫌で頷く師を、ラビは気味悪げに見下ろした。 「ジジィ・・・いい加減、落ち着いたらどうさ? あんまりハイテンション過ぎてキモチ悪いさ」 「何を言うか! これが喜ばずにいられようか!!」 大仰に両腕を広げ、身を翻したブックマンの髪が嬉しげに揺れる。 「リナ嬢に頼んで、室長自ら開発に携わってもらったおかげでどうじゃ! 私の頭に再び、髪が戻って来たぞい!!」 くるくると回るブックマンの背を追いかけるように、長い総髪がふわふわとなびいた。 「まだ定着率が悪いために、毎日の投薬は欠かせんが、それでもこの感触が戻っただけで私は幸せだ!」 「あー・・・はいはい。よかったさねー・・・」 数日前の誕生日に、コムイ特製の育毛剤をもらってからと言うもの、ブックマンの機嫌は下がることを知らない。 「まー俺も、ジジィの機嫌がいいのは嬉しいさ。 ちょっとしたことでどつかれずにすむからさ」 いつの間にかおとなしくなったアレンを抱えなおして、ラビはため息をついた。 「・・・で? お前はただちっさくなったんさ? それとも記憶退行してるん?」 ぷにぷにとした頬をつつきながら問えば、アレンはきっと睨んでくる。 「おかし!」 「あ? 報酬先払いってか」 ラビが苦笑してポケットから棒つきキャンディーを取り出すと、アレンは嬉しげに受け取った。 「リンクからはもらわんかったんか? あいつのことだから、さぞかし大量のケーキで釣ろうとしたろ」 「・・・・・・だって、わるいひとだもん」 キャンディーをくわえたままの、不明瞭な呟きにラビは耳をそばだてる。 「なんさ、ヤなことでもされたさ?」 キャンディーでぷっくりと膨れたアレンの頬をつつきながら、ラビは人の多い方舟の間を出た。 それとなく人気のない方へと歩いていくと、上機嫌のまま、ブックマンもついて来る。 「・・・わるいこと考えてたにきまってるもん」 中庭に面した回廊を渡る間、ぽつぽつと話すアレンの小さな頭に、ティムキャンピーが乗った。 「お前・・・どっかで様子でも窺ってたんさ?」 リンクがアレンの過去の記憶を探ろうとしたなら、クロスの・・・いや、14番目が放った監視役とも言うべきティムキャンピーが散々邪魔したことだろう。 リンクによって排除されたらしいゴーレムはしかし、特に破壊の痕もなく、いつも通りアレンの頭に乗っていた。 それでも、 「いぢめられたさ?」 と言うラビの問いにティムキャンピーは、泣きながら激しく頷く。 「それで『わるいひと』か」 逆効果だったなと、ラビは笑い出した。 「ところでアレン、俺のコトわかるんさ?」 アレンが咥えるキャンディーの棒を弾いてやると、ムッとした目で睨まれる。 「しるもんか」 「ふーん。 じゃあ、こいつのことはわかるんか?」 ティムキャンピーを指すと、アレンは首を振って、それでも手を伸ばした。 「しらないけど・・・すき」 「 嬉しげに尻尾を振りながら、ティムキャンピーがアレンに身体をすり寄せる。 「そっか。 ところでアレン、今いくつさ?」 その問いには、困惑げな目を向けられた。 「わかんね?」 成長したのちも実年齢は知らないと言っていたのだから、当然かと頷きかけたラビに、アレンが小首を傾げる。 「おれ・・・アレンじゃない」 「は?!」 その新たな情報には、ブックマンも耳をそばだてた。 「えっと・・・じゃあ、名前は?」 「なまえなんかない。なんとでも呼べばいい」 小さな子供のくせに、妙にやさぐれた口調にラビは思わず黙り込む。 と、代わりにブックマンが、ラビに抱かれた彼に歩み寄った。 「私たちもだぞ」 「へ?」 小柄で奇妙な老人を見下ろして、アレンはまた首を傾げる。 「私たちにも、名前なんぞない、と言ったのだ。 その場その場で、適当な名前をつけている」 「お・・・おい、ジジィ!」 いくらはしゃいでいるとはいえ、他人にぺらぺらと血族の話をするとは、彼らしくなかった。 しかしアレンはなにやら考え込むようにブックマンを見つめている。 「・・・おれだけじゃないんだ」 「珍しいことではないの。 ちなみに、おぬしはここでは『アレン』と呼ばれておる。 面倒だから、『アレン』と呼ぶぞい」 「犬のなまえだけどな」 ぷいっとそっぽを向いた彼の口調は不満げだが、その顔はまんざらでもない様子だった。 「ではアレン、犬の名前とは? そういう名の犬を、誰かが飼っておったか」 「うん。新しいピエロの相棒だよ」 「ほうほう。 そのピエロとはどんな芸をするのだ?名前は知っているのか?」 「うん。すごくうまいぞ。 名前は・・・マナだったかな?」 アレンの口から出た名前に、ラビが苦笑する。 さすがに師は老獪で、ついさっきまで固かったアレンの口を、すっかり滑らかにしてしまった。 今まで彼が積極的には語ろうとしなかった情報を次々に聞き出した上、アレン自身も忘れていただろう新しい情報を次々と語らせる。 「そうかそうか」 好々爺の仮面の下でほくそ笑む師は、機嫌よくラビを見上げた。 「監査官は押し付けたつもりだろうが、よいプレゼントをもらったな、ラビ。 後は任せたぞい」 「これ以上、何を聞けってか」 世話だけ押し付けてさっさと行ってしまった師の背を、ラビは恨めしげに見送る。 「あぁ、俺・・・ようやく眠れると思ったんに! 昨日徹夜しちってマジ限界なんに・・・そだ」 ふと気づいて、ラビはアレンの頬をつついた。 「お昼寝するさ、アレン! 子供は昼寝!」 「ねむくない」 きっぱりと言われて、ラビが舌打ちする。 「俺は眠いの! 別に一緒にいる必要ねーんだから、俺が寝てる間はジェリー姐さんのトコにでも行ってろよ。 姐さんなら散々可愛がってくれっさ」 と、床に下ろそうとしたアレンは、なぜかラビにしがみついたまま離れようとしなかった。 「・・・なんさ、この白コアラは」 「・・・・・・迷子になる」 憮然とした口調に、ラビは思わず吹き出す。 すっかり忘れていたが、アレンの迷子癖はこの頃から深刻だったようだ。 「そっか、今のお前にはココ、初めての場所だよな」 未だクスクスと笑いながらアレンを抱え直したラビは、食堂へ向かう。 「ジェリー姐さんはお前のことがお気に入りで、お前も姐さんのことが大好きなんさ。 ちょっとくらいのワガママは笑って聞いてくれっから、せいぜい甘えるといいさね」 「ふん・・・そんな人がいるもんか」 やさぐれた物言いに、ラビは目を見開いた。 「お前・・・ちっさい頃はそんなにひねくれてたんさね! 疑わんくても、ホントに姐さんはお前のこと大好きさ」 なんなら、と、ラビはにこりと笑う。 「騙されたと思って、甘えてみ?」 「やだよ・・・! こんな手をしてちゃ、みんな気味悪がるだけだし、いつの間にか髪も白くなって顔に傷まで・・・! ぜったいに、こっちくんなっていわれる!」 「んなコトねーよ!」 即座に否定したラビは、アレンの髪をくしゃくしゃとかき回した。 幼い頃のアレンがどんな容姿をしていたか、ラビは知らないが、コンプレックスを持っていたことは確かなようだ。 「お前はそんな容姿って思ってっかもだけど、10年後くらいのお前は、そんままで女子に人気だぜ? 腹黒い似非ジェントルマンのクセに、女子には優しくて恥ずかしげもなく褒めちぎるからな。 あっという間に篭絡した美女達にちやほやされやがって・・・こんちくしょー!」 「ぎゃあん!!」 思いっきり頬をつねられたアレンが泣き声をあげた。 「なにすんだよぅ!」 「ちょっとしたジェラシーさ。 俺の方がぜってーカッコイイのに、俺よりモテるし・・・強いし?」 「え?!なに?!」 小声の呟きを耳ざとく捉えて、アレンが身を乗り出す。 「・・・なんでもねーさ!行くぜ!」 「なんていったんだよぅ!!」 「うっさいさ! そのロンドン訛りやめろっつったの!」 今の彼はきれいなクイーンズ・イングリッシュを使うが、この頃は酷いロンドン訛りだな、と、情報を脳裏に書き込みながら、ラビは食堂へ向かった。 すると案の定、アレンの出現を待ち構えていたジェリーが、カウンターの中から小走りで出てくる。 「きゃあん アレンちゃん、ちっちゃくなってかんわいいいいいい 「ぴっ?!」 筋骨隆々たる身体のどこから出てくるのかと思う甲高い声に怯え、固まったアレンをジェリーは、ラビの手から取り上げた。 「リンクちゃんに聞いてたんだけどぉん、ホントにちっちゃくなったのねぇん アレンちゃん 嘘だ、と、蒼褪めた顔が語っていたが、否定しようにも恐怖のあまり、声が出ないらしい。 凍りついたアレンにラビは吹き出した。 「な?言ったろ、アレン? お前、すんげーもてるんだって!」 くすくすと笑いながら、ラビはジェリーの肩を叩く。 「姐さん、俺、任務終わったばっかでねむてーから、子供の世話は任せていいかな?」 「もちろんよぉ! アタシがばっちり面倒見るからねぇん ね ぎゅう、と抱きしめられたアレンが、とうとう泣き声をあげた。 「ア・・・アラッ! どーしたのん?」 自分が原因とは思わないジェリーの腕の中で、アレンが身体を仰け反らせて泣き喚く。 「あー・・・こいつ、人見知りみたいなんさ! なんでか俺には懐いてんだけど」 慌ててごまかし、再びアレンを受け取ろうとしたラビは、いきなり背後から押しのけられた。 「こども・・・子供の声だわ・・・! あぁ 「ミ・・・ミランダ・・・?!」 見るも無残に痩せ衰え、落ち窪んだ眼窩の中にある目だけを異様に光らせながら、骨と皮ばかりに見える指を震わせつつアレンへと手を伸ばすミランダの姿に、ラビが息を呑む。 「ど・・・どうしたんさ、そんなに衰弱しちまって・・・!」 「・・・わたし・・・身も・・・心も・・・荒んでしまって・・・癒しが欲しいの・・・! ふにふにほっぺ触らせてぇ・・・!」 「やああああああああ!!!!ぴぎゃあああああああ!!!!」 怯えて泣き喚くアレンを慌ててジェリーから取り上げたラビが、ミランダの手の届かない場所にまで抱え上げた。 「ミランダッ・・・! アレンが怯えてっから!やめたげてさ!!」 その言葉通り、アレンはラビの頭にしがみついて震えている。 「お願い・・・ちょっとでいいのぉ・・・! ふにふにほっぺに触らせてぇ・・・!」 「ちょっ・・・マジ怖っ!! 冥府から追っかけてくる亡霊みたいになってんさ!!」 普段のミランダを知っているラビですら怯える形相に、アレンは命の危険すら感じて泣き喚いた。 「お・・・落ち着け、アレン! ミランダも!! こっちの子供は怯えきってっから、ティモシーでも触りに行けばいいじゃんか!!な?!」 言うやぴたりとミランダの手が止まり、落ち窪んだ目がカッと見開かれる。 「ひっ?!」 その迫力にはジェリーまでもが怯え、カウンターの影に隠れてしまった。 それでも恐々と見つめる先で、ミランダは血の気を失った手を握り締める。 「あの子はダメです・・・! 交換条件に・・・胸を触らせろって・・・!」 「じゃあ俺も、アレン触らせる代わりに触ってい?!」 「やだあああああああああ!!!やああああああああああ!!!!」 早速売りに出そうとするラビの手の中でアレンが大暴れするが、幸い、ミランダの方から手を引いてくれた。 「ですから! そういう条件は・・・!」 よろよろと歩を引いたミランダが、テーブルにぶつかってひっくり返る。 「ミランダ!」 「んまぁ!大丈夫?!」 ラビだけでなくジェリーも駆け寄って来たが、頭でもぶつけたのか、ミランダは床の上に仰向けになって目を回していた。 「救護班! ミランダが大変よぉん!」 ジェリーの要請で駆けつけた救護班が、ミランダをストレッチャーに乗せて病棟へと駆け去っていく。 その様に、ラビは呆れ返った。 「ホント、どうしちゃったんさ、ミランダは。 今回の任務、きつかったんかな?」 「随分長いこと行ってたのは確かねぇ・・・。 あの様子じゃ、ろくに寝食できなかったんじゃないかしらん」 頬に手を当て、小首を傾げるジェリーにラビも頷く。 あの尋常ではない痩せ方を見れば、過酷な任務だったろうことは明らかだった。 「アレンちゃん、ミランダが来るのを見て怯えちゃったのねぇん」 ジェリーの楽観的すぎる解釈を否定しようと開いたアレンの口に、ラビが棒つきキャンディーを入れる。 「ホントに売ったりしねぇから、そんなに泣くんじゃないさ」 あからさまに嘘くさいことを言うラビを涙目でじっとりと睨んだアレンは、口からキャンディーを引き抜いた。 「おれだってつぎは・・・『ほっぺにさわりたいならおれもさわる』っていってやる!」 「元に戻った時、激しく後悔すっからやめとけ」 乾いた笑声をあげて、ラビは肩をすくめる。 「ここの連中は、心神耗弱を酌量してくれっほど優しくないさ」 「しん・・・?」 難しい言葉を理解できず、アレンが困ったように首をかしげた。 「ま、難しいことは後でさ、おまえ、ハラ減ってねーの?」 「そぉよん なに食べるぅ?アレンちゃんの好きなもの、なーんでも作っちゃうわよん、アタシ ジェリーの言葉に、いつもなら狂喜するアレンが、今日はラビにしがみついて顔を背ける。 「あー・・・姐さん、ゴメン。 こいつ、この頃は人見知りが酷いみたいさ」 「あらぁん・・・そぉなのぉ・・・」 残念そうに肩を落とした彼女を、アレンは見ようともしなかった。 「ダメだ、こりゃ。 とりあえず、俺の部屋で預かるさ。 アレン、昼寝しねーならそれでいいから、俺の睡眠邪魔すんな」 「アンタは食欲が睡眠欲に負けるものねぇ」 苦笑しながら厨房に戻ったジェリーが、カバーをかけたトレイを持って戻ってくる。 「起きたら食べなさい 「さっすが姐さん!! 愛してるさー 歓喜して受け取ったラビは、片手にトレイを掲げ、片手にアレンを抱えて部屋に戻った。 「あれ、ジジィどこ行ったんさ?」 先の戻ったはずのブックマンの姿がなく、ラビは積み上げられて今にも崩れそうな新聞紙の上に貼られたメモを見遣る。 「んーっと? 『ちょっと街までナンパに行ってくる』って、ジジィが色ボケやがって! 袋叩きにされるのがオチさね!」 腹立ち紛れに新聞紙の山を崩したラビは、なんとか見えるようになったテーブルの上に軽食のトレイを置いた。 「じゃー俺、寝るから部屋のもんでテキトーに遊んでろ。おやすみ」 言うやさっさとパジャマに着替えたラビは、ベッドに入った次の瞬間には寝入っている。 「すげ・・・!」 あまりの早業に呆れたアレンは、荒れ果てた部屋の中を恐々と見回した。 今のアレンにとっては見たこともない文字で書かれた新聞が天井近くまで積みあがり、少しの振動でも崩れ落ちそうだ。 こんな圧倒的質量に埋もれては、小さなアレンなど簡単に圧死するに違いなかった。 新聞に覆われた床をそろそろと這う彼の頭に、ティムキャンピーがちょこんと乗る。 「なぁ、おまえ・・・鳥なのか?」 触るとぷにぷにとして柔らかいが、羽毛の感触ではなかった。 もっと滑らかな、石のような感触だが、それにしてはこの柔らかさが不可解だ。 「へんなの」 とは言え、気に入った様子でアレンは、ティムキャンピーを撫で続けた。 しかしそれにも飽きると、アレンは改めて部屋を見回す。 新聞紙に埋もれている灰色の部屋にも、所々に色彩があった。 変な絵だったり、奇妙な仮面だったり、恐ろしげな人形だったり・・・。 「うっわ、なにこれ!毒?!」 唯一整理された鏡台の引き出しを開けると、劇薬を意味する緑の瓶が並んでいた。 「こいつとあのじいちゃん・・・人ごろしなのか?」 恐々とベッドの上のラビを見るアレンの前で、ティムキャンピーが身体ごと横に振れて否定する。 「そっか・・・よかった・・・」 ほっとしたアレンが引き出しを戻そうとするが、奥で何か引っかかってしまったのか、うまく行かなかった。 「うん・・・しょ!!」 全体重をかけて力任せに押し込むと、引き出しは戻ったが中でガラスの激しくぶつかる音がする。 「や・・・やばっ!!」 中を確認しようともう一度引き出しに手をかけるが、ガタガタと揺れるだけでアレンの力では引っ張り出すこともできなかった。 しかも、奥の方から割れたガラスの音と共に、奇妙な臭いが漂ってくる。 「し・・・しーらない・・・!」 蒼褪めながらまたも新聞紙を押しのけて物色していると、手にふわふわした物が当たった。 「なんだ?」 掴んで引き寄せたのは、茶色い毛並みのクマのぬいぐるみだ。 「ふかふかだぁ・・・!」 ぬいぐるみは小さなアレンの身体が収まるほどに大きく、抱きしめると丁度腕の部分が頭に当たって、撫でられているようだった。 「きもちい・・・!」 抱きしめているとなんだか安心できて、そのまま眠りそうになる。 その時、 「アレン・・・くぅ・・・ん・・・! ここに・・・いるんでしょぉ・・・!」 ドアの外から恐ろしい声が聞こえて、アレンは飛び上がった。 「ああああ・・・あのオバケみたいなひとだ!! ラビ!!ラビ!! オバケがきたよ!!」 怯えながらベッドによじ登ったアレンが、震える手で懸命に揺するも、ラビは全く起きようとしない。 「ラビー!!」 ドアの外に声が聞こえては困るからと、潜めた声では必死に呼びかけても無駄だった。 何しろ彼は、焦れたミランダがドアを激しく叩く音にも目を覚まそうとしない。 「ねぇ・・・いるんでしょぉ・・・! このドア・・・開けてよぉ・・・・・・!」 「ひぃぃぃぃぃぃぃっ!!」 ノブを掴んでガタガタと揺する音が恐ろしく、アレンは今にも飛び出しそうな悲鳴が漏れないように、両手で口を覆った。 と、ティムキャンピーが長い尻尾の先でぬいぐるみを指す。 「そ・・・そうだ・・・! ここに隠れれば・・・!」 ドアを破られてもきっと見つからないはずだ。 ティムキャンピーが鋭い歯で切ってくれた背縫いからオガクズを掻き出し、アレンはクマの中に潜り込む。 それだけでは不安だからと、崩れ落ちた新聞紙の山の中にまで潜り込んだが、ミランダの声とドアを揺する音、更にはガリガリと爪で掻くような音までは遮ることが出来なかった。 「こ・・・こわいこわいこわいこわ・・・っ?!」 ガタガタと震えるアレンの小さな耳が、ごとりと、金属の落ちる鈍い音と振動を捉える。 ぬいぐるみの腹の中、両手で口を覆い、息を潜めて聞き耳を立てていると、ギィ・・・とドアの軋む音がした。 「開いたわ・・・アレンくぅん・・・・・・」 ・・・声を限りに叫びたい衝動になんとか耐えたのは、裏地でも心地よいぬいぐるみの感触が、わずかながら守られていると言う安心感をくれたおかげだ。 隠れているのだから見つかるはずはないと自身に言い聞かせ、懸命に息を殺して様子を窺った。 と、ドサドサと言う新聞紙の山が崩れる音が、だんだんとアレンの元へ近づいてくる。 「・・・っ!!」 「アレンくぅん・・・?どこに隠れているのぉ・・・?」 ドサドサとまた、新聞紙の崩れる音がした。 「ここぉ・・・?」 次々に山を崩しながら、彼女はアレンの隠れる場所に近づいてくる。 「あら・・・」 アレンの真上で、彼女の乾いた声がした。 「可愛いクマさん・・・ 頭をそっと、撫でられる感触がする。 彼女が癒しを求めているなら、当然惹かれるだろう物に隠れてしまったことを、アレンは激しく後悔した。 「ふふ・・・抱っこすると気持ちい・・・あら?」 オガクズではない感触に気付いたのか、ミランダの手がぬいぐるみの身体を何度も撫でる。 アレンは今にも号泣しそうな口を必死に押さえ、額に汗を浮かべながら震えそうになる身体を固くした。 そんな彼の努力など頓着せず、ミランダはぬいぐるみごとアレンを抱える。 「重い・・・!随分中が詰まっているのねぇ」 中に隠れていることがばれたのではなかったのかと、ほっとしたアレンの元へ、更なる救い主が現れた。 「ミランダ! あんた、病棟抜け出してなにやってんのよ!!」 ぬいぐるみの中に隠れているアレンからは見えないが、やけに太い女の声だ。 どすどすと床を揺らす振動が足音だと気付くのに、少しかかった。 「キャッシュさん・・・でもぉ・・・!」 「でもじゃない!」 声と共に、彼女が勢いよく取り上げたぬいぐるみから零れ落ちそうになったアレンは、慌てて裏地にしがみつく。 そのわずかな動きと重さに気付いたのか、キャッシュはぬいぐるみごとそっと、アレンをラビの隣に寝かせてくれた。 「ホラ!病棟に帰るよ! さもないと・・・!」 きっと、キャッシュはミランダを睨みつける。 「あんたがラビの寝込みを襲ってたって、言いふらすからね!」 「や・・・やめてぇ・・・!」 消え入りそうな声で哀願しつつ、ミランダはキャッシュに縋った。 「私はただ、ふにふにほっぺに触りたかっただけなのぉ・・・! ふにふにの・・・ぷにっとした・・・ぷにぷに・・・ 「あんたなにあたしの腹に擦り寄ってんの――――!!!!」 大声で怒鳴られてもしかし、ミランダはキャッシュの腹にしがみついたまま、その感触を嬉しげに味わっている。 「キャッシュさん すごく・・・癒されます 「うるせー!!!!」 ごく当然のように言われたキャッシュは、屈辱の涙に頬を濡らした。 恐怖劇の亡霊のようなミランダと、姿は見えなかったが太い声の女の大声にも全く目を覚まさず、ラビは眠り続けていた。 「・・・なんでまだ寝てんだ?」 ようやくぬいぐるみの中から出てこられたアレンが不思議そうに見つめるが、彼はつついても揺すっても起きそうにない。 「ちぇっ。オレもつかれた・・・」 ミランダから受けた恐怖は小さな身体から随分と体力を奪っていた。 オガクズがなくなって、ぺったりしてしまったぬいぐるみを抱え、アレンもベッドの上に転がる。 ミランダが壊したドアは、彼女らが去った後に妙な格好の連中がやって来てすぐに直してしまったし、ミランダ自身もキャッシュとかいうぷにぷにに連れて行かれたから大丈夫だ。 そう思うと、安堵した瞼がとろとろと落ちてくる。 ややして呼吸も寝息に変わり、ティムキャンピーも傍に転がって、穏やかな夏の日差しが傾くまで、三人は眠りの国に滞在した。 目覚まし代わりの腹時計が鳴って、小さなアレンは目を覚ました。 「・・・オナカすいた」 むくりと起き上がると、ラビはまだ寝ている。 「いつまで寝てんだよ!」 苛立ち紛れに頭をはたいてやると、もぞもぞと動いて眠そうな目が開いた。 「・・・ハラへった」 アレンと同じことを呟いて、ラビがのっそりと起き上がる。 「アレン、姐さんがくれた皿取ってー・・・」 「あぁ、そういえば・・・ってあのひと、ねえさんなのっ?!」 「そこは突っ込まんでいいから」 気にするな、と言われても気になるが、特に反論もせずにアレンは辛うじてテーブルに載ったままだった皿を持って来てやった。 「どれどれ・・・バゲットの中身はチーズに生ハム あ、こっちはローストビーフさ さすがのチョイスさね、姐さん カバーを取るや、早速バゲットを口に運んだラビは、いつまでも皿を見つめたまま手を出そうとしないアレンを不思議そうに見る。 「食わねえの?」 「く・・・くっていいの?」 頬を紅潮させ、キラキラと輝く目でバゲットを見つめていたアレンが身を乗り出した。 「いいもなんも・・・いつもはなんも言わんでも、勝手に取ってくだろ」 「そうなんだ・・・?」 意外そうに呟いて、アレンは小さな手をおずおずと伸ばす。 おいしそうなバゲットは、口に入れるとびっくりするほどおいしかった。 「これっぽっちじゃ足りんだろうから、皿返すついでにアフタヌーンティでも・・・」 「まだ食べていいのっ?!」 カッと見開かれた目がこれ以上は無理なほど輝く。 アレンがここまで感動する理由をなんとなく察したラビは、いつもより小さな頭を撫でた。 「言ったろ、姐さんはお前のことが大好きだって。 遠慮なくなんでも作ってもらえよ」 「うんっ・・・!!」 むぐむぐとバゲットを頬張りながら頷くアレンに、ラビが笑い出す。 「今度は怖がらないで、愛想よくしろよ」 「うんっ!!」 おいしいバゲットにすっかりほだされたアレンが、現金にも頷いた。 「しっかし記憶まで退行したってのは、俺らにとっては便利だけど、お前には不便さね。 早く元に戻してやんねぇとな」 元に、と言う言葉にぎくりとして、アレンがバゲットを喉に詰まらせる。 「どした?」 ラビの問いには懸命に首を振ったが、そっと上目遣いに見遣った視線を辿られてしまった。 「・・・クマがぺっしゃんこさ」 「ご・・・ごめん・・・」 背縫いを解かれ、オガクズを掻き出されてしまったクマのぬいぐるみをぶら下げるラビへ、アレンがうな垂れる。 「俺が寝てる間になんかあったんさ?」 理由もなくこんなことはしないだろうと思って問うと、アレンは頷いてミランダのことを話した。 「・・・牡丹灯篭かよ。 魔除けの札でも貼っときゃよかったかな」 本物の亡霊じゃないから無理かと、ラビは苦笑する。 「お・・・怒んないのか?」 「なんで?」 逆に問われて、アレンが言葉に詰まった。 「オガクズくらい、また入れてもらえばいいさ。 ついでに毛並みのメンテもしてもらおっかな。 ユウにハンスおじさん紹介してもらわんとー♪」 ラビが全く怒っていないとわかって、ほっとしたアレンが小首を傾げる。 「ハンスおじさん・・・?」 「これ作った人さ」 最後のバゲットをくわえて、ラビはぬいぐるみを空の皿に持ち替えた。 「んじゃ、皿返しに行こうぜ」 「うん・・・あ、でも!」 ラビの後ろに着いて行こうとしたアレンが足を止める。 「まだオバケ・・・いる?」 「それは・・・どうだろうな」 いるかもしれない、と笑って、ラビは怯えるアレンの背を押した。 「また襲われても、今度は姐さんが追い払ってくれるさ! だから姐さんにはしっかりと媚を売っておくさね」 「まかせろ!」 小さな胸を張ったアレンに笑いながら、ラビは部屋を出る。 すると食堂へ向かう途中、宿舎へと向かうリナリーと鉢合わせた。 「ラビ!もう起きたんだ!」 珍しい、と笑う彼女に、ラビが頷く。 「こいつに起こされなきゃ、もっと寝てたさね」 「きゃあ アレン君、ほんとにちっちゃいー 方舟の間のスタッフから、アレンが子供に戻ってしまったことは聞いてはいたが、実際に見ると本当に小さくて、しかもラビの足にしがみついて隠れようとする様が可愛かった。 「人見知りしちゃってるの? 可愛いー しゃがみこんで視線を合わせると、頬を染めたアレンがぷいっとそっぽを向く。 「こっち向いて ねーえー 絶対ヤダ、と首を振ってラビの背に隠れてしまったアレンに笑って、リナリーは立ち上がった。 「リナ、今帰ってきたんか? 俺より前に出たのに、随分かかったさね」 ラビが何気なく言った途端、リナリーのこめかみが引き攣る。 「なにそれ!信じらんない!! 私が今日まで帰って来れなかったのはラビのせいなのに!!」 詰め寄られ、仰け反ったラビが、愛想笑いを浮かべた。 「えっと・・・俺のせいって?」 「ラビが! 今年の誕生日は! ベルギーの王室御用達チョコレート店の季節限定ボックスがいいって言ったんじゃないか!!」 「あぁ・・・言ったさね。 そんなに買えなかったん?」 「そんなに買えなかったんだよ!!」 大声で怒鳴って、リナリーは小脇に抱えていた大きな箱をラビに突きつける。 「ちょっと早いけど、先にお誕生日プレゼント! 3日だよ?! 3日間、開店前に並んでようやく買えたんだよ?! 他のチョコレートならまだあるよ、って言われたけど、ラビが季節限定ボックスって指定するからがんばって並んだんだよ!! さすがに3日目ともなると、店員さんが同情して優先してくれたよ!!」 「ご・・・ご苦労さん・・・!」 リナリーの剣幕に歩を引きながら、ラビは彼女の頭を撫でた。 「ホント、ありがとな! 大事に食べるさー 「うん・・・」 膨らませた頬を染めて、リナリーが頷く。 「リナ、俺ら食堂に皿を返しに行くんだけど、お前も行くさ? 3日も並んだんじゃ、疲れたろ」 「別に、ずっと並んでたわけじゃないよ。 お店から近い場所にあるホテルに泊まって、開店前に並んだだけだもん」 でも・・・と、リナリーは長い戦いを思い出して肩を落とした。 「地元民、すごいよ・・・! 夜中にはもう、並んでたよ・・・!」 いつ寝てるんだろうと、首を傾げるリナリーの背を、ラビが笑って押す。 「じゃ、がんばったご褒美にリナにもチョコレート分けてやんないとな!」 「それは私の分も買ってきたから大丈夫。 アレン君の分も買ってきたからね!」 どーだ!と、胸を張るリナリーを、アレンもラビの影からおずおずと見上げた。 「あ!やっと顔出してくれた!」 すかさず手を伸ばしたリナリーに抱き上げられ、アレンは顔を真っ赤にする。 「わぁい アレン君、軽いー 「リナ、そいつ迷子になるからそのまま運んでくれ」 「いいよー アレン君、お姉ちゃんと行こうねー 軽々と抱っこされたことが悔しいのか、無言で顔を背けるアレンにリナリーが笑った。 「もー! そんなに不満そうにしなくたって、食堂に着いたらジェリーと代わってあげるよー」 そう言ってやると、それは嫌だとばかりにしがみついてくる。 「えぇっ?!ジェリーより私がいいの?!ホントッ?!」 感動のあまり声を裏返して、リナリーはアレンを抱きしめた。 「ヤッター! 初めてジェリーに勝ったよ! アレン君、このままでいればいいよ!」 「そりゃダメだろ」 ラビが呆れるが、リナリーは首を振る。 「私が理想の男の子に育ててあげる!」 「どこの光源氏だお前は」 キラキラと目を輝かせるリナリーに苦笑して、ラビは先に食堂へ入った。 「姐さん、ミランダはどこ行ったんさ?」 アレンが怯えるからと、先に彼女の行き先を尋ねると、カウンターの中からジェリーが、 「精神状態が良くないからって、キャッシュちゃんが病棟に連れてって、監視してるわよん」 と笑う。 「なんでも、2週間もの間眠れずにイノセンス発動し続けたんですってぇ! 帰ったんだから休みなさいって言われたのに、ずっと悪夢を見ちゃって眠れなくなったらしいのん。 今、安定剤で眠らせてるそうよん」 その情報に、ラビは唖然とした。 「俺・・・1日徹夜したくらいでへこたれてゴメンナサイ・・・!」 「まぁ、アンタは頭の使い方が人と違うから、糖分と睡眠は欠かせないものねぇ」 そつなくフォローして、ジェリーはカウンター越しにアレンを見遣る。 「アレンちゃん、ラビが寝てる間に襲われたんですってぇん?大丈夫だったぁん?」 「すんげー怖かったってさ」 ケラケラと笑いながら、ラビはリナリーに抱っこされたアレンの頭を撫でてやった。 「おっきくなったらオバケも怖くなくなるから、早く元に戻るさ」 「ダメだよ! 私が理想の男の子に育てるんだってば!!」 ラビからアレンを引き離し、リナリーが大声をあげる。 途端、食堂中の視線が集まった。 「ロブ! 兄さんにご注進しちゃダメ!」 先制したリナリーの声に、無線ゴーレムを取り出そうとしたロブが慌てて頷く。 「そいつ、リンクから俺へのプレゼントだったんけどね・・・」 リナリーに取られてしまったと、ラビが苦笑した。 「そいやリンクは?」 「久々にアレンちゃんのお世話から解放されたって、中央庁に戻ったわよん。 別件のお仕事が入ったんですってぇ」 ジェリーはさすがの情報通で、団員だけでなく中央庁の人間の行動まで把握している。 「そっか。 じゃあ、うちのジジィどこ行ったか知んね? ナンパしに行くって出かけたんけど」 「アラァ!おじいちゃんなら・・・」 と、ジェリーは食堂の窓の外、テラス席を指した。 「ランチタイムの後に戻って来てから、ずっとあそこで黄昏てるわよん 「ナンパ失敗したんさね!」 こちらに背を向けて座る師の、ちんまりとした姿にラビが意地悪く笑う。 「ジジィジジィ アレンをリナリーに任せて一人、軽やかな足取りでブックマンの元に駆け寄ると、彼は不機嫌な顔でラビを見上げた。 「なんじゃい、はしゃぎおって」 「はしゃいでたんはジジィじゃんか! なんさ、ナンパ失敗したんさ?」 クスクスと笑うラビを、ブックマンが睨みつける。 「・・・少々若さが足りんかっただけだ。 髪も戻ったことだし、元通りの赤に染めれば・・・」 「やめてさ、暑っ苦しい」 すかさず手を振ったラビに、彼はむぅ、と口を尖らせた。 「では、金髪がよいかのう」 「どんだけ派手好きなんさ。ちったぁ年を考えて・・・」 「では黒だな。 黒に染めよう。そうしよう」 うむ、と頷いたブックマンが、椅子から飛び降りる。 「・・・あぁ、そうじゃ」 とことことラビの前を過ぎようとして、彼は足を止めた。 「ナンパのついでに書店に寄っての、色々注文してきたぞい。 明日には図書館に届くので、好きにするがいい」 「マジで!サンキュ、ジジィ!!」 師からのプレゼントにラビが狂喜する。 彼のことだ、ラビの欲しい本を入手しうる限り集めてくれたに違いなかった。 「明日が楽しみさ 後は・・・」 食堂に戻ったラビは、きょろきょろと部屋を見回すが、目当ての姿がない。 「姐さーん!ユウはー?!」 「まだ任務から帰ってないわよーん!」 その返事に、ラビが口を尖らせた。 「ユウがいなきゃ、ハンスおじさん紹介してもらえないさ!」 有名なぬいぐるみ職人は神田のことをいたく気に入っていて、入手困難なぬいぐるみを既にいくつも彼に譲っている。 その恩恵を受けた一人であるラビは、彼と直接知り合いになることを望んでいた。 「今世紀を代表するかもしれない職人さ。 顔繋いどいて悪いこたないさね」 そんな思惑は笑顔の裏に隠して、ラビはリナリー達の元へ戻る。 二人は既にテーブルに着いて、アレンが嬉しそうにケーキを食べるさまをリナリーがニコニコと眺めていた。 「アレン君、おいちい?おいちいねー 「いやいや、そこまでちっさくねえだろ」 言葉も話せない幼児を相手にするようなリナリーの口調に、ラビが笑い出す。 案の定、ムッとしたアレンは紅茶にミルクも砂糖も入れないまま飲んで見せた。 「もうおっきいんだい!」 ちょっと渋かったのか、眉根を寄せて意地を張るアレンにリナリーが頬を染める。 「そうなのぉー アレン君、大人だねぇ 「そ・・・そうだよぅ!オレ、もうおっきいんだよぅ!」 無理して紅茶を飲むアレンが、はっきりと顔を歪めた。 「どした?そんなに渋かったさ?」 「ちが・・・なんかこれ、にがい・・・」 それでもがんばって飲み干したアレンが、大きくため息をつく。 「ぜ・・・ぜんぶのんだぞ!」 マグカップの底をテーブルに叩きつけた途端、アレンは目を回して突っ伏した。 「えぇっ?!そんなに苦かったの?!」 驚いて立ち上がったリナリーが背中をさすってやると、その手の下で段々とアレンの身体が大きくなっていく。 「あ・・・あれ・・・?」 戸惑うリナリーの目の前で変化は進み、あっという間にアレンは元の姿に戻ってしまった。 「・・・はっ! どうしたの、僕!!」 身を起こし、辺りを見回すアレンから、リナリーが慌てて目を逸らす。 「・・・僕、食堂で寝ちゃった?」 なぜそっぽを向かれるのだろうと不思議に思いながら、アレンは対面にいるラビに問うた。 「詳しいことは、リンクが帰ってきたら聞けばいいさ。 それよりも」 と、ラビは慌てて厨房から出てきたジェリーを指す。 「アレンちゃん! これ着てこれ!!」 この真夏にロングコートを着せ掛けるジェリーを訝しげに見上げ、ふと自分へと目を下ろしたアレンが悲鳴をあげた。 「なんで裸なの僕!!!!」 「さっきまで子供だったかんね。 着てた服が破れちまったんさ」 「なんでそんな事態になってたんだよ!」 慌ててロングコートを着込み、全てのボタンを留めたアレンが顔を真っ赤にして絶叫する。 「だからリンクに聞けって。 あいつが原因だから」 「原因・・・。 じゃあ、アレン君が元に戻っちゃった原因は?」 食堂内を見回したリナリーは、彼らを見つめてにんまりと笑うロブをきりっと睨む。 「ロブゥ!!!!」 リナリーが詰め寄ると、彼は途端に逃げ腰になって、両手を振った。 「だ・・・だって私には室長への報告義務がね・・・! なのにそれをやめろというからには、リナリーの光源氏計画自体を潰さなきゃ私の立場がね・・・!」 「そんなの無視すればいいじゃない!」 「そういうわけには行かないんだよ!」 リナリーの怒号に負けじと、ロブも大声をあげる。 「この年で平研究員ってのも辛いんだよ?!」 「知らないよ、そんなの!!」 「私だってちょっとは出世したいなぁって思ってるんだ・・・! それなら室長に逆らうわけには行かないだろう?!」 懸命に言い募るロブに反論が出来なくなったリナリーは、頬を膨らませてそっぽを向いた。 「せっかくアレン君を好みの男の子に育てようと思ったのにィ!!」 「何をしようとしてたんですか?!」 驚いて大声をあげたアレンの口調に、ラビがにんまりと笑う。 「アレン、ちっさい頃のロンドン訛りはすっかり治ったんさね。 きれいなクイーンズイングリッシュさ」 「は? 僕、ロンドン訛りだったことなんかありませんけど?」 ごく当然のように言われて、瞬いたラビはややして、納得したように頷いた。 「そうさね。 今のお前からしちゃ、そうなんだろうさ」 「?」 ラビの笑みの意味がわからず、アレンは肩をすくめる。 そこへ、物凄い剣幕でブックマンが戻って来た。 「ラビイイイイイイイイイイイイイ!!!!貴様の仕業かあああああああああああ!!!!」 「へっ?!なにがさ?!」 驚く彼の目の前に、ブックマンが割れて空になった瓶を差し出す。 「私の育毛剤が! 私の育毛剤がああああああああああああ!!!!」 引き出しの中で割れていたと、号泣するブックマンにラビは苦笑した。 「それ、多分アレンの仕業さ。 俺が寝てる間にミランダから逃げ回ってたみたいだから」 「へ?!僕?!」 濡れ衣じゃないのかと疑うアレンに、ブックマンが詰め寄る。 「なんてことをしおったかこの小童が!!!!」 「だから僕、知りませんってば!」 「とぼけるでないわ!!」 「ほんとですよ! 全く記憶にございませんもん!!」 「おのれええええええええええええええ!!!!」 いきり立つブックマンの肩を、リナリーが笑って叩いた。 「それ、兄さんからのプレゼントでしょ? だったらまた作ってもらえばいいじゃない」 「そ・・・それはそうだの・・・」 彼女の言葉にブックマンが正気を取り戻す。 「では早速室長へ・・・」 「あれ、ブックマン、室長に聞きませんでした? それ、偶然出来たものだから、もう一度作るのは難しいって言ってましたよ?」 「な・・・なにいいいいいいいいいいいいいいい?!」 ロブの重大発言に、ブックマンが絶叫した。 「で・・・では、私の全知全能を尽くして室長のレシピを再現して・・・!」 諦めない老人に、ロブは何度も頷く。 「そうですね、急いだ方がいいです。 だってその薬、定着率が悪い上に副作用が・・・」 と、彼が指したブックマンの髪が、ハラハラと抜け落ちていった。 「元々あった髪まできれいさっぱりと抜けちゃいますからね」 「ぎゃああああああああああああ!!!!」 城中に響き渡る絶叫を上げて、一瞬のうちに禿頭になってしまったブックマンが白目を剥く。 「ジ・・・ジジィイイイイイイイイイイイイイイイ!!!!」 今までにないショックで師が永眠するのではないかと、ラビが慌てた。 「ちょっと空気読んでさ、ロブ! ジジィの繊細な心臓が止まっちまうさ!!」 「わ・・・私は本当のことを・・・。 とりあえず、救護班を呼ぼうね!」 「髪が・・・私の髪が・・・・・・!」 「ジジィ!しっかりするさ、ジジィ!!傷は浅いさ! ・・・あ、いや、全滅してるっぽいけど・・・きっと大丈夫さ!」 うなされながら病棟へ運ばれて行くブックマンに付き添って行くラビを、アレンは呆れ顔で見送る。 「いつも騒がしいですねぇ・・・」 「騒がしくなきゃあの二人じゃないよ。 それより・・・」 まだアレンの方を見ずに、リナリーが食堂の入り口を指した。 「・・・着替えてきたらどうかな」 「・・・ですね」 リンクに会ったらまずは一発殴ろうと誓って、アレンも頷く。 「ジェリーさん、スリッパも貸してください。 靴が小さくて痛いんです・・・」 「そうねん、ちょっと待っててぇん!」 厨房に戻って行ったジェリーを待つ間、アレンはこっちを向いてくれないリナリーの背に話しかけた。 「リナリー、ラビのプレゼント、もう用意しましたか? 僕、任務が終わったらロンドンにでも買いに行こうと思ってたんですけど、科学班に報告書提出に行った辺りから記憶がないんですよね」 「そ・・・そうなんだ。 でも、もういいんじゃないかな!」 「もういいって?」 なにが?と、不思議そうなアレンの声に、振り向きそうになるのを慌てて堪える。 「リンク監査官がね、ちっさくなったアレン君をラビにプレゼントしたんだって。 ラビだけでなく、ブックマンも一緒にいたんならきっと、色んな情報をもらったんだと思うよ? ラビにはそれが、何よりのプレゼントだよ」 「・・・あ! だからラビ、さっきロンドン訛りがどうのって・・・!」 「可愛かったよ、『そうだよぅおっきいんだよぅ』って それにジェリーより! ジェリーより私の方がいいって、しがみついてきたよ!」 はしゃいで振り返ったリナリーは、スリッパを持って来たジェリーとコートを着ただけのアレンを見てしまい、慌てて背を向けた。 「アラ、なぁにぃ? アタシに勝ったとでもぉ?」 「・・・ちぇっ」 自信満々の声を背中に受けて、リナリーは悔しげに床を蹴る。 「せっかく、光源氏ごっこするはずだったのにぃ・・・!」 「そう言うならまずはアンタが理想のオンナノコになんなさいよ、お転婆さん もういいわよん、アレンちゃん行っちゃったからん クスクスと笑われて振り向いたリナリーは、ジェリーへ向けて、思いっきり舌を出した。 「コムイ! 育毛剤、もう一回作ってさ!!」 執務室に飛び込んだラビを、ブリジットがきつく睨んだ。 「Jr.! 室長は今、お仕事中ですよ!」 「そんなことわかってるさね! だけど、育毛剤なくした上に大事な髪までなくしちまったウチのジジィが、今にもショック死しそうなんさ! ミス・フェイだって、貴重な戦力にこんなことで死なれちゃ困るだろ?!」 必死の交渉に、ブリジットはため息をついて頷く。 「なぁ、コムイ!!」 デスクに詰め寄ると、その向こうでコムイが困惑げに眉根を寄せた。 「でも原材料がさぁ・・・」 「原材料って何さ?!」 身を乗り出したラビの目の前で、コムイは自分の毛先を弄る。 「再生力が人外の、神田君の毛根」 「ちぎってくるさ!」 任地どこ?!と、詰め寄られたブリジットが、思わず『ドイツのフュッセン』と答えた。 「行ってくるさ!!」 コムイの執務室を駆け出たラビは、方舟の間に駆け込み、スタッフの制止を振り切って方舟に飛び込む。 「ドイツ行きのドア・・・は、ベルリンに繋がってんだった! フュッセン行きは確か、直通があったはずさ!」 方舟を出た後に鉄道を使うのももどかしいと、ラビは正確な記憶を頼りに滅多に使われないドアへ向かった。 と、運のいいことに、任務を終えたらしい神田の一行が、こちらへ向かってくる。 「さすが誕生月!! ついてるさ!!」 滅多に輝いてくれない幸運の星に感謝しつつ、ラビは神田へ呼びかけた。 「ラビ、どうした?」 「ユウ! 俺、明日誕生日だからさ! 俺の欲しいもん、快く譲ってくれ!!」 「は?!」 なにを、と戸惑う彼が束ねた髪を掴み、数本引きちぎる。 「なにすんだ、てめぇ!!」 「ジジィが死にそうなんさー!」 一瞬で神田の足下に踏まれたラビが泣き声をあげた。 「ジジィの育毛剤、アレンが割っちまってー! その上、元々あった髪まで抜けちまったジジィが今にもショック死しそうなんさ! もう一回作るのに、必要なのはユウの毛根だってコムイが・・・! だからさー!!」 「またか!! 何本引き抜きゃ気が済むんだ、テメェら師弟はよ!!」 以前はその育毛剤の研究とかで、ブックマン自身に髪を引き抜かれたと、神田が舌打ちする。 「欲しけりゃだまし討ちじゃなく、普通に言えよ!」 自身の長い髪に指をかけた神田が、更に数本抜き取って、ラビに渡した。 「ユウちゃん・・・!」 感涙するラビに、神田はまた舌打ちする。 「その代わり、今年の誕生日プレゼントはなしだからな! ・・・忙しくて、選ぶ暇がなかったんだ」 言い訳のように付け加えた神田に、ラビは何度も頷いた。 「全然気にしないさ! あ、そーだ! 前にもらったぬいぐるみのメンテしたいから、ハンスおじさん紹介してくれ! 俺へのプレゼントはそれでいいからさ!」 「あぁ、そのくらいなら・・・」 「頼んださー!!」 大声をあげて本部へと駆け去っていくラビを、神田は呆れて見送る。 「あいつ・・・暗証番号配布されてんのか?」 あの様子では、方舟に入る許可すらもらっていないだろうという予想は当たり、帰還したラビは無理に方舟の間を抜けようとしたため、常駐の警備班に追われる羽目になった。 「ついさっき入ってったって、あんたらも見てただろうさ!!」 「中で入れ替わってないと証明するのが先だ!!」 至極当然の反論を受けて、ラビは言い返せないまま科学班へ、そしてコムイの執務室へと飛び込む。 「はやっ!」 さすがに驚くコムイへ、ラビは神田の髪を差し出した。 「これを・・・これをジジィに・・・!」 「ラビ・・・!」 追いついた警備班に拘束され、身動きを封じられながらも師のために走りきったラビの姿に、コムイだけでなくブリジットの氷の心も熱くなる。 が、ここでほだされてはいけないのが二人の立場だ。 「キミの犠牲を無駄にはしないよ、ラビ・・・!」 「見事でしたわ、Jr.・・・! 後は潔く、罰を受けるのです・・・!」 ブリジットが顔を背けたのは、目に光るものを見られないようにと思ってだろうか。 芝居じみた二人の反応に居心地の悪さを感じながら、警備班の面々は拘束したラビを連行し、規則にのっとった調査の後、長い説教とげんこつを贈って解放してやった。 「・・・むっちゃ痛かったさ!」 病棟でうなされる師に、育毛剤が再開発されることを報告してから食堂に戻ったラビは、大きなたんこぶの出来た頭をさすりながらため息をついた。 「警備班の役目ってことはわかるけどさ、こんなにぶつことないさね!」 じっとりと睨んだ先には、ラビに強烈なげんこつをプレゼントしてくれた強面が、うまそうに遅い夕食を食べている。 べーっと舌を出してやると、腹の立つことに親指を立ててウィンクされた。 「けっ! 今度、メシに唐辛子混ぜてやるさ!」 忌々しげに言うラビに、対面のリナリーが苦笑する。 「再開発されるのはよかったけど・・・あれ、ロブが言うには偶然出来たものなんでしょ? また同じものが作れるの?」 気遣わしげな彼女へ、ラビはあっさりと頷いた。 「それはジジィがいるから大丈夫さ。 ジジィの奴、ユウの毛根ゲットして再開発できるようになったって言った途端、起き上がってさ。 前の育毛剤の開発中に記録した全データを提供するんだって、コムイんとこに走ってった。 本当は、ブックマンの情報って高いんけど、そんなことすっかり忘れてるさね、あれは」 「自分のためだもんなぁ」 不機嫌な顔で料理を頬張っていたアレンが、じっとりとラビを睨む。 「ところでラビは自分のために、ちっさい僕からどんなおいしい情報仕入れたの?」 「・・・ブックマンとしてゲットした情報は、ブックマン以外にはいわねーよ」 にんまりと笑ったラビの、予想通りの答えに、アレンは口を尖らせた。 「悪用しないでよね」 「しねーから安心シテ クスクスと笑うラビの目の前で、食堂の大時計が0時を指す。 「いいプレゼントをサンキュ 頭を撫でる手をうるさげに払ったアレンは、思い出し笑いをするラビに思いっきり舌を出した。 Fin. |