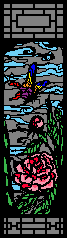「―――― よろしいでしょう」 華やかな衣装に身を包んだ女は、優雅な蘇州なまりでそう言うと、艶やかな紅い唇に笑みを浮かべた。 室内に篭もる、きつい香の薫りと同じく、そのなまりさえ、作り物だと知ってはいたが、コムイは顔色も変えずただ、礼を述べた。 「いいえ・・・これは、わたくしから貴方への、贈り物でございます。 どうぞ、これからもご贔屓に」 傾ぐように、優雅に会釈した女に、コムイは頷いて立ち上がる。 「こちらこそよろしく、店主殿。 私が教団の室長となったあかつきには、便宜を図らせていただきます」 コムイの言葉に、女は笑みを深めた。 「さすがは李家の若様。商売が、お上手でいらっしゃる」 「私は、商人としては失格ですよ」 女の言葉に、コムイは愛想の良い笑みを返す。 「たった一人の娘のために・・・身代を捨てるのは、惣領のやることじゃない」 自嘲と共にそう言い残し、立ち去ったコムイの背に、女は囁いた。 「欲しいものを手に入れるためなら、あらゆる策を使う・・・・・・貴方は、立派な商人ですとも」 そう、あらゆる策を・・・・・・。 女は、コムイがここに来るまでのことを思い、その朱唇に艶やかな笑みを浮かべた。 コムイが、黒の教団のサポーターだった、妓楼の女主人と会うことになる、数ヶ月前の事・・・・・・。 黄梅(オウバイ)の咲き誇る庭の四阿(あずまや)に寝転んでいたコムイは、長椅子から垂れた長い髪を引かれて、日よけ代わりに顔を覆っていた本を落とした。 「哥哥(グァーグァ)!」 髪を引かれるまま、寝ぼけ眼を横に向けると、ふっくらとした幼い顔が、にっこりと笑う。 「あそんでー!」 子供特有の、高い声が耳元で弾け、コムイは、うるさげに目をつぶった。 と、まるでそれが、とても残酷な行為だと糾弾するように、小さな手はぐいぐいと彼の髪を引き、声は涙を含んで更に甲高くなる。 「哥哥!!哥哥!!あそんでー!!あそぶのー!!!!」 仕方なしに目を開けたコムイは、のろのろと起き上がり、小さな乱暴者を抱き上げた。 「もー・・・おにーちゃんは、眠たいのにサー・・・・・・」 ブツブツとぼやきながらも、彼は抱き上げた妹を、上下左右に揺らす。 と、今まで泣き声を上げていた幼女は、きゃっきゃっと笑い声を上げた。 「リナリィー・・・せっかくのいいお天気だよ? お兄ちゃんとここで、お昼寝しよー?」 ネムイヨー・・・と、今にも閉じそうになる目を向けるが、リナリーは強情に首を振る。 「ねむくないもん」 断言した通り、彼女の大きな目は、ぱっちりと開いて、コムイを見下ろしていた。 「・・・じゃあ、お兄ちゃんはお昼寝するから、媽媽(マーマ)の所に・・・」 「マーマはおでかけしたもん。ティエティエもいないよ」 「そっかー・・・父さんもいないかぁー・・・」 言葉もたどたどしい幼女でありながら、先回りしてコムイの言葉を塞ぐ賢さに、彼は深々と吐息する。 「じゃあ・・・仕方ないねぇ・・・・・・」 「うん!しかたないの!哥哥は、リナリーとあそぶのよ!」 くりくりとした大きな目を輝かせ、小さな手でしがみついた妹の頭を、コムイは大きな手で撫でてやった。 二人は、年の離れた兄妹だ。 年が近ければ、対等にケンカもしただろうが、13も年が離れていれば、本気のケンカはしないものだ。 いつも、コムイがリナリーのわがままに負けて終わり。 それが、この二人のスタイルだった。 コムイは、リナリーを抱き上げたまま、のろのろと立ち上がると、四阿を出る。 「アイテテテ・・・日差しが目に痛いよー・・・・・・」 寝ぼけまなこを射る日差しに目を細めると、リナリーがきょとん、と、目を見開いた。 「哥哥、おめめいたいの?」 じっと、彼の目を覗き込む顔が、幼いながらも真剣だ。 「おひさまがいたいの?」 そう言って、リナリーはコムイの眼前に、小さな手をかざした。 思いもしなかった、彼女の的確な処置に、コムイは思わず吹き出す。 「哥哥?」 笑い出した兄に、不思議そうに首を傾げたリナリーを抱きしめ、コムイは春の日差しの中、笑いながら母屋に歩いていった。 「だーれかー?」 母屋に入るや、コムイは声を掛けたが、返答はない。 「父さんはともかく、母さんまでいないって・・・なんで?」 抱いていたリナリーを、長椅子の上に転がすと、彼女は『わからない』と言うように、ふるふると首を振った。 「ふぅん・・・珍しいねぇ」 李家は、大商人とは言えないが、そこそこは裕福な家庭だ。 だからこそコムイも、のんびり学問などをしていられるし、そんな家の女主人は、滅多に外出などしない。 コムイは母屋を一巡りし、家人を探したが、珍しいことに今日は、下働きの一人も見つからなかった。 「まぁ、いいや。 リナリー、なにをして遊ぶんだい?」 ちょこちょこと、コムイの後ろをついて回るリナリーを振り返ると、彼女は、母の部屋から持ってきたらしい、きれいな刺繍の靴を履こうとしている。 「哥哥!きれい!」 刺繍の靴が、リナリーの幼く小さな足に、ぴったりと合う様を見て、コムイは母屋から一番離れた建物を見遣った。 と、幾人かの家人が、慌しく行きかう様が遠目に見える。 「マァ〜マァァァァ〜〜〜〜!!」 母と家人らが、一斉に消えた理由を察したコムイは、地を這うような声で呟くと、きれいな靴を履いてご機嫌のリナリーを抱き上げた。 「リナリー・・・お兄ちゃんと、お出かけしようね・・・!」 その数日後、友人宅に身を寄せていた兄妹は、街中を大捜索していた家人に見つかり、無理矢理家に連れ戻された。 「コムイ!!お前、なんてことしてくれたの!!」 母の部屋に入った途端、耳に刺さるような甲高い声で怒鳴られ、コムイに抱かれていたリナリーが、驚いて泣き出した。 「あの日は、お義母さまや他家に嫁がれた方達にまで来ていただいて、準備万端整えていたのに・・・! 全てが無駄になってしまったわ!」 普段、優しく物静かな女性だけに、柳眉を逆立てて怒声を上げる様には、心臓をわしづかみされるような恐ろしさがある。 が、コムイは眉一つ動かさず、傍らの友人にリナリーを託すと、悪鬼のように怒り狂う母と対峙した。 「媽媽(マーマ)、ボクは謝るつもりはありませんよ」 「お黙りなさい! 本当だったら、リナリーには去年の秋に纏足(てんそく)をしてあげるはずだったのに、お前はあの時も邪魔をして・・・!」 怒りのあまり、母の朱唇がぶるぶると震える。 「お前、リナリーが不幸になってもいいと言うの?!それでも兄なの?!」 激怒して立ち上がった母は、コムイに詰め寄ろうとしてよろけた。 「媽媽・・・」 片手で母を支え、コムイは、憐れみを含んだ目で彼女を見下ろす。 「纏足なんて、残酷な風習です。 ボクは、こんな小さな子の足を潰してしまうなんて、可哀想な事はしたくない・・・・・・」 幼いリナリーの足に、ぴったりと合った靴・・・それは、二人を産んだ母の足にもぴったりと合う。 纏足とは、幼女の足を潰し、成長を止めてしまう風習のことだ。 こうすると、女性は走ることはおろか、歩くことすらままならず、『家』に縛られる。 「こんな悪習、いずれなくなります。 ボクはリナリーに、自分の足で歩き、走って欲しい・・・それが、この子を不幸にすることですか?」 「女が走る必要など、ありません!」 自身を支える息子の手を乱暴に振り払うと、母は、小さな足でよろけながらも息子に詰め寄った。 「お前は外国の学問にかぶれて、清国人の誇りを失ったのですか! 他国ではいざ知らず、お前は清国人で、リナリーは清国の男性に嫁ぐのです! こんなに可愛らしいのに・・・大足の小姐(シャオチェ)などと蔑まれて、お嫁の貰い手がなかったら、この子は一生不幸ですよ!」 「だったら、この子を外国に連れて行きますよ!」 「そんなことは、私が許しません!!」 母子の会話は、見事にすれ違い、一切の妥協がないまま、激しさを増していく。 と、 「ま・・・まぁまぁ、李太太(リータイタイ)、落ち着いてくださいな」 泣くリナリーをあやしていた男が、逞しい体躯に似合わない柔和な口調で、二人の間に割って入った。 「コムイも、最初っからそんなケンカ腰じゃァ・・・太太(奥様)も立場がないわぁ」 ねぇ?と、睨みあう二人の顔色を伺う彼に、しかし、彼女は鋭い眼光をそのまま向ける。 「ジェリーさん、あなたもうどうせ、纏足に反対でいらっしゃるんでしょう?」 「えぇ・・・まぁ・・・」 こんな小さな子の足を潰すのはねぇ・・・と、ジェリーは自分の腕の中でぐずるリナリーに、苦笑を浮かべた。 「では、あなたの額についているヴィンディや、お守りのメヘンディが、他国の方に『愚かで無意味な風習だ』と言われたら、どうお思い?!」 「んまっ!これはちゃんと意味があるんですっ!愚かでも無意味でもありませんわっ!」 彼女の言葉に真っ向から反論したジェリーは、太太の勝ち誇った笑みに、『しまった・・・』と、気まずげに口をつぐむ。 そんな彼の様子を、母は『ご覧なさい』と言わんばかりに示し、再びコムイと対峙した。 「他国の者がなんと言おうと、これは、愚かでも無意味でもありません。 先日は、せっかくの吉日を台無しにしましたが、次は逃がしませんよ。 さ、リナリー。こちらにおいでなさい」 ジェリーから、リナリーを取り上げると、彼女は、二人に出て行くよう、手を払う。 「儀式が終わるまで、お前はこの子に近づかないで頂戴」 「コムイ、ごめんねぇ〜・・・」 失言しちゃったわ、と、しょげるジェリーに、コムイは深く吐息して、首を振った。 「いや・・・ジェリーがあそこで止めてくれなかったら、もっと大変だったよ」 普段は物静かで、良妻賢母の誉れ高い母だが・・・いや、だからこそ、子供達を『まともな清国人』にすることに関しては、一歩も引かない。 「リナリーが・・・5歳になるまで逃げ切れば、母さんも諦めると思ったんだけどねぇ・・・」 纏足は本来、骨が柔らかく折りやすい、3、4歳頃に行うものだ。 「去年の秋を何とか逃げ切ったから、もう大丈夫だと思ったのに・・・・・・」 「今ならまだ、ギリギリ冬だものねぇ・・・・・・」 凄い執念だと、呆れるジェリーに、コムイも同意する。 「可哀想にねぇ・・・あの子、ものすごく泣くでしょうねぇ・・・・・・」 後ろ髪を引かれる思いで、ジェリーは背後を振り返った。 「諦めるしかないのかなぁ・・・・・・」 母の怒りの形相を思い出し、呟いたコムイだったが、ふるりと頭を振る。 「いや、ボクは、間違ったことは言ってない。 纏足しないとお嫁に行けないというなら、行かなくていい」 「ちょっと・・・アンタ、それはいくらなんでも・・・・・・」 横暴でしょ、と、言いかけた言葉は、コムイの真摯な表情に、ジェリーの口から出る前に消えた。 彼の友人はその母に似て、とても強情だと言うことは、よく知っている。 「ハイハイ・・・今度もまた、邪魔するのね?」 「手伝ってくれるかい?」 期待に満ちた声に、ジェリーは、諦観のこもった声音で応じた。 「太太には悪いけど・・・アタシ、外国人だしぃー。 やっぱり、可哀想だと思っちゃうのよねぇ・・・」 そう言って苦笑すると、コムイは、嬉しそうに笑う。 彼としても、こんなことを頼めるのは、ジェリーしかいない―――― 同国人の友人達はきっと、母の肩を持つに違いないのだ。 「ありがとう!」 そう言って、コムイはジェリーに、ニコリと笑いかけた。 そして、その日はやって来た。 朝早く起こされたかと思うと、きれいな服を着せられ、母や祖母、親戚の女性達に囲まれて、リナリーは大きな目をきょとんと見開く。 と、 「ほら、リナリー。きれいなお靴でしょう?」 掌に乗るほどの、小さな刺繍の靴を、母が差し出した。 ぱぁぁっと頬を上気させ、かわいらしい靴に見入る娘に、嬉しげに微笑み、彼女はそれを、リナリーから良く見える場所に置く。 「このお靴を、履かせてあげましょうね。嬉しいでしょう?」 「うん!」 いつも、母の部屋で見ては、憧れていた靴を、自分も履けるのだと思うと、リナリーは嬉しさのあまり、小さな足をパタパタと揺らした。 そんな少女の姿を、一族の女達は微笑ましく、あるいは哀しげに見守る。 「マーマ、哥哥は?」 きれいな靴を履いた自分を見せたいと、きょろきょろと周りを見渡した。 が、リナリーの目の届く場所には、兄どころか、男性の姿もない。 「お靴を履いたら会えますよ」 そう言って、リナリーに笑いかけた母の傍らで、突然、悲鳴が上がった。 「ニワトリがいないわ!どうして・・・ちゃんとここに、用意していたのよ?!」 その声に、皆の視線がニワトリを閉じ込めていた籠に集まる。 「どうせまた、コムイの仕業だよ!」 最年長の老婆の、厳しい声音に、母は恐縮してこうべを垂れた。 「も・・・申し訳ありません、お義母さま・・・・・・!」 「仕方ない・・・誰か、庭へ行って、獲っておいで!」 老婆の声に、若い女が部屋を飛び出して行き、彼女を見送った老婆は、怒りに紅潮した顔を嫁に向ける。 「息子を甘やかしすぎだよ、お前は! すっかり外国にかぶれてしまって、何度邪魔すれば気が済むんだろうね?! 今、出て行った娘なんてね、ついこないだ、リナリーと同じ年頃の娘を亡くしたばかりなのさ! 娘を思い出しちゃあ辛いだろうに、お前たちのために手伝いに来てくれたんだよ?! それを、なんて罰あたりな・・・・・・?!」 老婆の叱責に、ひたすらこうべを垂れていた彼女だったが、延々と続くだろうと思っていたそれが、突如止んだことをいぶかしんで顔を上げると、ぽかんと口を開けた義母の顔が、そこにあった。 「お義母さま・・・?」 不思議に思い、その視線の先を追うと・・・つい先ほどまでいた場所から、リナリーが消えている。 「コムイ――――!!!!」 女達の絶叫が、室内に満ちた。 「おっ・・・追いかけてこない見たいよっ!」 「そりゃそうだよ!走れないんだもん!」 共に全力疾走をしていたジェリーの言葉に、コムイは笑って歩調を緩める。 「やったわねっ!!」 コムイと歩調をあわせたジェリーは、そう言って、嬉しげに拳を握った。 「もう追いつけないよ!」 後ろを振り返り、だいぶ距離を稼いだことを確認したコムイも、満面に笑みを浮かべる。 その腕の中では、リナリーが、きょとん、と、兄を見上げていた。 「哥哥?リナリーのお靴は?」 はだしの足を、ぶらぶらさせる妹を、コムイはぎゅうと抱きしめる。 「大丈夫。 もう、痛いことはないからね」 「いたい?」 なにが・・・と、言いかけたリナリーは、前も見ずに歩いていたコムイが、ちょうど門をくぐってきた人物と真正面からぶつかったために、押しつぶされて、短い悲鳴を上げた。 「リッ・・・!!リナリィィィ!!」 兄の胸に鼻をぶつけたリナリーが、大きな泣き声を上げる。 「・・・あらまぁ」 リナリーの泣き声に負けず、絶叫したコムイの傍らで、彼とぶつかった人物を見たジェリーは、その異様な風体に思わず呆れ声を上げた。 「これはまた、派手なガイジンねぇ」 「・・・・・・お前に言われる筋合いはないぞ」 黒衣の肩に流れる、血の様に紅い髪と、端整な顔の半面を覆う白い仮面。 憮然と呟いた男は、長身のコムイが驚くほど大きく、十分派手なジェリーが呆れるほど色彩豊かだった。 と、 「どうされました、神父? ・・・こんな所でどうした、コムイ?」 門前に立ち塞がる大男の陰から、ひょっこりと出てきた顔に、コムイは気まずげに表情を歪める。 「父さん・・・」 「ティエティエー 「ただいま、リナリー。 ・・・・・・コムイ、またやったのか」 息子と娘が、揃ってここにいる意味を悟り、彼、李家の主人は、厳しい目を息子に向けた。 「だって・・・」 「ティエティエ!マーマがきれいなおくつ、くれるのよ!」 母の差し出した靴を履くことで、どういう目に遭うかを知らぬリナリーが、無邪気に笑う。 ぱたぱたと揺れる裸足を見て、神父と呼ばれた男は、口の端を歪めた。 「靴が欲しいのか? だったら・・・・・・これを履いてみろ」 そう言って、神父が取り出した黒い靴を、リナリーは興味深げに見つめる。 「マーマのとちがう・・・でも、きれい・・・・・・」 神父の手にした靴は、日の光を浴びて、きらきらと光っていた。 「西洋の靴だ。『ブーツ』と言う」 言うや、神父はコムイが止める間もなく近づき、リナリーの小さな足に、黒いブーツを履かせる。 「哥哥!おろして!」 歩いてみたい、と、腕の中で暴れるリナリーを、コムイは渋々下ろした。 「きゃー 嬉しそうに駆け回るリナリーを、和んだ目で見下ろした父は、しかし、コムイに対しては厳しい目で睨みつける。 「全く・・・何度も母さんの邪魔をして・・・! リナリーが嫁に行けなくなったらどうするんだ、お前は!」 「ほぉ・・・この国では、足が小さくないと嫁にいけない、という話は本当だったのか」 神父の、皮肉に満ちた声音に、三人は一斉に彼を見た。 「神父、あなたなら、こんなに小さい子供の足を潰し、縛って、自由に歩くこともできなくするなんて、残酷なことだと思いませんか?」 「黙れ、コムイ!纏足は、わが国に古くから伝わる習俗だ! お前という奴は、すっかり外国にかぶれて・・・」 「ま・・・まぁまぁ、爺爺(だんなさん)・・・! そりゃ、アタシは外国人ですから、お家のことに口出しすることじゃありませんけどぉ・・・」 「まぁ、俺も外国人だから、好き勝手言うが・・・・・・」 そう言って、彼らの周りを仔犬のように駆け回る少女の姿に、神父は目を細める。 「これほど嬉しそうに走る姿を見ていると、この子供から足を奪うことは、喜びを奪うことに等しいと思うんだがな?」 途端、コムイとジェリーは喜色を浮かべ、主人は不快げに眉をひそめた。 「リナリー、おいで」 憮然とした口調で呼ぶと、主人は嬉しげに駆け寄ってきた娘と手を繋ぎ、息子と客達に背を向ける。 「神父、少々失礼します。 妻たちが、この子を探しているでしょうから」 言うや、彼は憤然とした足取りで、リナリーの手を引いていった。 「止めないのか?」 唇を引き結んで、父の背を睨みつけるコムイに、神父は殊更、からかうような口調で言う。 「・・・・・・家長の命令には、逆らえない」 悔しげに呟いたコムイに、神父は口の端を曲げた。 「外国かぶれとか言われていたが、お前、十分東洋人だな」 喉を鳴らすように、皮肉な笑声を上げる神父を、コムイが睨みつけた時―――― 地を揺るがす爆音が響いた。 「なにっ・・・?!」 驚愕に立ち竦むコムイとジェリーの傍らを、神父が風のように駆け抜けていく。 一瞬遅れて、 「リナリー!!」 コムイは絶叫し、慌てて神父の後を追った。 「あ!アタシも行くわ!!」 更に一瞬遅れて、ジェリーが続く。 が、彼らは前方を行く神父に、あっという間に引き離され、目的地に着くまで、彼の背を見ることすらかなわなかった。 「なっ・・・なんなの、あのヒト!」 息を切らしつつ、ようやく追いついたジェリーは、部屋の入口に立ち竦むコムイを、訝しげに見る。 「どうしたの・・・っ?!」 コムイの肩越しに、部屋の中を見たジェリーは、絶句した。 リナリーに纏足を施すため、きれいに飾り付けてあった部屋は、銃痕らしき無残な破壊の痕があり、壁や床は、丹で塗られたかのように紅く彩られている。 壁にもたれ、あるいは床に倒れて、光の消えた目を見開いているのは、李家の女達・・・そして、この家の主人までもが、リナリーを庇うように抱きしめたまま、事切れていた。 「リ・・・ナ・・・・・・!」 全身に血を浴びて、呆然と目を見開いていたリナリーが、コムイの引きつった声に、ぎこちなく振り向く。 その視界に、兄の姿が写った途端、火がついたように泣き出したリナリーに、コムイはもつれる足をどうにか動かして、まだ暖かい父の腕から、妹を受け取った。 「間に合わなかった・・・・・・・・・すまない」 表情を隠すように、仮面で覆われた半面のみを向け、低く呟いた神父に、コムイは、刃のように鋭い目を向ける。 「あれは・・・なんですか? あなたが、破壊した・・・・・・」 コムイの問いに、神父は、仮面を向けたまま呟いた。 「アクマ・・・・・・。 あれが、お前の一族を殺した」 「なぜ・・・?!」 燃えるような目で問うコムイに、神父は、ゆっくりと振り向く。 「それは、お前が自分で突き止めるんだな」 仮面に覆われていない半面までも、凍ったように微動だにせず、神父は歩み寄ると、コムイの腕からリナリーを取り上げた。 「なにをする?!」 リナリーを取り戻そうと、伸ばした手は、鋭く弾かれる。 「つっ・・・!」 骨が折れたかと思うほどの衝撃に、コムイが手を引いた一瞬、神父はコムイだけでなく、戸口に立っていたジェリーの手までも届かぬ場所まで退いていた。 「リナリー!!」 「哥・・・・・・っ!!」 コムイの絶叫に応じて、リナリーは引きつった泣き声を上げたが、怯えきった身体は硬直して、神父の腕の中で細かに震えている。 「この娘は適合者だ。 ダーク・ブーツが、この娘を守った」 「適合・・・?!」 「ダーク・ブーツって・・・?」 眉をひそめる二人には答えず、神父は、リナリーを抱いたまま、踵を返した。 「待て!!」 足に一族の血を絡ませながら、コムイは神父を追いかけるが、人並外れた足の速さに、距離は開いていく。 「妹を・・・リナリーを返せ!!」 コムイの絶叫に、神父は半身、振り向いた。 「返して欲しければ、英国の黒の教団へ来ることだ」 「英国ですって?!」 「黒の・・・教団・・・?!」 なおも追い縋る二人を、神父はあざ笑うかのように引き離す。 「そうだ。 追いかけて来い、コムイ・リー。 父が亡くなった今、お前が家長だ」 誰も止めるものはいない。 リナリーを追って英国に行くも、清国に残って、父から継いだ家を守るも、コムイ次第・・・。 だが、神父は確信とともにに嘯いた。 「俺は黒の教団の元帥、クロス・マリアン。 妹を返して欲しければ、俺を追ってくるがいい」 だが・・・と、彼は、皮肉な笑みを浮かべる。 「未だ、一族の血を足枷にしたお前には、無理なことか?」 「な・・・っ!」 怒りに頬を紅潮させ、追いすがるように神父へ伸ばしたコムイの手は、しかし、寸前でかわされた。 「お前の選ぶ道を、見ているぞ」 あざ笑うように言い残すと、神父は、コムイ達の前から消え去った。 それから、数ヶ月が無為に経った。 李家が、コムイを除いて全滅した事件において、両親と争っていた彼は犯人として目をつけられ、厳しい詮議の対象となったのだ。 あらゆる手を使って、役人の手から解放された時には、当然のようにリナリーの消息は絶えていた。 「コムイ!やっとわかったわよぉ!」 コムイの協力者として、共に詮議を受けていたジェリーが、息せき切って駆けて来る。 「黒の教団って言うのは、欧州じゃ割と有名な、カトリックの組織だそうよ。 世界中に支部があって、この清国にも、サポートの部署があるらしいわ!」 「よし!じゃあ、早速そこへ・・・!」 しかし、ジェリーが苦労して探し当てた中国支部では、文字通り、門前払いされた。 それはそうだろう。 いくら、クロス元帥の名が出たからといって・・・いや、だからこそ、身元不明の人間を受け入れることはありえない。 「どうすれば・・・・・・」 いらいらと、焦燥ばかりが募っていくコムイの肩を、ぽん、と、慰めるようにジェリーが叩いた。 「ねーぇ、アタシ、いいこと思いついたわ」 にんまりと、唇に笑みを乗せるジェリーを、コムイが縋るように見つめる。 「アタシがインドから来た時、この国はまだ、鎖国状態だったの。 でもアタシ、ここまで流れてくる間に、客家(ハッカ)とか青弊(チンパン)なんかの、組織の人間と仲良くなって、この国に住めるようにしてもらったのね」 客家(ハッカ)とは、元は大陸の北から流れてきた民族で、独自の習俗、言語を保持する一族だ。今や中国大陸だけでなく、世界中に散らばった彼らの結束は固い。 青弊は、端から見ればヤクザの集団と取られないこともないが・・・客家と同じく、この組織に属するものは、世界各地に散らばろうと、その土地の青弊の仲間として受け入れられる。 「黒の教団は、大きな組織なんでしょ? この二つ組織の有力者にお願いすれば、どちらかが教団に入れるよう、便宜を図ってくれるんじゃないかしら?」 「ジェリー・・・っ!」 コムイの声が、歓喜に詰まる。 「ぜひともお願いするよ!」 ジェリーの提案に賛同するや、私財をなげうって有力者との繋ぎを取ったコムイに、程なく、いずれの組織からか、『ある妓楼へ行け』と、連絡があった。 そこの女主人が、黒の教団への道を開いてくれるだろう、と。 すぐさま向かえば、妓楼の女主人は、香の薫りに満ちたあでやかな部屋で、艶やかな唇に笑みを乗せ、彼らを迎え入れた。 「いらっしゃいませ、李家の若様。 この度は、大変な事でございましたわね」 事情は伺っております、と、優雅に一礼し、二人に席を勧めた彼女に、コムイは、単刀直入に目的を語った。 話を聞き終わった主人は、仮面のように張り付いた笑みを崩すことなく、しばし、考え込むような素振りを見せる。 「・・・若様は確か、この月の十三日にお生まれになったのですわね。 西洋には、誕生日に贈り物を習慣がありましてねぇ」 独白のように呟くと、主人はやがて、その朱唇に本物の笑みを乗せた。 「―――― よろしいでしょう。 貴方の英国への渡航と、教団への入団の件、お世話させて頂きます」 「んまぁ!!ありがとうございます、太太!」 思わず歓声を上げたジェリーに、主人は優雅に微笑んだ。 「実は・・・クロス様より、仰せつかっておりました。 貴方が自力でここまで来れたなら、黒の教団へ受け入れるように、と。 次の、教団本部室長になる者だから、と・・・・・・」 そう言って、彼女は少々、意地の悪い笑みを浮かべる。 「僭越ながらわたくしも、貴方の人となりを拝見させていただきました。 教団本部室長に、おなりあそばせ、若様」 主人の言葉に、コムイは顔色も変えずただ、礼を述べた。 「いいえ・・・これは、わたくしから貴方への、贈り物でございます。 どうぞ、これからもご贔屓に」 傾ぐように、優雅に会釈した女に、コムイは頷いて立ち上がる。 「こちらこそよろしく、店主殿。 私が教団の室長となったあかつきには、便宜を図らせていただきます」 コムイの言葉に、女は笑みを深めた。 「さすがは李家の若様。商売が、お上手でいらっしゃる」 「私は、商人としては失格ですよ」 女の言葉に、コムイは愛想の良い笑みを返す。 「たった一人の娘のために・・・身代を捨てるのは、惣領のやることじゃない」 自嘲と共にそう言い残し、立ち去ったコムイの背に、女は囁いた。 「欲しいものを手に入れるためなら、あらゆる策を使う・・・・・・貴方は、立派な商人ですとも」 「媽媽(マーマ)・・・?」 コムイと入れ替わりに、部屋に入ってきた少女に、女は目を和ませる。 「今の男、ちゃんと見たかい?」 両手を広げて迎え入れた少女は、彼女の言葉に、しっかりと頷いた。 「次の、教団本部室長だよ。 あの人がお前を使うことになる・・・しっかりお助けするんだよ、アニタ」 「はい、媽媽」 彼女の腕の中で、少女はにこりと笑みを浮かべた。 Fin. |