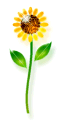「バカンス行きてー・・・・・・!」 いきなり部屋に入ってきたかと思うと、そう言ってベッドへダイブしたラビに、アレンは目を丸くした。 「えっ・・・と・・・?」 なぜよりによって自分の部屋で倒れるのか、わけのわからないまま硬直するアレンの目の前で、ラビは枕を抱き寄せ、安らかな寝息を立て始めた。 「ちょ・・・なんで僕のベッドで寝るんですかー?!」 ゆさゆさと揺すれば、ラビがほんのわずか、まぶたを開ける。 「かたすのめんどーさー・・・・・・」 「かたすのって、なに?! まさかまた、自分のベッドにガラクタぶちまけてんですか?!」 「ぐー・・・」 「寝るなー!!」 ヒステリックな声を上げ、更に激しく揺さぶるが、ラビはもう、目を開けようとはしなかった。 「・・・っもう!!」 アレンは腹立ち紛れに、ラビが抱きしめる枕を取り上げ、代わりに部屋の隅に転がしていたミイラ人形をあてがう。 「目が覚めた時にびっくりするといいよ!」 ふんっ!と、鼻を鳴らし、アレンは部屋を出た。 そのまま食堂へ駆け込み、カウンターに縋って泣き声を上げる。 「ジェリーさぁぁぁんっ!! ラビに部屋とられたぁぁぁぁぁ!!」 「アラ! アラアラ・・・しょうのない子ねぇ・・・・・・」 アレンの泣き声を聞いて厨房の奥から出てきたジェリーは、苦笑しながらカウンターに突っ伏す彼の頭を撫でてやった。 「でも、お部屋ですることがないなら、ちょっと貸してあげてね、アレンちゃん。 ラビ達のお部屋ねぇ・・・科学班が壊しちゃったから 「え」 アレンが思わず顔を引きつらせた理由を、ジェリーは見事に勘違いして深く頷く。 「アレンちゃんは昨日帰ってきたから、知らないわよね。 一昨日だったかしら? 真夜中に、いきなり爆音がしてねぇ・・・。 ラビ達の部屋を含めて、全階吹き抜けになってるのよ、今」 「えぇー・・・・・・」 だらだらと汗を流しながら、気まずげに顔をそらしたアレンに、ジェリーはにこりと微笑んだ。 「だから、ね? あの子も任務から帰ったばかりで疲れてるだろうし、ちょっと休ませてあげて?」 「は・・・はい・・・・・・」 ぎこちなく頷いたアレンは、話題転換の必要性を感じて、無理やり微笑む。 「ブ・・・ブックマンは、どうしたんですか? どっかで寝てるんですか?」 と、ジェリーは顎に人差し指を当て、可愛らしく首を傾げた。 「んー? アタシが見た時は、なんだか平気そうにしてたけどぉ・・・休まなくて大丈夫なのかしら? もういい年なのに・・・って?あら?」 ふと気づいた様子で、ジェリーは厨房内にかかったカレンダーを振り返る。 「あらま! 明日、ブックマンのおじいちゃんのお誕生日じゃない!!」 「へ? ・・・ということは、もうすぐラビの誕生日?!」 ひぃっ!と、引きつった声を上げて青ざめるアレンに、ジェリーは乾いた笑声をあげた。 「毎年大変ね、アレンちゃん・・・」 「ホントですよっ! うわっ・・・すっかり忘れてた・・・! 今から考えて間に合うかなぁ・・・・・・」 本気で頭を抱えるアレンの前で、ジェリーもまた、頬に手を当てて首を傾げる。 「そぉねぇー・・・確かおじいちゃん、数えで90なのよねぇー・・・卒寿って、どんなお祝いするんだったかしら?」 「は?ソツジュ・・・?」 聞き慣れない言葉に、アレンが首を傾げると、ジェリーは優しい笑みを浮かべた。 「たまにコムイが使っている字があるでしょ?あれ、漢字っていうんだけど、『卒』って字は『卆』とも書いてね、それが、数字の『九十』に成り立ってるってことから、90歳のお誕生日を『卒寿』って言って、特別なお祝いをするのよ」 「へぇー・・・でも、ブックマンは確か、明日で89歳なんじゃ・・・?」 「数え、って言うのは、西洋で言う0歳を1歳って数えるの。 だから、今年が卒寿で間違いないのよ」 「ほぇー・・・・・・」 色んな文化があるものだと、アレンは感嘆の声を上げる。 「じゃあ、僕も何かやろうかな・・・でも、なにやっていいかわかんないし」 ラビが起きるまで待っていよう、と、呟いた彼に、ジェリーは笑みを深めた。 「じゃあ、あの子が起きるまで、アレンちゃんにはおいしいもの作ってあげましょおねぇ 「はいっ!!」 アレンが途端に目を輝かせ、元気に返事をすると、彼女は弾むような足取りで踵を返す。 「とりあえずはみたらし団子ねー 明るい声をあげ、作業に入ったジェリーを見守りつつ、アレンは気まずげに頭をかいた。 ―――― ちょっと悪いことしちゃったな・・・。 目を覚ました途端に、部屋から溢れるだろう絶叫を思い、アレンは苦笑する。 「ま、いっか」 大したいたずらでもないし、と思い直し、アレンは尻尾を振って待つ犬のようにうきうきと、ジェリーが戻って来る時を待った。 その、数時間後。 ようやく半眼を開けたラビは、自分が抱きしめている物の固く乾いた感触に、夢見心地のまま首をかしげた。 「なにさ・・・?」 ぺたぺたと手を這わせるうちに、べり、と、何かを引き剥ぐ感触がしたが、寝ぼけた頭はそれが何かを特定する事ができず、仕方なく、重い瞼をこじ開ける。 途端、干からびた皮膚の中に二つ、ぽかんと開いた空洞をまともに見てしまい、ラビの口から絶叫がほとばしった。 「マミ――――――――――――――――――――――――――――!!!!」 あまりの恐ろしさに、ラビは自分の温もりが残るミイラを思い切り投げ飛ばす。 が、投げた先が悪かった。 アレンが住み着く以前からこの部屋にあった、怪しいゲル状のものがたっぷり入った大瓶にぶつかり、ガラスを叩き割る。 たちまち石床を灼く黒煙と共に、酸とも腐臭ともつかない刺激臭が立ち上り、ラビは慌ててベッドを降りた。 「ってかなんで俺、アレンの部屋で寝てんさ・・・でゅあっ!!」 広くはない部屋の、壁際に逃げた途端、斧と鎌が刃先を下に落ちて、前髪を何本か持って行かれる。 「ちょっ・・・マジこえぇぇぇぇぇぇ!!!!」 足の切断はなんとか免れたものの、ラビは視覚的にも物理的にも恐怖と危険に満ちた部屋に心底怯えた。 「早く逃げねぇと・・・っ!」 必死の目でドアを見遣るが、そこは既にゲル状の何かに浸食され、踏み入れば彼の足をも溶かしそうだ。 だが、彼にはイノセンスと言う、強い味方がいる。 「アレンにゃ悪ぃけど、ドア壊させてもらうさ!」 あっさりと言って、手を伸ばした先に、しかし、槌はなかった・・・。 「んなーっ?!」 寝ている間に落としたかと、再びベッドに飛び乗ってくまなく探るが、その目にも手にも、槌の存在は感知できない。 「どこ行ったさー!!!!」 そうするうちにも、ゲルはひたひたと床を覆い、明らかに有毒なガスは部屋中に充満していった。 「やっべ・・・!」 慌てて引き剥がしたシーツで鼻と口を覆うと、ラビは格子のはまった窓辺に置かれた箱の上に飛び乗る。 今までそこに置いてあった人形をベッドの上に放り出して、代わりに彼が、椅子に腰掛けた。 「・・・・・・マジやべぇ。 部屋に戻ってからの、記憶がねェさ・・・・・・」 任務から戻り、疲れ果てて到達した部屋が、無残に破壊されていたことまでは覚えている。 しかしその後、自分がどういう行動を取ったのかが、見事に抜け落ちていた。 「ジジィに怒られる〜・・・!」 思わず頭を抱えてしまったラビの手から、シーツが流れ落ちる。 「げっ!!」 足元にまで迫ったゲルに触れたシーツは、一瞬にして蒸発し、更なる毒煙をあげた。 「なんなんさ、これえぇぇぇっ?!」 泣声をあげつつラビは格子に縋り、なんとか酸素を確保する。 が、それにも限界が来た。 背後から迫る毒煙はラビの喉を焼き、彼を激しく咳き込ませる。 「ここで・・・死んだら・・・・・・」 遠のく意識の中、ラビは必死にかすれた声をあげた。 「化けてでてやるぅ〜・・・・・・!」 怨念にまみれた声は、しかし、誰の耳にも届かず、誰の助けも得られないまま、ラビの意識は闇に落ちていった・・・・・・。 「――――・・・きろ・・・ぃい加減に・・・」 遠くから聞こえる声に、ラビは目を閉じたまま手を振った。 「もうちょっと・・・・・・」 「いい加減に起きんか!!」 「ぴぎっ!!」 怒声と共に頭に激痛が走り、ラビは目を見開く。 「んなっ・・・にすんだ、ジジィー!! 割れた!頭割れた!!」 ぷっくりとたんこぶのできた頭を抱え、ラビが泣声をあげると、ブックマンは憤然と紫煙を吐いた。 「お前がいつまでも寝とるからだ! とっとと起きて、支度せんかっ!!」 再びの怒声に、ラビは慌ててベッドから降りる・・・が。 「・・・っジジィ?!」 悲鳴じみた声をあげるや、目を見開いて硬直した彼に、ブックマンの方が訝しげな顔になった。 「どうした?まだ寝ぼけとるのか」 「寝ぼけて・・・?いや!でも!!」 愕然とした表情で、必死に首を振る彼の頭に、ビシッ、と、ブックマンの平手が乗る。 「お前が混乱している訳は後で聞こう。 だから今は、支度をせい」 ぽかん・・・と口を開けて、ラビは動きを止めた。 いつも、彼が見下ろしていたはずの小柄な師が、彼の頭に手を下ろしている。 しかも、わずかではあるが、今のラビは師の顔を見上げていた・・・・・・。 ―――― ど・・・どういうこと・・・・・・?! 思考力すら停止しそうになる状況で、なんとか目だけを動かし、ラビは、師の背後にある鏡を見遣る。 「んな―――――――――――――――――?!」 そこには、小柄な師よりも更に小柄な・・・いや、小柄というよりも幼い自分の姿が写っていた・・・・・・。 「ふむ・・・まるで胡蝶の夢じゃな」 「こ・・・胡蝶の夢・・・?!」 次の目的地へと移動する列車のコンパートメントの中で、ラビ・・・いや、今はまだ、その名ではない少年は、オウム返しに呟いた。 「現在、清と呼ばれる土地の歴史で、戦国時代と言われた頃、宋国に荘子という思想家がいた。 彼は夢の中で蝶となり、蝶として生きるうちに、夢と現実の区別がつかなくなったという。 同じような話は他にもあり、『黄粱(こうりょう)一炊の夢』や、『南柯(なんか)の夢』という話もあるな。『壺中天』もある意味、同じような話やもしれん」 幼い子供相手でも、なんら遠慮なく話を進める師に、しかし、少年は困惑もせずに頷く。 「つまり俺は、大人になった夢を見て、現実と混同しちまったってこと?」 「もしくは、こちらが夢か」 にやりと、意地の悪い笑みを浮かべる師を睨み、少年は不満げな声をあげた。 「俺、真面目に話してんだけど!」 「知っておるわ、そんなこと」 そう言って、ぷかりと煙を吐いたブックマンに、少年は憤然と鼻を鳴らした。 「それで? 18のお前は、何をしていた?」 「あぁ、それなんだけど・・・」 問われた途端、少年の目が、猫のようにきらりと光る。 生まれながらの能力に加え、訓練によって鍛えられた人並みはずれた記憶力が、脳裏でフル回転を始めた。 長い『記録』を整理し、精確な『情報』として口から出たそれに、ブックマンは時折頷きつつ聞き入る。 そして、少年が全てを語り終えたのち、ブックマンは口を開いた。 「奇態なことだな。 ヴァチカン直属の組織で、『黒の教団』というものは存在する。 ただし、これは秘密組織などではなく、公に知られた存在だ。 ふとした拍子に、お前の耳目に入ったのだとも考えられるが・・・・・・」 「それがなんで奇態なんだ?」 「このままこの戦の記録を続けていけば、いずれ、我らは黒の教団に入り込む必要があると予測するからだ」 「・・・・・・へぇ」 ぱちりと瞬きした弟子に、ブックマンはすかさず首を振る。 「このことをお前に明かしたのは、今が初めてだ。 この情報が、夢に影響したとは考えられん」 「ちぇっ」 不服そうに舌打ちし、少年は窓の外へ目をやった。 ヨーロッパの街を出て数日、風景は既に、アジアのそれに変わっている。 流れ行く景色の中に、時折現れる人々は全て、黒髪黒瞳のアジア人だった。 「・・・・・・ナカマ」 「ん?」 弟子の呟きに、ブックマンは片眉を上げる。 「夢の中の俺は、なんでだか、そんなものを大事にしてたよ・・・」 「一族ではなく、か?」 「うん・・・どこの血族でもない、他人だった」 黒髪黒瞳の美しい少女が、彼のことをそう呼び、彼もまた、同じくアジア人の少年と西洋人の少年を、口には出さないものの、そう思っていた。 「・・・変なの。 そんなこと、あるはずがねぇのに」 子供のくせに、妙に大人びた口調で否定する弟子に、ブックマンは眉をひそめる。 「先のことを、安易に予測するものではない」 「俺にだって、このくらいのことは予測できるよ。 俺は、ブックマンを継ぐために在るんだ。 そのためにただひとつだけ、俺は自分の名前を『記憶』から消した。 自分から『世界』の框外に出た俺に、そんなもんができるとは思えないし、作ろうとも思わないよ」 淡々と呟いた言葉に、ブックマンはそっと苦笑した。 それは、ブックマンが弟子へと、ずっと言い聞かせていた言葉。 それを幼い弟子は、自身の言葉にすり替え、自身の意思だと思い込んでいるだけだ。 「まだまだじゃな」 「なんだよ、それ」 そう言って頬を膨らませた少年は、ブックマンの後継者にふさわしく、類まれな記憶力を持ってはいるが、その脳に蓄積される情報は未だ玉石混淆で、真偽の別をわきまえない。 だが今はまだ、それでいい、と、老人は窓の外を見つめる弟子の横顔にそっと、微笑んだ。 真偽を分けるということは、『情報』に対し、『主観』を持ってあたるということ。 経験の浅い者の『主観』は、百害あって一利なしだ。 特に、ブックマンの一族のように、精確な『記録』が求められる立場においては。 無関係と思われた情報が、のちに多大な影響を及ぼしていたと判明することは、今までにも多々あった。 ゆえに『歴史』を記録する者は、情報が熟す時を待つ必要があるのだ。 それを知ってか知らずか、少年は見るもの聞くもの全てをその幼い頭に『記憶』し、『記録』していた。 ただひとつ、自身の名前以外は――――。 「喪失感は、まだ大きいか」 師の、独白とも取れる呟きに、少年は再び瞬いた。 しばらく考えて、首をかしげる。 「ジジィが言ってんのが、俺のホントの名前のことだったら、別に、失くして悲しいなんて思ってねぇよ。 どうせ、ジジィと二人きりの旅なんだ。『お前』で十分だよ。 他人が俺を呼ぶのに困るんなら、『ブックマンJr.』でいいじゃんか」 「そうか・・・」 「そうだよ。 俺には、役目があるからね!」 そう言って、キラキラと目を輝かせる少年に、ブックマンは思わず笑みそうになる口元を引き締め、殊更憮然と言う。 「お前が私の後を継ぐなんぞ、100年早いわ」 「100年ってジジィ、いつまで生きる気だよ・・・。 今でさえ十分妖怪じみてんのに、100年後っつったら、本物の化物だよ!」 「誰が妖怪だ!」 ごつんっと、ゲンコツをお見舞いされ、少年は赤い頭を押さえて泣声をあげた。 「なぁなぁジジィ。 あれ、なんだ?」 列車から船に乗り換えた後は、何日も四方を水平線に囲まれた海の只中にあった。 見るものとてない風景に、他の船客達は早々に飽きて、船室にこもっている。 しかし、少年はおさまりの悪い赤毛を潮風になぶらせながら船中を走り回り、様々なものを目ざとく見つけては、師や周りにいる船員達から知識を吸収していた。 「元気のいい子だなぁ。 あんたの孫かい?」 「あぁ、そんなものだ」 ブックマンが頷くと、人懐こい少年にほだされた船員達の頬も緩む。 「あんなに物覚えのいい子は初めて見たよ。 今のあの子は、波と潮風に負けない腕力さえあれば、こんな船、簡単に操るだろうよ」 仲間の言葉に、別の船員も頷いた。 「漁師にだってなれるさ。 船の周りにいた魚の名前と漁法を、全部覚えちまった!」 船員達が感嘆の声をあげる中、少年が今度は鳥を追いかけて甲板を駆け去って行くと、彼らの興味はブックマンへと移る。 「ところであんた達、どこまで行くんだ?」 「この船は確かに客船だが、行き先は・・・」 言い難そうに口を濁した船員に、ブックマンはなんでもないことのように頷いた。 「ペルーの首都、リマへ向かう」 「あんた、それは無茶だ!」 「あそこはもうすぐ、戦場になるんだぞ?!」 「そんなところに、あんな子供を連れて行く気か?!」 船員達の非難を、しかし、ブックマンはどこ吹く風と聞き流し、淡々と言う。 「それが、我らの目的だからな」 「しかし・・・!」 同意を求め、仲間達を見渡した船員は、彼らの表情に自分と同じ戸惑いを見て、ブックマンに詰め寄った。 「なにが目的かは知らないが、あんな小さな子供を戦場に連れて行くなんて、正気の沙汰じゃない! 悪いことは言わない・・・ペルーに入るのは止めた方がいい!」 彼が決然と言い放つと、老人は、拍子抜けするほどあっさりと頷く。 「それもそうだ。 私とて、なにも好き好んで戦場に赴くわけではない。 用事の方は、なんとか理由をこじつけて断ることとしよう」 そう言って、小柄な肩をすくめたブックマンに、船員達は深々と吐息した。 「考え直してくれて良かったよー・・・!」 「じいさん、頑固そうだからさー」 「あぁ、意地でも行くって言い張ると思ってた!」 ほっと緩んだ顔を見上げて、ブックマンは意地の悪い笑みを浮かべる。 「心配かけて、すまなんだの。 しかし、おぬしらの気遣いには感謝する」 「イヤイヤ!」 「気遣いなんてもんじゃ・・・なぁ?」 潮焼けした顔を真っ赤に染めて照れる彼らに笑みを深め、ブックマンはぺこりと、東洋式のお辞儀をした。 「では、私はそろそろ船室に入らせてもらおう。 さすがにこの暑さの中で、子供を追いかけるのは辛いわい」 「おう、ゆっくりしてな、じいさん!」 「孫が海に落ちないよう、俺らが見ていてやるからよ!」 「感謝する」 船員達の好意に再びお辞儀をし、ブックマンは船室に入る。 と、そのすぐ後から、少年が入ってきた。 「ジジィ、目的地を変えんのか?」 「まさか。 ここで言い争うても面倒なだけだ。 相手に合わせただけのこと。 目的地は変わらん」 淡々と言ってのけると、少年も、あっさりと頷く。 「わかった。 じゃあ俺、もうちょっと遊んでくる!」 言うや、機敏に踵を返した弟子を見送り、ブックマンは苦笑した。 「あんな子供・・・確かにな」 自身の4分の1しか生きていない年齢の子供を戦場に連れて行くなど、確かに正気の沙汰ではないだろう。 だが、ブックマンを継ぐ者には、幼い頃よりこの世界の『現実』を見せるのが慣わしだ。 それが、どんなに残酷なものであろうと・・・いや、だからこそ、早めに知らしめるのが、彼ら一族のやり方だった。 「幼いが、弱い子ではないよ」 確信に満ちた口調で呟き、ブックマンは口の端に笑みを載せる。 「むしろ、あの年頃の私よりも・・・」 古い記憶を手繰り寄せようとした彼は、しかし、途中でやめてしまった。 「比べるなど、くだらぬことだ・・・」 自身は自身、彼は彼。 ブックマンは笑みを苦笑に代え、狭い船室に押し込められたベッドに腰を下ろした。 「・・・すげぇ。空気が痛ェよ」 ペルーに入国した時から、段々と張り詰めていった空気は、リマに入った途端、最高潮に達していた。 足音を立てることすら気を使うほどの緊張の中、ブックマンは不用意に駆け出そうとした少年の襟首を掴んで引き寄せる。 「うろちょろするでない! 私から離れるな」 声を潜めて叱声を発した師を上目遣いで見上げ、少年は素直に頷いた。 逆らえない気迫と、反駁を許さない空気が、そこにはある。 おとなしく師と並んで歩きながら、少年は街を見渡した。 「・・・文字にできない情報、ってのが、あるんだな」 ぽつりと呟いた彼に、ブックマンは頷く。 「それが、我らが『歴史』を文字に残さない理由だ。 事実は事実として記録するが、この空気を記録するのに、あらゆる言語も語彙が少なすぎる」 「だから俺らは、俺らだけの『言葉』を使うのか?」 「そう。 ブックマンの一族のみが使う言語・・・歴史の『事実』と『状況』と『真実』、それらを混在せず、分類するにふさわしい言語。 いや、そうするために作られた言語が、我らの『言葉』だ」 「会話するには、超不便だけどなー」 軽口を叩く弟子を、ブックマンはじろりと見遣った。 今の今まで、この戦場の空気に呑まれていたと言うのに、もうこの場に溶け込んでしまっている。 少々浮ついたところはあるが、尋常ではない順応力に、思わず笑みが漏れた。 「本当にお前は・・・」 言いかけて、ブックマンは言葉を切る。 「ジジィ?」 「こっちだ」 乱暴に腕を掴まれた少年は、たたらを踏みつつも、建物の陰に隠れた師に従った。 「軍隊か・・・」 軍靴を響かせながら、血走った目で街を駆け抜ける兵士達を、二人は息を潜めて見送る。 この状況下で、よそ者である彼らが兵士に見つかれば、不愉快な思いをすることは目に見えていた。 「下っ端にかまけている暇はない。 とっとと司令官に会って、行動の自由を保証させる」 兵士の姿が視界から消えてしまうと、ブックマンは素早く道へ戻る。 彼に手を引かれて、少年はにこりと笑った。 「りょーかい!」 少年にはまだ、詳しい仕組みはわからないが、『ブックマン』という一族は『世界』の框(わく)の外にありながら、あらゆる組織と繋がっている。 特に問題のない国に入る時はともかく、この国のように動乱の只中にある国で行動するには、最高権力者の後ろ盾が何よりも重要だった。 その伝手を、彼の師はいつもたやすく繋いでしまう。 いかなる権力に対しても屈せず、暴虐の独裁者に対しても泰然自若と接するその姿を、少年はけして師本人には言わないものの、『かっこいい』と思い、誇りにもしていた。 それだけではない。 まるで、戦場となるこの街を容赦なく照らす太陽のように苛烈でありながら、常に冷静で、物事を第三者の目で捉え、真実を記録していくその姿は、世界を知りたいと願う彼にとって、憧れの存在だった。 ―――― 彼についていけば、間違いはない。 そんな確信を持って、少年はいくつもの戦場を師と共に渡った。 名を変え、姿を変え・・・・・・やがて辿り着いた場所は、世界の歴史の水面下で繰り広げられる『戦争』の、一方の陣営。 つい先日、大きな戦を終えたばかりらしいその陣営の礼拝堂には、棺と悲しみが満ちていた。 「こりゃー・・・負け戦だねぇ」 ぽつりと呟いた彼―――― ラビの声が聞こえたかのように、棺に縋っていた少女が顔を上げる。 黒髪黒瞳の、美しい少女・・・・・・! 「こっ・・・?! こここここここここここ!!!!」 ラビの奇声に、師と話していた教団の幹部が、訝しげな目を向けた。 「は?」 「なにを騒いどるのだ、ラビ」 忌々しげに舌打するブックマンに、しかし、ラビは慌てて詰め寄る。 「だってジジィ!!胡蝶が!!」 思わず絶叫したラビは、その言語を一族のそれへと変えた。 『昔の夢に出てきた女の子だよ、あれ!!』 ブックマンの一族である以上、ラビに記憶違いなどあろうはずがない。 予知夢だ、と騒ぐ弟子を、ブックマンは強烈な蹴りで無理矢理黙らせ、改めて教団の幹部、コムイ・リーへと向かった。 「すまんな、騒がしい弟子で」 「い・・・いえ・・・・・・」 ラビが彼の妹を指して騒いだことには、多大な関心を引かれたものの、血みどろになって床に這うブックマンJr.の姿に、さすがのコムイも追求する事ができず、ただ、ブックマンへ愛想笑いを向ける。 「ご覧の通りの状況です・・・あなた方の助力は、願ってもないこと。 どうぞ、よろしくお願いします」 「こちらこそ」 短く言うと、ブックマンはまだ、床に這う弟子を蹴りつけた。 「いつまでも寝とらんで、お前も挨拶せい!」 「あ・・・あぃ・・・・・・ヨロシク・・・・・・」 「ヨロシク・・・・・・」 血塗れの顔をあげて笑うラビに、かなりのところ退きつつ、コムイは彼とも握手する。 ・・・その時から、ラビのエクソシストとしての生活が始まった。 ――――・・・いつも、『歴史』を外から眺めていた。 なのに今回は、『兵士』として、内側から歴史を見ろという。 ブックマンたるもの、様々な視点を持てとの、師の命令だ。 その言葉に、なんの疑問も差し挟んだりはしない。 自身は『個』ではなく、大いなる歴史の記録を次代へと引き継ぐ組織の一部になるべきと、己に科してきた。 『個』の感情など、捨てるべきと・・・・・・なのに。 ナ・・・カ・・・・・・マ・・・・・・・・・ 今ではなぜか、その言葉が胸に突き刺さる・・・。 ずっと疑いもしなかった師の言葉が、辛くなってきた・・・・・・。 『なぜ』 『くだらない』 『あってはならない』 『ふさわしくない』 一族の『言語』が、何度も脳裏に響く。 そう・・・『ナカマ』なんて、ブックマンの言語にはありえない。 リナリーが、微笑んで手を差し伸べる・・・『ナカマ』だと。 ユウが、照れ隠しに憮然とする・・・・・・『ナカマ』だからと。 アレンが、不安そうに追いかけてくる・・・『ナカマ』でしょうと。 ア リ エ ナ イ 。 そんな言葉は、一族の言語にありはしない。 そんな言葉がなくとも、『記録』に困りはしなかった。 なのに、今はその言葉が、ラビを困惑させている。 精確な『記録』に邪魔な『感情』を揺り起こす。 『なぜ』 『くだらない』 『あってはならない』 『ふさわしくない』 一族の『言語』が、彼自身の声で繰り返される。 「そんなの・・・答えられっかよ!」 苛立たしげに呟く間にも、歴史は彼を呑み込んで、容赦なく進んでいく。 が、冷静に状況を見守る師の傍らで、ラビはいつしか、自身の耳目が得るものに、『感情』のフィルターがかかっているのではないかと疑うようになっていた。 それはブックマンを目指す者にとって、恐怖以外のなにものでもない。 「俺は・・・」 『なぜ』 「ナカマなんて・・・」 『くだらない』 「感情なんて・・・」 『あってはならない』 「俺はブックマンに・・・・・・」 『ふさわしくない』 一族の『言語』がもたらす答えに、ラビは必死に首を振った。 「俺は、ブックマンになるんだ・・・!」 動機こそ単純だったが、その願いは真実。 なのに今では、『絶対』だった師の訓えさえ、辛く感じる自分に戸惑っていた。 『なぜ』 「俺は戸惑っている・・・?」 『くだらない』 「気の・・・迷いだ」 『あってはならない』 「感情なんて」 『ふさわしくない』 「俺は・・・ブックマンに・・・・・・」 ―――― ラ・・・ビ・・・・・・ 名を呼ばれて、目を見開いた。 目の前で揺れる白髪に、鼓動が跳ねる。 『ふさわしくない』 「うわぁぁぁんっ!!そんなコト言わないでさ、ジジィ――――――――!!!!」 絶叫して両腕を伸ばし、目の前の師に抱きつこうとしたラビは、しかし、強烈な力で壁に叩きつけられた。 「・・・永眠しますか、このウサギ」 「ほべっ?!」 驚いてよく見れば、ラビを壁に押し付けているのは、発動したアレンの左手だ。 そしてその先には、殺気立った彼の顔があった。 「・・・誰がジジィですか。超ムカつくんですけど!」 「えぐっ・・・?!夢・・・ッ?!」 「人の部屋でぐーぐーと、いつまで寝てんだと来てみたら、なんで箱の上なんかでうなされてんですか。 寝相が悪いにも程がありますよ」 「え? いや・・・えーっと・・・・・・なんつーか、こー・・・・・・」 珍しく記憶が混乱していることに混乱して、ラビが頭を抱える。 が、下を向いた視線が、床に散らばったガラス片をとらえた瞬間、記憶がよみがえった。 「そう! 目ェ覚めたらなんでか俺、ミイラと一緒に寝てて! スゲーびっくりして、思わず投げちゃったらあの大瓶に当たって中のもんが出ちまったんさ! そしたら、有毒ガスは出るわ意識は遠のくわ、散々だったさ!!」 ぱっと顔を上げてまくし立てると、アレンが気まずげな顔をして、目線をそらす。 その様子に、ラビは目を眇めた。 「アーレーンーくぅーん? ちょっとこっち向くさ、お前」 「え?なに?」 きょときょとと泳ぐ目を覗き込んで、ラビはアレンに詰め寄る。 「お前、俺に謝ることがあるよな? 怒んねーから、にーちゃんに言うてみ?」 「・・・・・・絶対怒るから、ヤダ」 「アホか!! その態度でもうバレバレさ!! よくもミイラ仕込みやがったな!」 「だってラビがいきなり僕の部屋に来てベッド占領するからー!!」 むにーっと、両頬を引き伸ばされながらアレンが悲鳴を上げると、ラビがきょとんと目を見開く。 「あれ?そうなん?」 「そうだよ!覚えてないんですか?!」 真っ赤になった頬をさすりながらアレンが抗議すると、ラビはあっさりと頷いた。 「なんで俺、よりによってアレンの部屋なんかに来るかなぁ〜?」 「その言葉、のしつけて夏のお中元返しですよっ!」 それより、と、アレンは改めてラビに詰め寄る。 「君が僕の部屋を1日占領してくれたおかげで、もう8月5日になってしまいましたが、何か案はありますか?」 「5日・・・って、マジ?!」 「・・・おかげさまで、昨日は一晩中、使える部屋を探してさまよいましたよっ! もう・・・科学班、無茶しすぎですっ!」 ぷぅっと、頬を膨らませるアレンに苦笑し、ラビはようやく避難場所だった箱から降りた。 「ほんじゃ、急いで準備するぜー♪ アレン、手伝うさ!」 「はぁい!」 部屋を出たラビを追いかけて、アレンも部屋を出る。 そのまま廊下を駆け抜けて、ラビは無残に砕けた自室に至った。 「あーいーつーらー・・・」 軋むドアを開ければ、今すぐにでもエレベーターが設置できそうな吹き抜けの空間がある。 「今までせっせと集めた俺の・・・」 「ガラクタ」 「宝物さっ!!」 スパンッ!と、いい音をさせてアレンの頭をはたき、ラビは部屋の中心に開いた大きな穴に落ちないよう、壁に沿って歩いた。 「ねぇラビ!危ないよー?」 ドアの廊下側に立つアレンが声をかけると、ラビは振り向きもせず手を振る。 「ヘーキヘーキ。 万が一落ちても、俺には・・・」 「あ。 そう言えば昨日、廊下で君のイノセンス拾っ・・・ラビィィィィィィ?!」 アレンが言い終わる前に、目の前でラビが踏んだ床が崩れ、彼もろとも落ちて行った。 「受け取って!!」 すかさず投げたイノセンスが、大穴の底付近で発動する気配がする。 「たたたたた・・・助かったさ・・・・・・!」 長い柄の先に縋って、青ざめた顔を大穴から出したラビに、アレンもほっと息をついた。 「もー・・・びっくりしたぁ・・・。 そんなに大事なものなんですか?」 「大事っつーか、せっかく用意したんだから、渡さなきゃもったいない、ってカンジさ」 大穴から這い出したラビは、そう言って果敢にも、部屋の探索を続行する。 「はぁ・・・。 今年は一体、なにを用意したんですか?」 考えてみれば、ラビが今までにブックマンへのプレゼントとして用意したものはいつも、とんでもないものだった。 パンダだの古代の遺跡から発掘されたハンコだの・・・・・・。 「ミイラなら、僕の部屋にありますけど?」 欲しいですか、と尋ねれば、ラビは心底嫌そうな顔をして振り向いた。 「あれは好みじゃないさ」 「・・・どんなのなら好みですか」 「そりゃもちろん、女の子!」 「穴に落ちろ、エロウサギ!」 アレンが足元の瓦礫を拾って投げつけると、慌ててよけたラビが、キャンキャンと喚く。 「なにすんさ! 女好きはお前もだろ!!」 「僕はレディに対して、礼儀正しく振舞っているだけです!」 「お前にかかれば、生物学上の雌は全部レディじゃないさ!」 「なんですか!それが悪いとでも?!」 お互い喚きあいながら瓦礫を投げ合っていたが、ラビの喚声がある瞬間、歓声に代わった。 「めっけたさ!」 「なにを?」 「ウジャトの目!」 「・・・・・・誰の目ですって?」 反射的に左眼を手で隠したアレンに、ラビが苦笑する。 「魔よけさ、魔よけー ジジィ、今年で卒寿なんだけどさ、卒って字、あんまよくねーじゃん?」 「知りませんよ。僕、漢字の国の人じゃありませんから」 「あ、そっか。 つまり『卒』って字は、確かに『多い』って意味もあんだけど、『死ぬ』って意味もあるんさ」 「・・・っ縁起悪!」 思わず息を呑んだアレンに、ラビも笑みを収めて頷いた。 「んまー、『親死ね 子死ね 孫死ね』って言葉が縁起いいって理屈も通る宗教観だから、数えで90まで生きりゃ、確かに大往生かもしんねーけど、ジジィにゃまだまだ長生きして欲しいからさー とりあえず、気休めにでも魔よけをおくっとこーかと」 「・・・・・・君にしては珍しく、まともなチョイスじゃないですか。 どうしたんですか。 頭でも打った?」 「・・・お前こそ、どーゆー感想さ。 俺はいつも、まともなチョイスしてんじゃないさ」 「・・・・・・パンダや古代の遺物が真っ当だと?」 「真っ当さ。 これだって、わざわざエジプトの墓から掘り起こした・・・・・・」 途端、ぱたりと手で口を覆ったラビに、アレンが目を眇める。 「・・・・・・なんか今、聞き捨てならない言葉が聞こえたんですが」 「・・・・・・考古学者に知り合いがいてー」 「それ、個人がどうこうしていいもんじゃないことは確かだよね?」 「いずれ、飽きたら博物館に収めっからいいじゃないさ。 英国の貴族なんて、スポンサーになってんのをいいことに、貴重な宝物を個人で所蔵してんだからさ!」 「そりゃまぁ・・・そうですけど・・・・・・」 「同じことさ!」 「同じこと・・・かなぁ・・・・・・」 多大な疑問を抱きつつも、アレンはこれ以上話しても無駄だと早々に判断し、降参の手を上げた。 「わかりましたよ。 それで? 僕はなにを手伝うんです?」 まさか、それを贈るためだけに手伝いはいらないだろうと問えば、ラビはにんまりと口の端を曲げる。 「演出、手伝って ふふふ・・・と、楽しげな笑声をあげ始めたラビに、不安は更に募ったが、興味の方が勝った。 「了解です。 ただし、怒られない程度にして下さいね」 無駄だろうけど、と思いつつも申し出ると、ラビは自信満々の笑みを浮かべて頷く。 「そんな保証、できるわけがないさ!」 「じゃあ頷かないで下さいよ!」 ジェスチャー間違ってるよ!というアレンの非難はどこ吹く風と受け流し、ラビは、次なる演出の準備へと、アレンを伴って行った。 「ラビー! クロウリー連れて来ましたよ・・・って、ちょっと待って。 何をしてるんですか、何を」 クロウリーを傍らに、鈍い音を立てて部屋の隅にモーニングスターを転がしたアレンは、長い配線を手足に絡ませながら、嬉々として部屋の飾り付けをするラビに乾いた声をかけた。 「んー? やっぱさ、護符を渡すんなら、周りがおどろおどろしい方がありがたみが増さね?」 爽やかな汗を散らしながら、ラビはクロウリーの存在に目を輝かせる。 「と、いうわけで、マイスター 「はっ・・・はぃぃっ?! わっ・・・私のことであるか?!」 「うんっ お部屋レイアウト監修してほしいさ 両手を組んで『お願い』するラビに、クロウリーは慌てて手を振った。 「そ・・・そんなこと、やったことがないである!」 「ダイジョブダイジョブ クロちゃんち風にしてくれれば、十分だから 「いや・・・それはちょっと・・・・・・」 クロウリー城の様子を知るアレンが、さすがに止めに入るが、ラビは聞いてくれない。 「どうせなら、お化け屋敷風にするとか、良くね?!」 「良くないでしょ・・・」 城中に飾ってある武器や怪奇な品を集めろと言われた時から、既に嫌な予感はしていたが、誕生会にお化け屋敷はないだろうと言うアレンの意見は、軽やかに無視された。 「な? 協力してくれ、クロちゃん 「そ・・・そういうことであるならば・・・・・・」 「説得されちゃったよ・・・」 アレンが頭を抱えている間にも、手早いラビはクロウリーの意見を参照しながら、部屋をおどろおどろしく飾り立てていく。 古い鎧に赤い粘液を絡ませた武器を持たせたり、不気味な絵にクモの巣に似せた綿を掛けたり、壁一面に不気味な面を貼り付けたりと、本当にお化け屋敷のようになってしまった部屋の中心で、アレンは深々と吐息した。 「ブックマンはいいですよ、ブックマンは・・・だけど、こんなに怖くしちゃって、お守りを持ってない人はどうするんですか?」 「お前は左手の十字架があるからいいじゃん」 「僕はいいですけど・・・」 こんな部屋を見たら・・・その上、ラビが提案し、アレン達に協力を求めた演出を実行したならば、リナリーやミランダが本気で悲鳴を上げそうだ。 「ハロウィンじゃないんだから・・・」 「いいじゃん。俺の誕生会はいっつもハロウィンみたくなるしさ」 「そりゃー君のもとに集まるプレゼントのせいでしょーよー・・・なに?今年も神田のプレゼントは、呪いの人形ですか?」 「あは 俺、去年ジジィから百万塔陀羅尼(ひゃくまんとうだらに)もらったしー 幽霊憑いてても怖くねーさ 「いっそ憑かれればいいのに・・・」 忌々しげに舌打したアレンの傍らで、クロウリーが無邪気に微笑んだ。 「しかし、このような趣向も面白いものであるな! パーティにもこのように様々な種類があるとは、驚きである!」 「種類・・・まぁ、確かに特殊な部類ではありますねぇ・・・・・・」 世間知らずなクロウリーの、無邪気すぎる感想にも、アレンは乾いた笑声をあげる。 「でもまぁ・・・このくらいはやらないと、ブックマンには驚いてもらえないかな」 「だろー? さすがのジジィの記録にも、こんな誕生会をやってもらった記憶はないはずさ!」 そう言って、楽しそうに笑うラビに、アレンとクロウリーは顔を見合わせた。 頷きあうと、図ったようなタイミングで同時に手を伸ばし、ラビの頭を撫でる。 「そうなんだ・・・」 「可愛いところもあるであるな」 「え?! ナニナニナニ?!」 二人の手の下で目を剥くラビに、なぜか彼らは莞爾と笑う。 「おじいちゃん、大好きなんですねぇー 「孝行は良いことである」 「えぇっ?!」 真っ赤になって飛びすさったラビを、二人はいまだ、莞爾とした笑みを浮かべたまま見つめた。 「おじいちゃんのために、毎年毎年趣向を凝らして・・・」 「祖父殿の長寿を願って貴重な品を求め・・・」 「知恵を絞って特別なパーティを用意するなんて!」 「感動したであるっ!!」 「ちっ・・ちがっ・・・!! 俺は別に、そんなつもりじゃ・・・!! そもそも俺、血は繋がってても孫じゃねェし!!」 耳まで赤くして、必死に手を振るラビの姿に、二人は愛らしい小動物でも観賞するかのように笑みを深める。 「なんさその、微笑ましげな顔はー!!」 「だってラビ・・・」 「とても、微笑ましいである!」 「うわぁぁぁぁぁぁぁ!!! そんな目で俺を見るんじゃないさぁぁぁぁぁぁ!!」 「やかましい!」 ラビが絶叫した途端、それを上回る怒声と共に、強烈な蹴りが炸裂した。 「たわばっ!!」 「なにをさわいどるか!」 軽々と宙を舞い、床に叩きつけられたラビは、ブックマンの怒声に血まみれの顔を上げる。 「なにすんさ、ジジィー!頭割れたさ!」 「割れれば少しはまともになるやもしれんわっ!」 ブックマンの容赦ない口調にも、アレンたちの微笑ましさはとまらなかった。 「仲良しさんですねぇー 「いやいや、あれと比べてはいかんであるよ」 「それもそうですねー」 二人が爽やかな笑声をあげていると、ブックマンに続いて、教団の面々が部屋に入り・・・一様に驚きの声をあげる。 中でも、 「ナニこれぇぇぇぇ?! アタシが用意したお花はどうしちゃったの?!」 と、ジェリーのヒステリックな悲鳴は一際高く、部屋中に響いた。 「ご・・・ごめんなさい、ジェリーさん。 ラビが装飾変えちゃって・・・・・・」 「わ・・・私がレイアウトしたである・・・」 ラビの代わりに頭を下げた二人を前に、ジェリーは憤然とたくましい腕を組む。 「・・・あの子が違う部屋を使いたい、って言い出した時から、なんかやるだろうとは思っていたけどぉ! ナニコレ! 全然お祝いって雰囲気じゃ・・・」 「そーぉ? おもしろいとおもうけどなぁー?」 ジェリーの言葉を遮る暢気な声に、アレン達はようやく顔を上げた。 と、彼女の後から部屋へ入って来たコムイが、不気味なお化け屋敷と化した部屋を感心したように見回している。 「やっぱり、ブックマンの卒寿って言ったら、このくらいやらないと趣向を凝らしたうちには入らないんじゃなーぃ?」 「そ・・・そりゃそうでしょうけど、せっかくの・・・・・・」 「まぁまぁ。 ここのところ、暑かったしねー。 気分だけでも涼しーくなるのはいいんじゃない?」 ね?と、笑顔で説得され、ジェリーは渋々ながら頷いた。 「・・・わかったわ。 もうお料理運んでもいい?」 後半はラビに問うと、彼はぶんぶんと首を横に振る。 「もうちょっと待ってさ!これからちょっと、面白いことすっから と、得意げに笑うラビに、しかし、ジェリーはあからさまに不安げな顔をした。 彼女の表情につられるようにアレンも、 「やっぱり・・・リナリーやミランダさんは嫌がりますよね・・・?」 そう言ってコムイを、上目遣いで見上げると、彼は意外にも、にっこりと笑って首を振る。 「リナリーはホントのお化けが嫌いなんであって、こういうのはむしろ、好きな方だよ。 ミランダさんはどうだか知らないけど・・・」 その時、ドア付近で引きつった悲鳴が上がり、一斉に集まった視線の先で、黒いドレスのミランダが、白衣のリーバーに抱きとめられていた。 「・・・大丈夫じゃなかったみたいです」 「・・・・・・であるぅ〜」 泣声をあげるアレンとクロウリーを、失神したミランダを抱えたままのリーバーが、拒絶を許さぬ表情で手招く。 「ラビも」 短いが、迫力のある声に、ラビも首輪を引かれた犬のように歩み寄った。 途端、頭に走った激痛に、三人は揃ってうずくまる。 「こういうことは、あらかじめ言っておくように」 「あぃっ・・・すびばぜん・・・っ!」 彼らが揃って頷くと、リーバーは拳を下ろしてミランダを抱き上げた。 「すんません、ブックマン。ちょい外します。 すぐ戻れるとは思いますが」 「気にするな。 私の弟子が、余計なことをした」 ぺこりと頭を下げたリーバーに苦笑を返し、ブックマンは、まだしゃがみこんでいる三人を見下ろす。 「さぁ。 次は、なにをしでかしてくれるのだ?」 どこか楽しげな口調に、涙を浮かべた二対とひとつの目がブックマンを見上げ、次にお互いの顔を見合った。 「ほんじゃー・・・」 ラビの掛け声で、立ち上がる。 「ハイハイ、ごめんなさい、みんな!」 「ちょっとさがるであるよー!」 ラビとブックマンを部屋の中心に残して、アレンとクロウリーが団員達を、最も危険の少ないドアの近くに集めて部屋の明かりを消した。 「ラビ!オッケーです!」 「アイサー♪」 「おい・・・」 なにをする気だ、と、眉をひそめたブックマンの前で、ラビがイノセンスを発動する。 「火判っ♪」 軽い口調で言って、彼はいつもより随分と小さな、イノセンスの炎を出現させた。 「屋内で火を使うのは・・・」 「まぁまぁ そんな、堅っ苦しいこと言うもんじゃないさ にこりと笑い、ラビは炎を纏った槌を床に叩きつける。 飛び散った火花は、薄暗い部屋にちらちらと舞い、壁にぶつかって弾けた・・・と、思った瞬間。 壁際に置かれた鎧や仮面、絵の中の人物全ての眼窩(がんか)に、光が灯った。 「んぎゃっ!!」 「なんだこれ!!」 「こわっ!!」 あまりに不気味な光景に、集まった団員達が、口々に悲鳴をあげる。 が、その中で一人、ブックマンだけは冷静だった。 「よくもまぁ・・・これだけの電球を仕込んだものだ」 「あっちゃー・・・・・・。 やっぱすぐバレたさー・・・・・・」 ブックマンの呆れたような、しかし、わずかに感心したような口調に、ラビは肩を落とす。 「ちょっとは驚いたふりでもすりゃいいのに、ホント、サービス精神のないジジィさ!」 「十分驚いたわい。 卒寿の祝いに、こんな演出をするお前にな」 くつくつと、笑声をあげるブックマンに、ラビもつられて笑い出した。 「祝いってゆーには、縁起の悪い字をあてがってるんだもんさ。 だから、ジジィの代わりに呪いを引き受けそうなもんを集めたんだぜ?」 得意げに胸をそらした弟子に、ブックマンはとうとう吹き出す。 「ヒトガタにしては、随分大仰なことをする!」 「大仰でいいくらいさ。なんたって、来年で90だかんな、ジジィ」 そう言うとラビは、ほい、と、ポケットから出した包みをブックマンに渡した。 「そんなわけで、今年のプレゼントはコレなー♪ しっかり魔除けてくれさ 演出が派手だった割にはいやに軽々と渡された包みを開け、ブックマンはまた、笑い出す。 「ウジャトの目か・・・!」 「目、繋がり いたずらっぽく笑って、ラビは自身の目を指した――――・・・眼帯に隠された目を。 「長生きしてさ、ジジィ にこりと笑う弟子に、ブックマンは笑みをたたえたまま、隼の目をかたどった護符を身につけた。 「お前のようなジュクジュクの未熟者が跡取りでは、死んでも死にきれんわ。 むしろそれが、私の長生きの秘訣かも知れんな」 「じゃー俺、ずっと未熟者のまんまでいるさ ラビが陽気に笑った途端、 「ぶざけるなっ!!」 がすっ!と、鋭い爪で切り裂かれる。 「んなっ・・・! なにすんさ、ジジィー!!」 血みどろになって抗議する弟子を、ブックマンは苛烈に睨みつけた。 「とっとと一人前にならんか! わしゃお前に跡目を譲った後は、南の島でのんびり暮らすと決めておる!!」 「あ!ずり・・・! 俺だってバカンス行きてーさ!!」 「100年早いわ、この未熟者!!」 きゃんきゃんと喚きあう師弟と、不気味すぎる部屋の雰囲気に呑まれ、団員達全員がパーティの開始をためらう中、パタパタと軽やかな足音を響かせて、リナリーが現れる。 「遅れてごめんなさい! ・・・って、どうしたの、みんな?」 ドアの近くに固まっている団員達を、部屋の外から不思議そうに見遣ったリナリーは、彼らの隙間から部屋の中を覗き見て、悲鳴をあげた。 「んなっ?! なに?!どうしたのこれ?!」 愛しい妹の悲鳴を聞きつけて、真っ先に駆け寄ったコムイが、慌てるリナリーの肩を抱いて微笑みかける。 「大丈夫大丈夫 ラビの演出だよ 「え・・・演出?」 「そ あらかじめ、鎧や仮面の目の奥に電球を仕掛けておいたんだね。 あの子が火判で火の粉を散らした瞬間、アレン君かクロちゃんが電源を入れた・・・そうでしょ?」 「あー・・・やっぱり、バレバレですか」 アレンが苦笑すると、コムイは朗らかな笑みを返した。 「ボクを誰だと思ってんのさー。 でも、目に炎が灯ったように見せる演出は面白かったよ 「えー・・・そんなことやったんだ! 見たかったなぁ・・・・・・」 リナリーが残念そうに吐息すると、コムイは笑って首を振る。 「リナリーが見ていたら、泣いちゃってたかも知れないよ 「そっ・・・そんなこと、ないもんっ!」 「はは・・・無理をしない方がいいであるよ、リナリー。 ミランダは演出を見る前に、部屋の不気味さに驚いて失神したであるからな・・・」 クロウリーが気まずげに言うと、リナリーはやや怯えた様子で兄に縋りついた。 「大丈夫大丈夫 お兄ちゃんがいるから、怖くないよー リナリーに頼られたコムイが、至上の悦びといわんばかりにはしゃぎ狂って彼女を抱きしめる。 「あの・・・コムイさん、そろそろ始めませんか?」 乾杯の音頭を取るべき室長が、妹への愛に溺れる姿からやや目を逸らしながら、アレンが遠慮がちに提案した。 「えー・・・」 せっかく頼ってくれてるのに、と、不服そうなコムイを、リナリーがやんわりと押しのける。 「もう大丈夫だよ、兄さん。 ブックマンのお誕生会、始めましょ」 「そうだねー・・・」 渋々とリナリーから離れ、コムイは団員達を掻き分けて部屋に入った。 「じゃあ、ジェリー! セッティングをお願いするよ!」 コムイに依頼されるや、有能な料理長は部下の料理人達を従えて、瞬く間にパーティ会場を整える。 「いつでもどうぞ」 すまし顔で言った彼女へ、皆から賞賛の拍手が沸いた。 「では! ブックマンの卒寿と、今後の長寿を祈念しましてー!乾杯っ!!」 「乾杯!!」 コムイの音頭に唱和し、一斉にグラスが掲げられる。 「お誕生日おめでとうございまーす!」 「うむ、ありがとう」 一同の祝辞にぺこりと頭を下げ、ブックマンが杯を干した。 「さっすが! いい飲みっぷりっすねェ!」 「あんまり呑み過ぎないようにして下さいよー!もう年なんだし!」 「・・・余計な世話だ」 ブックマンが苦笑すると、どっと笑いが起こる。 「じゃーもう一杯♪」 「ってかその前に、プレゼントが・・・」 「あ!花!花をあげてなかった!!」 団員達に囲まれ、楽しげに酒を酌み交わすブックマンを、今はやや遠くから見つめながら、ラビはグラスを口に運んだ。 ―――― ジジィは・・・いつまで俺と一緒にいてくれんだろ・・・・・・。 考えたくもないことだが、人間である限り、師の命は永遠ではない。 ―――― 俺は・・・ジジィの跡を継げるんだろうか・・・・・・。 ふと浮かんだ考えに、背筋が凍った。 そんなことは、今まで思いもしなかった。 ブックマンの血族に生まれ、世界の全てを見ようと故郷を出、師に付いて世界中を旅した―――― ブックマンの後継者となる以外の将来など、考えたこともない。 なのに今、彼の胸中を覆うのは、漠然とした不安だった。 ―――― バカな・・・・・・。 きり・・・と、唇を噛み、震えそうになる身体を抑えこむ。 ―――― そんな、バカな・・・・・・! 「ラビ?」 俯いた視線の先に、アレンの気遣わしげな顔が現れて、ラビはびくりと顔を上げた。 「どうしました?」 アレンは屈めていた身を起こし、不思議そうに首を傾げる。 「な・・・なんでもないさ! すきっ腹に飲んじまって、ちょっと酔っ払っただけさ!」 いつもの『陽気な笑顔』を作り、ラビはパタパタと手を振った。 「ワインはメシ食った後に飲みなおすか! アレン、どの料理がうまかった?」 殊更にはしゃいだ声をあげて、ラビが料理のテーブルに歩み寄ると、アレンもパタパタと追いかけてくる。 「どれもおいしいに決まってるじゃないですか! でも僕、今日は子羊が最高においしいと思いました!」 「お♪ワインに合いそうさ 温かい肉料理を皿に盛り付け、グラスになみなみと赤ワインを注ぐラビを見つめて、アレンが苦笑した。 「あんまり飲むと、怒られるよー?」 「大丈夫さ! 今日は、ジジィもしこたま飲むだろうし ―――― 大丈夫・・・さ・・・・・・。 楽しげに笑う顔の下で、ラビは、今まで感じたこともない不安を覚えていた。 ―――― 絶対・・・きっと・・・・・・多分・・・・・・・・・。 何よりも、不安を覚える自身に動揺しつつ、表面上は楽しげに談笑する。 ―――― 大丈夫・・・・・・。 今まで通り、師に付いて行けばいい。 笑顔を浮かべながら、ただ、目の前を過ぎゆく『事実』を記録すればいい。 何も疑わず、何も迷わず、ただ、ひたすらに歩めば、いずれブックマンになる・・・なれる・・・・・・なれる、はず・・・・・・・・・。 自身の思わぬ気弱さに、呆然としたラビの手から、グラスが滑り落ちた。 「ラビ?!」 「あ・・・悪ぃ!」 破片を拾おうとする彼を、清掃班の団員が押しとどめ、手早く片付けていく。 その間ラビは、部屋中に飾った人形の『目』が放つ、淡い光に照らされたガラス片をぼんやりと見つめていた。 ―――― 俺は、ブックマンに・・・・・・。 Where is the answer? |