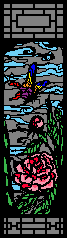いつも通り騒がしい科学班で、いつも通りリーバーは、カリカリとペンを走らせていた。 「おっし!できたぜ!」 ファインダーから報告を受けた情報を分析し、関連資料も完璧に揃えたことを確認して、彼は、自分の席を立った。 が、 「あ?!おい!室長はどこいきゃあがった?!」 科学班内のコムイのデスクから、主が消えている様に、リーバーは目を尖らせて辺りを見回す。 と、 「室長なら、さっき『執務室に帰る』って、出て行きましたよ?」 メンバーの答えに、リーバーは舌打ちしつつも、コムイの執務机に書類を置いた―――― その、常ではありえない、あまりに整然とした机上に、リーバーは息を呑む。 「・・・・・・誰か、アジア出身者!!!」 「はいっ?!」 たまたま科学班に入ってきたメッセンジャーが、リーバーの大声に驚いて振り返った。 「今年の旧暦正月はいつだ?!」 「あ・・ぁ・・・明後日です・・・・・・!」 リーバーの剣幕に、怯えきったメッセンジャーが答えるや、室内が一斉に凍りつく。 「な・・・・・・っ!」 「なんだと――――――――?!」 「チックショ!!道理で神田が、『何でもいいから任務をよこせ』って、出てったはずだよ!!」 「なんでそん時気づかなかったんだよ!あり得ね――――!!!!」 「皆、静まれ――――――――!!!!」 混乱に陥った室内に、再び、リーバーの大音声が響き渡った。 「騒いでる場合じゃねぇ!! 科学班、全員集合!至急、コムイ室長の執務室へ走れ!! あンの外道が重要機密書類を処分しちまう前に、阻止しろ!!!」 「ハイッ!!」 一斉に答えるや、科学班の面々は全員、白衣をはためかせて駆け去る。 「間に合ってくれよ・・・!!」 科学班を最後に出たリーバーは、メンバーとは違う方角―――― 武器庫を目指して、全力疾走していった。 その頃、コムイの執務室では、リー兄妹が、(旧)正月を迎える準備にと、室内の美化にいそしんでいた。 「兄さん、空になったアルコールランプの瓶、なんで捨てないの?」 「忘れちゃうんだよ」 「・・・図書館の本、いつまでここに置いてるの?」 「えー?それ、ボクのじゃなかったっけ?」 「・・・・・・この落書きは捨てていいの?」 「あ、ダメダメ。その端っこに、計算式書いてるでしょ?」 リナリーと二人、執務室の片付けに励むコムイは、そう言って、床に散らばった紙を拾い集める。 と、 「そこを動くなっ!!」 動けば撃つ、と言わんばかりの、殺気立った声に、兄妹は揃って凍りついた。 「よーし!二人とも、そのまま動くなよっ!」 「室長!その手にあるものを渡してもらいましょうか!!」 「・・・・・・ナニ?強盗団ごっこ?」 どやどやと乗り込んできた、白衣の集団に、コムイが呆然とする間に、彼らはコムイやリナリーの手から書類を取り上げ、ゴミ箱をあさり出す。 「やっぱり・・・!室長!今度俺の報告書捨てたら、アンタを焼却処分しますよ!!」 「え?!それ、処理済書類じゃなかったっけ?!」 「昨日出した報告書まで・・・! 室長!アンタ、この部屋出てけ!!ここにあるものに触るな!!」 「リナリーも!妙なお祭気分を起こさず、速やかに自分の部屋に帰れ!!」 「なによ!みんなヒドイ言い方!」 「そうだよ!ここはボクの執務室・・・・・・」 途端、刃のような視線で貫かれ、兄妹はすくみあがった。 「じゃあ、自分の部屋と、実験室の清掃をどうぞ!」 「ここは俺らに任せて!」 「終わるまで絶っっ対に近寄るんじゃねぇぞ?!いいな?!」 科学班メンバー達にまくし立てられながら、ゴミの代わりに部屋から掃き出された兄妹は、激しい音を立てて閉まったドアの前で、しばし呆然とする。 「・・・・・・追い出されちゃったね、兄さん」 「うん・・・・・・・・・」 「仕方ないわ。私、兄さんのお部屋の大掃除をしてあげるから、実験室はがんばってね」 「うん・・・・・・・・・」 妹の言葉に頷いたコムイは、挙動不審気味に辺りを見回した―――― が、生憎、彼の視界の中に、人影はない。 「今年のカモを釣って来るよ」 そう言うと、コムイはふんふん~♪と、鼻歌を歌いつつ、明らかな狙いを持って、食堂方面へと向かった。 「・・・父さん!妖気です!!」 「は?!なに言ってんさ、お前?」 アトランティス大陸がどの辺りに沈んでいるか、という自説を熱心に語っていたラビは、突然、奇妙な言葉を吐いて彼の話を遮ったアレンに、目を丸くして問い返した。 と、 「ラビ!今日はなんだか、いきなり寒くなりましたね!」 アレンは、ラビの問いを無視して、腰を下ろしていたベッドから立ち上がる。 「あ?そうか・・・?でもやっぱり・・・」 いつもと変わらない気がする、と言いかけたラビの口を封じるように、アレンはベッドの上に放り出していた自分のコートを手に取った。 「僕、インドにいたから、英国の冬は厳しくって・・・ところでラビ、身長いくつですっけ?」 「ん?こないだ計った時は177cmだったけど?」 やたらと話を変えるアレンを不思議に思いつつも、ラビは、手にしていたマグカップを、小さなテーブルの上に戻す。 「僕!ここに来てから結構背が伸びたんですよ! ね!今の僕と、どのくらい体格差があるか、比べて見ませんか?!」 言うや、アレンはラビに自分のコートを差し出し、着るように促した。 「このコート、ラビが着てもきつくないようなら、体格同じですよね?!」 「はぁ・・・まぁ、比べてみたいっつーなら別に・・・」 いいけど、と言う前に、アレンはラビを立たせ、自分のコートを着せ掛けた。 「あ!ちゃんとフードも被ってくださいね!」 「はぁ?!フードはあんま、関係ねぇだろ」 「いいから!」 言うと、アレンは背に落ちたフードを引き上げ、ラビの頭に目深に被せる。 「これで、後ろから見たら、僕と間違えられるかもね、ラビ」 にやりと、黒い笑みを浮かべるアレンに、ラビは嫌な予感を覚えた。 「・・・・・・お前、なに考えてんさ?―――― って!なにしてんさ!!」 ラビは、挙動不審なアレンが更に不審さを増し、窓から脱出しようとする様に、目を剥く。 「ちょっと、出てきます」 「どこに?!」 明らかに怪しい様子で窓の外に消えたアレンに驚き、窓辺に駆け寄った彼は、背後からいきなり抱きすくめられて、更に驚いた。 「アレン君、ゲットー!さぁさぁ!今年もボクの実験室の掃除を手伝ってよね!」 「はぁぁぁぁぁぁぁっ?!」 大絶叫して振り向いた少年の、フードの下の顔が違うことに気づいて、コムイも目を丸くする。 「なんと、変り身の術とは!あの子も成長したねぇ・・・・・・」 「なに?!これ、どう言う事さ?!」 「んー・・・はっきり言っちゃってもいい?」 えへ 「こ・・・この事態を解明できるものなら、ぜひとも教えて欲しいさ・・・!」 「人身御供にされたんだよ、キミ」 「俺が?!生贄?!」 ヒドイ!と絶叫するラビの首を、コムイはにっこりと笑って、長い腕で固める。 「ボクはカモと呼んでるけど、いいよ別に、羊でもヤギでもウサギでも」 「あんの・・・腹黒道(ハラグロード)食欲魔王――――!!」 「ホラホラ、泣かないで、生贄のウサギ君。お手伝いしてくれたら、ごほうびにビーカーコーヒーいれてあげるからね♪」 「いらねぇぇ――――!!!!」 「遠慮しないで 「してねぇぇ――――!!!!」 城中に響き渡るような絶叫を上げるラビを、コムイは鼻歌を歌いながら実験室へと連行していった。 「ふぅ・・・危なかった」 自室の窓の下にある生垣に身を潜め、息を殺して中の様子を伺っていたアレンは、コムイがラビを連行したことを確認して、額に浮いた汗を拭う。 「ラビがいてくれてよかったよ。僕一人じゃ、逃げられたかどうか・・・」 後でお礼しなきゃ、と、根本的解決にはなりそうにないことを心中に呟きつつ、アレンは、ほふく前進で自室を離れた。 と、 「なにやってんだ、お前?」 アレンが自室からかなり離れた場所まで至った頃、呆れ果てた声を掛けられて見上げれば、リーバーが鍵束を派手に鳴らしながら、駆け回っている。 「リーバーさんこそ・・・」 ナニ走ってるんですか、と問えば、彼は、大量の鍵をじゃらつかせながら持ち上げた。 「室長に火薬を悪用されないよう、全部の武器庫に鍵を掛けて回ってんだ・・・まぁ、こんな事しても、あの人なら爆竹くらい、簡単に作っちまうんだけどな・・・・・・」 それでも、調子に乗ったコムイに武器庫を爆破されないよう、手を打っておかなければ!と、息巻くリーバーに、アレンは乾いた笑声を上げる。 「僕も・・・実験室の大掃除へ連行されるのを、命からがら逃げてきたところです」 「・・・・・・お互い、苦労するな」 「いえ!リーバーさんに比べたら、僕なんかまだまだ・・・!」 げっそりと、やつれた顔で深く吐息するリーバーに、アレンは慌てて言い募った。 「はは・・・がんばって逃げ切れよ」 「はい。リーバーさんもがんばって」 「おう!」 お互いに激励し合ったのち、アレンが更に本城から遠ざかる道を選んで走っていると、てっきりコムイと同じく、部屋にこもっていると思っていたリナリーが、前方から歩いてくる。 しかも、プライベートで城を出るらしく、黒いロングコートを着て、団服を隠していた。 「あれ?リナリー?!」 お掃除は?と、問うアレンに、リナリーはにこりと笑う。 「兄さんの部屋を見たら、とても今日中には終わりそうになかったから、先に、春節のお買い物に行こうと思って」 「へぇ・・・どこまで?」 「イースト・エンド」 彼女の答えに、アレンは真っ青になって首を振った。 「リナリー!まさか、あんな危ないところに、一人で行くなんて言いませんよね?!」 「危ないかしら?」 「危ないですよ!アヘン窟の集合地じゃないですか!!」 とんでもない!と、絶叫するアレンに、しかし、リナリーは不思議そうに首を傾げる。 「でも、春聯(しゅんれん)を売ってる、清国人の店って、あの辺にしかないのよ」 いかにも、大したことなどない、と言わんばかりのリナリーの口ぶりに、アレンは眉をひそめた。 「何度も一人で行ったことがあるんですか?」 「ううん。いつもは、兄さんとか班長が、無理やりついてくるの」 でも今日は、二人ともいないから、と、平然と言うリナリーに、アレンは深く吐息する。 「僕が通りかかって、本当に良かった・・・。荷物持ちでも何でもしますから、お供させてください」 「え・・・?いいの?」 「いいもなにも・・・リナリー、言っておきますが、あそこは年頃のレディが、一人で行く場所じゃありません!」 「でも私、エクソシストよ?」 いたずらっぽい、上目遣いで笑うリナリーに、しかし、アレンは断固として首を振った。 「エクソシストでも、レディはレディです。 イースト・エンドに行くと知っていながらお供しなかったなんて、僕の沽券にかかわります」 「じゃあ・・・荷物持ちを手伝ってくれる?」 「喜んで」 口ではしかつめらしいことを言いつつも、内心は嬉しくてたまらない気持ちを抑えて、アレンは、リナリーと一緒に城外へ出て行った。 ―――― 一方、そうとは知らないリーバーは、全武器庫の施錠を終えた後、リナリーが一人で春節の買い物に行ったと聞いて、絶叫した。 「なんっで一人で行かせたんだ!エクソシストとはいえ、まだ子供だぞ?!」 「だって・・・!まさか、イースト・エンドに行くなんて知らなかったんですよぉ!」 リーバーの剣幕に、身を縮めた科学班メンバーの傍らで、彼以上にぶるぶると震えながら、ミランダが顔を覆う。 「ごごごごご・・・ごめんなさい、リーバーさん!! リ・・・リナリーちゃんが買い物に行くって聞いたの、わ・・・私なんです! わゎっ・・・私っ・・・イースト・エンドが、あ・・・危ない場所だって・・・ししし・・・知らなくてっ・・・・・・!!」 「えっ?!イヤ、あのっ・・・!!」 まさか、リナリーを見送ったのがミランダだとは思わず、つい、怒声を上げてしまったリーバーは、慌てふためいた。 と、 「あ!班長がミランダさん泣かしてる!!」 「ひっでぇ!ミランダさん、ロンドンに不慣れなのに!」 「鬼班長だ!」 「バカッ!黙ってろ、お前ら!!」 メンバー達に、口々に非難され、リーバーが更に怒声を高めると、自分に向けられたと思ったのか、ミランダが泣き崩れる。 「本当にごめんなさいっ!!」 「ちちっ・・・違います!ミランダさんに言ったんじゃなくて・・・!! っておい!リナリーはいつ出てったんだ?!」 ミランダを気にしつつも、リナリーの身をも気にかけて問えば、 「ついさっきです!」 と、素早く回答が返った。 「じゃあ、まだ間に合うかも知れねぇ!城門前に馬車回せ!!」 白衣を脱ぎ捨てながら、リーバーが門番への回線を開き、命じると、 「わ・・・私も行かせてください、リーバーさん!」 と、ミランダが申し出る。 「え?!ミランダさん、イースト・エンドっすよ?!」 危ない場所なのだ、と、ひき止めようとするリーバーに、しかし、ミランダは断固として首を振った。 「私の責任です!リナリーちゃんを無事に連れ戻さないと!!」 「・・・わかりました。じゃあ、急いで!」 「はい!」 ここで説得する時間はない、と、リーバーが部屋を飛び出すと、ミランダも後に続く。 二人は城門前に到着するや、馬車に飛び乗り、御者を急かしてリナリーを追った。 「ここでいいわ。降ろして」 リナリーは、イースト・エンドにはもう少々距離のある場所で御者に言うと、教団の紋章の入った馬車を降りた。 「リナリー、なんでここで降りるんですか?」 もっと先まで行けばいいのに、と言うアレンに、しかし、リナリーは首を振る。 「アレン君も、教団の紋章で人の態度が変わる事は知ってるでしょ? ヴァチカン直属だって印は、便利な時もあるけど、不便なこともあるよ」 特にこういう所では、と言うリナリーに、アレンも納得して頷いた。 「確かに、面倒なことになりそうですね」 それでなくとも、身なりのいい二人は、昼の貧民街では浮くに違いない。 「お店までの、正確な道はわかりますか?買い物を済ませたら、すぐに戻りますよ?」 「うん、わかってる」 「絶対に、僕の側を離れないでくださいね」 「それは私のセリフ・・・・・・」 苦笑しつつ、リナリーは、アレンの腕を取った。 「こうしてましょ。離れないように」 「ぜ・・・絶対、手を離さないでくださいね!」 照れながら、アレンは歩を踏み出したリナリーに付き従った。 「おい!止めろ!!」 イースト・エンドに至る前に、教団の紋章がついた馬車を見つけたリーバーは、御者に命じて止めさせるや、馬車から飛び出てその御者に駆け寄った。 「科学班班長のウェンハムだ!この馬車、リナリーを乗せて来たものか?!」 駆け寄ってきた青年にいきなり詰め寄られ、御者は、驚きながらも頷く。 「どっちに行った?!」 「イ・・・イースト・エンドの街の中へ・・・・・・」 リーバーの剣幕に、どもりつつ言って、リナリーの立ち去った方向を示した御者に、彼は礼を言って、ミランダを呼び寄せた。 「ミランダさん!まだ近くにいるかも!!」 「はっ・・はいっ!!」 リーバーに続いて馬車を出てきたミランダは、慌てて彼に駆け寄る。 と、 「絶対、はぐれないで!」 リーバーの、大きな手で手を掴まれて、慌てふためいたミランダの足が、たたらを踏んだ。 「リリリリ・・・リーバーさん!!」 「手を離さないでくださいよ!」 厳しい声音で言われて、ミランダは、こんな状況にありながら・・・とは思いつつも、嬉しさに顔を赤らめて頷く。 ―――― が、しばらく行く内に、ミランダは、リーバーがこんなにも焦っていた理由を理解した。 異臭と汚物にまみれた、汚らしい街路に、今にも崩れそうな家並み・・・。 まだ昼間だと言うのに、道端には酒やアヘンに酔い痴れた者達が転がり、生気の失せた目を宙に漂わせている。 ミランダは、その異様な恐ろしさに、リーバーとつないだ手に力を込めた。 と、彼女を安心させるように、強く握り返され、ミランダは、厳しい顔を前方に向けるリーバーを、不安げに見上げる。 「リーバーさん・・・私・・・本当になんてことを・・・・・・!」 リナリーのように、若く可愛らしい少女を、一人でこんな場所に行かせるなんて、知らなかったでは済まされない。 カタカタと、細かく震えだした彼女を見下ろし、リーバーは安心させるように微笑を浮かべた。 「大丈夫。あいつは子供だが、エクソシストです。酔っ払い相手に負けはしませんよ―――― けど、こんなに心配させやがって・・・! 早く捕まえて、厳しく説教してやりましょう」 「はい・・・!」 リーバーの言葉に、やや気が軽くなったミランダは、深く頷いて、真摯な目を辺りに巡らせた。 一方、リナリーと腕を組んで、イースト・エンドの街を歩くアレンは、アクマの気配を探るように、油断なく辺りに気を配っていた。 と、 「あ!ここよ、アレン君!」 正月用なのだろう、派手な飾り物がたくさん下がった店の前で、リナリーが立ち止まる。 が、そのすぐ近くには、アヘン窟らしき店も多くあった。 「リナリー、早く店に入って」 いかにも怪しい目で、リナリーを見る住民達から、彼女の姿を隠しつつ、アレンは先に彼女を入らせる。 「どれにしようかなー♪あ!提灯も新調しちゃおうかな 楽しそうに狭い店内を見て回るリナリーに、アレンは、忠実な猟犬のように付き従った―――― 店員や客達の、二人を見る目が怪しいのは、決して気のせいではない。 「リナリー・・・絶対、離れないで」 決して腕を放そうとしないアレンに、リナリーは狭い店内で動きにくそうではあったが、苦笑して頷いた。 「あ!アレン君、コウモリの春聨見つけたよ!ね!金魚とどっちがいい?」 「幸せになれそうな方」 いやに真面目に答えた彼に、リナリーが弾けるように笑い出す。 「じゃあ、コウモリね!いい?ちゃんと、逆さに貼るのよ?」 「うん」 にこりと、アレンが笑って頷いた時だった。 「そんなの、英国人にわかるわけがないさ、小姐(シャオチェ)」 訛りのきつい英語で話しかけられ、見遣ると、清国人らしい男が数人、店内の狭い道を塞ぐように立っている。 「・・・道をあけてくれませんか?」 「あぁ、いいよ。帰りたきゃ帰んな、あんただけな」 ぐいっ、と、アレンの腕を引き、リナリーと引き離そうとした男は、しかし、アレンに無造作に振り払われ、紙の春聨を押しつぶしながら石の床に叩きつけられた。 「てめ・・・!!」 「怪我をしたくないなら、おとなしくしていてください」 少年とは思えない、鋭い目で見下ろされた男は、石の床に尻をついたまま、硬直する。 「リナリー、ここ以外に春聨を売っている店は?」 「う・・・うん、あるけど・・・・・・」 アレンに腕を引かれ、店の外に連れ出されようとするリナリーを、しかし、他の男たちが執拗に追いかけてきた。 「待て!!」 「女を置いていけ!!」 その言葉に、アレンはリナリーを背にかばい、まなじりを吊り上げて振り返る。 「ふざけろ!お前たちなんかに渡すもんか!」 アレンの啖呵に、男達は更にいきり立った。 「ガキが!!」 「ガキでも男だよ」 言うや、アレンは殴りかかって来た男達に、次々と蹴りを喰らわせては、床に沈める。 「リナリー!早く!」 アレンは、そう言ってリナリーの腕を引いた。 少年とはいえ、エクソシストの攻撃をまともに受けては、大の男でもすぐに立ち直ることはできないだろうが、新手にまた道を塞がれないとも限らない。 急かすアレンに、しかし、リナリーは『ちょっと待って!』と、手近にあった春聨を一抱え、取り上げた。 「お金はここに置いておくから!足りない分はまけてねー!じゃあ、また来年!良いお年を!」 アレンが、思わず脱力するようなセリフを店内の店主に掛けて、リナリーはアレンの側につく。 「えへへ どこか自慢げなリナリーに、更に脱力して、アレンは彼女が手にした春聨を持ってやった。 「来年って・・・またここに来るんですか?!」 「もちろん。だってここが一番近いし、品揃えもいいんだもん」 「でも・・・・・・」 眉をひそめるアレンに、リナリーはクスクスと、明るい笑声を上げる。 「足技は私の専売特許かと思ってたけど、アレン君も中々のものね」 「・・・人間相手に、左腕を使うわけには行かないでしょ」 からかわないで、と、苦笑するアレンに、リナリーは更に笑声を上げた。 「お前たちなんかに渡すもんか!って、カッコよかったよ 「え?そんなことはないでしょう?!」 冗談ではなく、本気で喜んでいるらしいリナリーに、アレンは驚いて目を見開く。 が、リナリーは彼の傍らで、ふるふると首を振った。 「ホントだよ。みんな、私のことは子ども扱いで、レディって言ってくれたの、アレン君が初めてだもん。 あ、ジェリーにはよく、『もうレディなんだから、きちんとなさい!』って怒られるけど、それってレディ扱いじゃないじゃない?」 「そ・・・そうですね・・・・・・」 「戦場では、エクソシストとしてしか扱われないし、私、そんなに女としての魅力がないのかなぁって、時々、落ち込んじゃうんだ」 「そ・・・そうですか・・・・・・」 リナリーの話を聞く内に、アレンは、その裏のからくりに気づいて、背中に冷たい汗をかく。 ―――― つまり、リナリーに魅力を感じた男は全員、闇に葬られたってこと・・・?! 最悪の確信に、アレンは頭を抱えたものの、 「どうしたの?」 と、大きな目を見開いて、彼の顔を覗き込むリナリーに、顔を赤らめた。 ―――― 無理!これで意識しないなんて、絶対無理!! 「アレン君?」 不思議そうに、小首を傾げるリナリーに、アレンは息を詰まらせる。 「さっきから青くなったり赤くなったり・・・具合でも悪いの?」 「いえ!なんでも・・・!強いて言えば、寒いかな?!部屋にコート置いて来ちゃったし!!」 慌てて適当なことをまくし立てると、リナリーは、見開いた目を和ませて頷いた。 「ごめんね。急につきあわせちゃったもんね。お礼に、アフタヌーンティをご馳走するわ」 「そっ・・・そうですね!は・・・早く馬車に戻りましょう!」 「そう!そして、そのまま教団へ戻れ!!」 突然、厳しい声で怒鳴られ、アレンとリナリーは、驚いて声の方向を見遣る。 と、彼らの視線の先で、リーバーが、仁王立ちに立っていた。 「あら?どうしたの、リーバー班長?」 無邪気に微笑みかけたリナリーに、しかし、リーバーは厳しい顔つきのまま、無言で歩み寄ると、容赦ない力で彼女の頭を叩く。 「いったぁっ!!なにすんの!!」 「なにすんの、じゃねぇ!!」 アヘンに酔い痴れた者達までもが目を覚ますほどの、大音声で怒鳴りつけ、リーバーはリナリーを見下ろした。 「子供が一人で来る場所じゃねぇだろ!!」 「こ・・・子供って!ひどいわ!!」 「じゃあ、こんな分別のない事するやつが、一人前のレディだとでも言うのか!!」 厳しく叱りつけられて、リナリーは俯いた目に、涙を浮かべる。 「あ・・・あの・・・リーバーさん・・・そんなに怒らないで・・・・・・」 リーバーの剣幕に、傍らで見守っていたミランダが、おろおろとしながらも、控え目に口を出した。 「リ・・・リナリーちゃんも、泣かないで・・・ね・・・? リーバーさんね、ホントにリナリーちゃんのこと、心配してたのよ?」 「し・・・心配なんかされなくっても・・・大丈夫だもん・・・!!」 涙をこらえているせいか、やや震えている声に、リーバーの目が更に吊り上がる。 「子供のクセに生意気言うんじゃない!!」 「子供じゃないもん!!もう、一人前のエクソシストだもん!!」 「背は伸びても頭ン中は子供だって言ってんだ!!」 「ちょ・・・っ!!リーバーさん!!リナリーも、落ち着いて!!」 町中で、辺り構わず怒鳴り合う二人の間に、アレンが慌てて飛び込んだ。 「リーバーさん!急だったもんで、報告しなくてごめんなさい!でも、ちゃんと僕がついてましたから!」 「アレン・・・正直に言え。絶対、なんかあったろ?」 「え・・・・・・」 リーバーに問われ、気まずげに泳いだ視線が、全てを語ってしまう。 「リナリー・・・今回は、アレンがついてきてくれたからよかったものの、一人で来るには危ない場所だって、わかったろ? もう二度と・・・」 「ダーク・ブーツがあるもん・・・・・・」 「まだ言うか!!」 「ちょっ・・・!!やめてくださいってば!!」 強情なリナリーに、再び手を上げようとするリーバーにミランダが慌てて取りすがった。 「ここじゃなんですから!場所かえましょ!!」 アレンも、いきり立つリーバーと駄々をこねるリナリーを必死になだめ、馬車に戻ることを合意させる。 が、馬車に戻っても、険悪な空気は、決して和らぐことはなかった。 1台を空のまま教団に帰し、4人が同乗した馬車の中で、アレンとミランダは、それぞれ、ふてくされたリナリーと憤然とするリーバーの傍ら、身を固くするしかない。 が、馬車が川に差し掛かった時、 「渡らないで。ピカデリー・サーカスに行きたいの!」 そう、御者に命じたリナリーに、ぴくりと、リーバーの眉が吊り上がった。 「何しに?」 「アフタヌーン・ティーの時間だわ」 「教団でもできるだろ」 「やだ。せっかくロンドンに来たんだもの。フォートナム&メイソンでお茶買うんだもん」 「お前な・・・!」 「わゎっ!!リーバーさん!落ち着いて!!」 「そっ!!そうよね!せっかくロンドンに来たんだから、お茶くらいしたいわよね?!」 アレンとミランダが、同時に二人の間に入り、狭い車内であわや大喧嘩になりそうだった二人を止める。 「・・・茶っ葉買ったら、すぐ帰るぞ」 「ふんっ!」 「リナリーちゃん!」 「お返事は『はい』でしょぉっ?!」 これ以上刺激しないで!と、ミランダとアレンが、悲鳴じみた声を上げて、リナリーに懇願した。 が、彼女は強情にも折れようとはせず、店に至るや、真っ先に馬車を出て、店内に入って行く。 「リナ・・・!」 「リーバーさん!!僕がお供しますから!」 追いかけようとするリーバーをおしとどめ、アレンがリナリーの後を追った。 更には、傍らのミランダにそっと袖を引かれ、浮かしていた腰を下ろす。 「いきなり手を出すのは、いけませんよ」 そっと、控え目に囁かれた言葉に、しかし、リーバーは不満げに眉を寄せた。 「でも・・・」 「リナリーちゃんが、あんなに反抗的になったのは、単に叱られたからじゃありません。 男の子の前で、子供扱いされたからですよ」 「は?!」 ミランダの言葉は、リーバーにとって、よほど意外だったのだろう。 思わず、大きな声を上げた彼に、ミランダは、困ったような笑みを浮かべた。 「年頃の女の子・・・いえ、レディに、恥をかかせちゃいけませんよ」 「レディって、まだあいつは・・・」 「レディですよ、リーバーさん。アレン君は彼女を、ちゃんとレディとして扱っています。 その彼の前で、あなたは彼女を、子供扱いしたんです。リナリーちゃんが怒るのも、当然ですよ」 「・・・・・・・・・・・・」 目を丸くして、声を失ったリーバーに、ミランダはクスリと笑みを漏らした。 「待っている間、私達も、お茶しませんか?」 「は・・・?えぇ・・・」 「すみません、ちょっと、待っててくださいね」 リーバーが頷くと、ミランダはそう、御者に声を掛けて、リーバーと共に馬車を出た。 「ちょっとは落ち着きましたか?」 ポットの紅茶を、カップに注いでやりながらアレンが問うと、リナリーは、軽く吐息して頷く。 「リーバーさんは、心配して来てくれたんですから、あんなに怒っちゃ・・・」 「わかってるけど!」 憤然としつつ、リナリーはカップにたっぷりとミルクを入れ、飲み頃に冷えたお茶を一口飲んだ。 「新参者の僕が言うのもなんですけど、リーバーさんはコムイさんに近い人だから、リナリーを妹みたいに見ちゃうんじゃないですか?」 「そうね・・・」 「僕には親も兄弟もいないから、よくはわからないですけど、親にとって、子供はいつまでも子供で、兄弟もそういうもんなんでしょ?」 「そうね・・・・・・」 途端、リナリーが吹き出して、次の言葉を一所懸命考えていたアレンは、目を丸くする。 「ゴメン・・・だって、アレン君があんまり一所懸命、班長をかばうから・・・!」 こらえかねたように、クスクスと笑声を上げるリナリーに、アレンも苦笑を浮かべた。 「だって、リーバさん、いい人ですよ?気が置けない、お兄さんって感じで」 僕は好きです、と、笑うアレンに、リナリーも微笑んで頷く。 「・・・わかった。馬車に戻ったら、ちゃんと謝るわ」 「はい。年に一度の、お正月なんでしょ?気分よく迎えましょ」 「うん・・・って、アレン君まで私にお説教してるわ」 「え?そ・・・そうかな・・・?」 「もう!私、年上なんだからね!」 ぷぅ、と、頬を膨らませたリナリーに、アレンは思わず吹き出した。 「ちょっと!アレン君?!」 「ゴ・・・ゴメ・・・!!」 リナリーが、抗議の声を上げるが、アレンの笑いはなかなかおさまらない。 ―――― やっぱり可愛い・・・。 彼女の兄の恐ろしさを、十分知りつつも、アレンは、その思いをごまかすことは出来そうになかった。 一方、リーバーとミランダは、ピカデリー・サーカス内のコーヒー・ハウスで、時間を潰していた。 「・・・もう、怒ってませんから」 両手で持ったカップの向こうから、じっと、困惑げな目で自分を見つめるミランダに、リーバーは深々と吐息する。 「・・・怒っていないのは、わかっていますよ」 そう言って、同じ姿勢のまま、視線を外さないミランダから、リーバーは気まずげに視線をそらした。 「でも・・・俺が謝るのも変でしょ」 更に言えば、いきなりレディとして扱うのも気恥ずかしいと言う彼に、ミランダは、吐息するようにカップに息を吹きかける。 「女性が少ない場所ですから、リナリーちゃんの扱い方に困るのはわかります。 特にリーバーさんにとっては、妹のようなものでしょうから・・・」 「そうなんすよー・・・!妹っつーか、むしろ娘・・・?」 まだ26なのに!と、リーバーは絶望的な声を上げて、眉間に深い皺を刻んだ。 そんな彼に、クスリと笑みを漏らして、ミランダはカップをソーサーに戻す。 「・・・犬と子供は、ドイツ人に育てさせろ、なんて言葉があるでしょう?」 「え?・・・あぁ・・・」 よく聞く言葉に、リーバーはミランダに視線を戻して苦笑した。 「ミランダさんも、厳しくしつけられたクチっすか?」 子供を鞭で叩くって、ホント?と、こわごわと問う彼に、ミランダは笑声を上げる。 「我が家では、鞭は使いませんでしたけど、子供は厳格に躾けられます。 もちろん、厳しいだけではなく、たくさんの愛情も一緒に注いでくれますけど・・・」 細い指を組み合わせ、ミランダは小首を傾げた。 「名詞に性別のあるドイツ語ですが、kind(子供)には性別がありませんよね・・・。 そんな、中性の者をきちんと男女に分けるため、子供は小さな大人として扱われます―――― 女の子は、リナリーちゃんよりずっと小さな頃から、一人前のレディとして扱われるんですよ」 だから・・・と、ミランダは湯気の収まったカップを、再び取り上げる。 「16歳のリナリーちゃんは、子供ではなく、一人前のレディです。そして、周りがレディとして扱わない限り、『子供』はいつまでもレディにはなりません」 静かに言い終えて、コーヒーを飲むミランダに、リーバーは感心したように頷いた。 「ミランダさん、もしかして、俺にわかりやすいように言い換えてくれたんすか?」 科学者であり、言語学者でもあるリーバーには、わかりにくい『オンナノコの気持ち』などより、言語構造や児童の発達心理の話の方が、はるかにわかりやすい。 そう言うと、ミランダは、クスクスと、明るい笑声を上げた。 「だって、リナリーちゃんが怒った理由を話した時、リーバーさんたら『なにを言われてるのか、全然わからない』って顔をするんですもの。どう言ったらわかってもらえるのか、ものすごく考えたんですよ」 でも・・・と、ミランダはほっと吐息する。 「うまく説明できたみたいでよかった。私も少しは、慣れてきたみたいです」 「へ?」 何に?という、リーバーの問いには、しかし、赤らんだ顔を俯けたまま、答えられなかった。 ・・・どうすれば彼と会話のレベルを合わせられるか、いつも必死に考えている、なんて事は、恥ずかしくてとても言えない。 が、リーバーは、彼女から答えが得られそうもないとわかると、早くも関心が移ったようだった。 「未分化の人間を分化する、かぁ・・・・・・」 コーヒーに視線を落としたまま、ぶつぶつと呟く彼を、ミランダは上目遣いに、そっと見遣る。 「そう考えれば、子育ても悪くないっすね!」 パッと、楽しそうな笑みを浮かべて顔を上げたリーバーと目が合って、ミランダはますます顔を赤らめた。 「・・・・・・・・・あ」 自身の吐いた言葉の意味に気づいたか、リーバーはそう呟いたまま硬直し、茹で上がったように赤い顔を向かい合わせた二人は、周りの客達が奇異の視線を送ってしまうほど長い間、硬直していた。 その後、待たせていた馬車の前で、4人は合流した。 「・・・・・・はんちょーゴメンナサイ。これ、お詫びデス」 詫びの言葉を、恐ろしいほどの棒読みで読み上げると、リナリーは馬車の前に立っていたリーバーに頭を下げ、手にした紅茶を一袋、差し出す。 「どういたしまして、レディ」 対するリーバーも、寒気がするほど丁寧な口調で応じ、馬車のドアを開けて、リナリーに手を差し出した。 「オ足元にオ気をつけテ、レディ」 「寒い・・・っ!外気以上に空気が寒いっ!!」 二人の会話に、心底怯えるアレンに、ミランダが苦笑を浮かべる。 「だ・・・大丈夫よ、アレン君!二人とも、仲直りする気なんだから・・・」 あなたも説得してくれたんでしょ?と、耳元に囁かれ、アレンは、深く頷いた。 「納得はしてくれたと思います・・・けど・・・・・・」 まだギクシャクしている雰囲気に、アレンとミランダは目を合わせ、深く吐息する。 「まぁ・・・遅くても、明日には仲直りしていますよ」 「そ・・・そうかしら・・・?」 私の説得の仕方が悪かったのかも!と、ミランダまでもが深く沈んでいきそうな状況に、アレンはぎょっと目を剥いた。 教団までの道のり、重く沈んだ3人に取り囲まれるのは辛すぎる。 一瞬で状況を判断したアレンは、慌ててミランダに言い募った。 「ミランダさんが説得してくれたから、リーバーさんもあれだけ態度を軟化させたんじゃないですか!ミランダさんのおかげですよっ!!」 「でも・・・・・・」 「大丈夫です!二人とも、長い付き合いなんですから!」 ね?!と、妙に確信ありげに断言され、ミランダは押し切られて頷く。 「さぁ!早く帰りましょ!帰ったらやること、たくさんあるんですから!」 「え・・・えぇ・・・・・・」 アレンはミランダを急かして馬車に乗せると、続いて乗り込もうとしたリーバーの袖を引き、素早く囁いた。 「いきなりは不自然です。今日はいつも通りで」 と、リーバーは目をしばたたかせ―――― 吹き出して、その大きな手で、アレンの頭をくしゃりと撫でた。 「そうだな・・・!」 ミランダに言われて、リナリーをレディ扱いするよう、心がけてみたものの―――― アレンの言う通り、今まで妹か娘のように思っていた相手を、いきなりレディとして扱うことには気恥ずかしさが先んずる。 「自然にどうぞ」 「サンキュ」 10歳以上も年下のアレンに諭された照れもあって、リーバーはアレンの頭を、殊更にくしゃくしゃにしてやった。 しかし、そのおかげもあってか、帰りの道では、とげとげしかった雰囲気も和らぎ、馬車は、無事に教団の城門をくぐった。 その夜・・・既に、日付も替わった頃。 「ラービー?今日はゴメンね えへ 「ごめーん!怒ってる?」 アレンはベッドの傍らにしゃがみこみ、背を向けたまま、無言のラビに、苦笑する。 「だけど、コムイさんの実験室の掃除を体験してわかったでしょ?あれを一度経験すると、なんとしても逃げ出したくなるこの気持ち!」 「・・・・・・」 「来年は、一緒に逃げましょーね 「・・・・・・・・・・・・」 「ラービー?」 「うるさいさ、裏切り者!!」 耳元で、しつこく呼びかけるアレンに、とうとうラビが絶叫した。 「俺が怒ってんのは!コムイの手伝いを押し付けられたことじゃなくて、お前が俺を売ったことさ!!」 「売っただなんて、やだなー。ラビを置いて、逃げただけですよ」 「俺を身代わりにしたくせに!!」 くるん、と、寝返りを打てば、ラビの目の前に、アレンの笑顔がある。 「なに笑ってんさ!」 「なに泣いてんですか」 「これが泣かずにいられるか、鬼畜!!」 くすり、と、笑みを漏らしたアレンに、ラビは更に激昂した。 「もーイヤさ!!お前なんかダチじゃねぇ!!」 「まぁまぁ、そんなに怒んないで」 「これが怒らずにいられるか!!」 そう言って、またくるりと背を向けたラビに、アレンは苦笑する。 「ねぇ、ゴメンってば。お詫びに、フォートナム&メイソンで、いいもの買って来たから」 「茶っぱなんかいらないさ!」 背を向けたまま、憤然と言うラビに、アレンは首を振った。 「お茶っぱじゃないですよ。ワインです」 途端、ピクリと、ラビが反応する。 「おつまみになるものも買ってきましたよ?」 くるん・・・と、再び向き直ったラビの眉間は、未だに深く皺が寄っていたが、アレンはもう一押し、と、笑みを深めた。 「もちろん、ブックマンには内緒です」 「・・・・・・・・・・・・ちぇっ」 その一言に、ラビは舌打ちして起き上がる。 「いっとくけど!これで全部許したわけじゃないさ!」 アレンの手から、ワインボトルとチーズを奪い取り、憮然と言うラビに、アレンはもう一度、『ゴメン』と、笑った。 「お詫びに、もう一ついいこと教えてあげますよ・・・・・・明日、なるだけ部屋の外に出ない方がいいですよ」 「・・・なんでさ?」 不意に、声を潜めたアレンに不穏な気配を感じ取り、ラビが眉をひそめる。 「リーバーさんが先手を打ってましたけど・・・ヘタすれば、武器庫が爆破されます」 「はぁっ?!」 何が起こんの?!と、絶叫するラビに、アレンは、昨年の恐怖を、最初から最後まで、事細かに語って聞かせた。 「そ・・・そんなことが・・・・・・!」 「清国では、平和なお祭りなのかもしれませんが・・・ここでは恐怖以外のなにものでもありません・・・・・・!」 「辺り構わず爆竹を鳴らす行為が、平和だと本気で思ってるんさ?」 その問いには、無言で返答を避けたアレンに、ラビも深く吐息して頷く。 「ラジャ。 明日はなるだけ、コムイに近づかないようにするさ」 「そうしてください」 そう言って、自室に戻ったアレンの準備は、万端整っていた。 明日は、食堂にも顔を出さなくて済むよう、部屋には大量の食糧を確保している。 更には、外から爆竹が投げ込まれないとも限らないので、窓を塞ぎ、ドアには何重にも鍵を掛けた。 「明日一日、耐え凌げば・・・・・・!」 まるで、篭城する城主のような面持ちで、アレンは左手の十字架に祈る。 「どうか、無事に過せますように・・・・・・!」 その姿は、他国の風習とはいえ、新年を迎える日とは思えないほど、悲壮感に満ちていた。 そして翌日、旧暦大晦日。 「ねぇ、今日はアレンちゃんの顔を見てないんだけど、任務に行っちゃったの?」 ランチタイムも過ぎ、客のはけた食堂の厨房で、器用に餃子の皮にあんを包みつつ、ジェリーが問うと、なぜか、彼女と一緒に餃子を作っているコムイが、ふるふると首を振った。 「今、任務に行ってるのは神田君だけだよ。それも、別にエクソシストが行くような任務じゃないのに」 仕事熱心だねぇ、と、へらへら笑いながら、彼も器用に餃子を包んでいく。 どころか、包み終わった餃子に、ゴマを乗せて、なにやら細工までしていた。 「ホラホラ、見てごらん、リナリー♪シロクマ 「わぁっ 兄の掌に乗った、白いクマの顔に、同じく餃子を作っていたリナリーが、目を輝かせる。 「こっちは白ウサギー♪」 「きゃあ 「そして、白ペンギンっ!!」 「かわいいー!!」 「・・・いないでしょ、白ペンギンは」 仲睦まじい兄妹に苦笑しつつ、ジェリーは立ち上がった。 「あれ?どうしたの?」 まだ終わってないよ、と、餃子の皮を示すコムイに、ジェリーは眉をひそめる。 「アレンちゃんが食堂に来ないなんて一大事を、ほっとくわけには行かないでしょ!ちょっと見てくるわ」 「1日くらい食べなくったって、死にゃしないよ」 「あの子は死ぬでしょ!」 びしりと言って、ジェリーは厨房を出て行った。 途端、 「あ!忘れてた!」 がたんっ!と、リナリーも椅子を蹴って立ち上がる。 「なにを?」 掌の上で、白鳥を作っていたコムイが首を傾げると、リナリーは粉まみれになった手を洗いながら、やや慌てた口調で答えた。 「アレン君に、コウモリの春聨あげるつもりだったのに、忘れてたの!早く飾ってもらわないと、新年が来ちゃうわ!」 「なんでアレン君に?」 あげても意味わかんないでしょ、と、不思議そうに問う兄に、リナリーはにっこりと微笑む。 「大丈夫よ。春聨を買いに行った時、一緒に選んだんだもん」 「一緒に・・・って!リナリー!リーバー君と一緒に行ったんじゃなかったのかい?!」 「最初は一人で行こうと思ってたんだけど、門の近くでアレン君に会って、一緒に行ったの。班長は、後から追いかけてきたのよ」 「なんっ・・・・・・!!」 そう言ったきり声を失って、顔を紫色にした兄に、リーバーの態度を思い出して、リナリーはぺこりと頭を下げた。 「ごめんなさい。もう、一人でイースト・エンドに行こうなんて、思わないから」 先に謝って、兄の怒りを和らげようとしたリナリーだったが、生憎、彼の怒りのベクトルは、彼女の予想とは別の方向を向いている。 「何もなかっただろうね?!」 「え・・・」 答えに窮して、視線を泳がせるリナリーの態度に、コムイの掌の中の白鳥が、無残に握り潰された。 「・・・春聯を取っておいで、リナリー。お兄ちゃんからも、キミに付き添ってくれたアレン君に、お礼をしなきゃね」 不気味な容に歪んだ唇に、悪い予感がしないわけではなったが・・・・・・リナリーは頷いて、部屋に春聯を取りに戻った。 その頃、アレンの部屋の前で、ジェリーは、懸命に中に話しかけていた。 「アレンちゃん、体の具合でも悪いの?大丈夫?お腹すいてるんじゃないの?」 出てらっしゃい、と、呼びかけると、ドア越しに、アレンの声が答えた。 「心配掛けてごめんなさい、ジェリーさん。体の具合が悪いんじゃないんです・・・ただ、今日、大晦日なんでしょ?コムイさんが怖くて、部屋から出られないんです」 「あ・・・そういえばアレンちゃん、去年、ヒドイ目に遭ったんだったわね」 「ハイ・・・」 悄然とした返事に、ジェリーは苦笑を深める。 「じゃあ、無理に出てきなさいとは言わないけど、お腹空いてないの?」 「それは、昨日のうちに食糧を確保しました」 「そう。じゃあ明日、コムイが爆竹を全部、使い果たしちゃったら、出てきなさいね」 「ハイ」 アレンの返事に、満足げに頷くと、ジェリーは彼の部屋を後にした―――― その直後、リー兄妹が、まるでタイミングを見計らったかのようにやってきた。 「アレン君、いるんでしょ?」 ドアをノックして、リナリーが呼びかけると、返事がある。 「ごめんね、アレン君。昨日、一緒に選んだ春聯を、あげるの忘れてたね。開けてくれる?」 「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・え?」 ものすごい間の後に発せられた、困惑げな声に、リナリーはドアの外で首を傾げた。 「どうしたの?体の具合でも悪い?」 「えーっと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」 はっきりしない返答に、リナリーは不安げな目で、傍らの兄を見上げる。 「体の具合が悪いなら、兄さんに診てもらう?」 何の悪気もなく発せられたその一言に、しかし、アレンは慌てふためいた。 「ちょっ・・・!!早まらないで、リナリー!!僕は元気で、どこも悪いところはありません!!」 「え・・・でも・・・・・・」 「しゅ・・・春聯なら、ドアの外に置いておいてもらえれば、後で・・・・・・」 「あら!ダメよ!春聯は今日飾らないと!」 効果がないよ、と、ドア越しに声を掛けられ、アレンは、仕方なく、いくつもの鍵を外し始める。 その間に、挙動不審にドアの脇の壁に貼り付いた兄を、訝しげに見ながら、リナリーは、ドアが開くのを待った。 「・・・・・・お待たせしました」 「・・・・・・・・・・・・ホントに」 一体、いくつ鍵をつけていたの、と、大きな目を見開いて問うリナリーに、アレンは乾いた笑声を上げる。 「ハイ!これ、コウモリの春聯ね!逆さにして貼ってね」 「はい・・・・・・これ貼ると、幸せが来るかなぁ・・・・・・」 妙にしみじみと呟くアレンに、リナリーはにっこりと微笑んだ。 「もちろんよ!後で、お正月用の餃子を持ってくるから、食べてね!」 「は・・・はい・・・・・・」 かなり警戒気味な返答に、リナリーは意味を取り違えたようで、眉を吊り上げる。 「大丈夫よ!具はジェリーが作ったんだから、味は悪くないはずだわ!」 「あ!いえ!そうじゃなくて!!」 慌てて手を振り、アレンはリナリーの勘違いを訂正した。 「もうそろそろ、コムイさんの爆竹が鳴り出すんじゃないかなぁって・・・・・・」 「あぁ、そのこと・・・・・・」 と、リナリーが、ドアの脇に貼り付いた兄に目をやった―――― 途端。 「It's show time!」 ニヤリ、と、口元を歪めたコムイが、どこに隠し持っていたものか、大量の爆竹を取り出し、火をつけてアレンの部屋に放り込んだ。 「ぎゃあああああああああああ!!!!」 爆竹の破裂音と、アレンの絶叫が石造りの廊下中に響き渡り、悲壮なハーモニーを奏でる。 「兄さん!!」 何てことするの!と、アレンを部屋から引きずり出そうとしたリナリーの前で、しかし、そのドアは閉ざされた。 「今はまだ危ないから、入っちゃいけないよ、リナリー」 「って!兄さん!!アレン君が閉じ込められてるのに!!」 「閉じ込めたんだよーん♪」 言いつつ、コムイはドアが簡単には開かないよう、ノブにぐるぐると布を巻きつける。 その上に、更に爆竹を巻きつけ、点火した。 「なにしてるの?!」 「何って、熱伝導で、向こうからドアノブに触れないようにしてるんだよ。これでもう、アレン君は逃げようと思っても、ドアノブは熱くて触れない」 「ちょ・・・どうしてそこまでやるの!!」 「楽しいじゃない」 悪魔の形相でさらりと言うと、コムイは、ドア越しに聞こえる悲鳴に、嬉しそうに聞き惚れた。 「あ、始まったみたいさ」 アレンの忠告に従い、自室に閉じこもっていたラビは、部屋の外に響く破裂音と悲鳴に、耳をすませた。 「・・・・・・爆竹にしちゃ、なんかすげー音がしてっけど・・・・・・」 興味を惹かれると、確認せずにいられないのが、ブックマンの性だ。 ラビは、警戒しつつも部屋を出て、音のする方へ走っていった。 そして、その音が間近に迫った時、 「いい加減にしなさい!」 聞き覚えのある怒声と、破裂音とは違う破壊音に、ラビは急停止する。 そろそろと、回廊の角から声の方を覗くと、リナリーの足元に、瓦礫に埋まったコムイの姿が・・・。 「アレン君!大丈夫?!」 彼女が開けたらしい、壁穴の向こうへと呼びかけると、アレンがほうほうの体で出てきた。 「な・・・何があったんさ?」 もう安全らしい、と、判断して、ラビが寄っていくと、白い髪を煤で汚したアレンが、涙目を向ける。 「・・・・・・コムイさんに、いぢめられました」 火薬のせいか、目を赤くしたアレンは、か弱い兎のようで、昨日、酷い目に遭わされたばかりのラビですら、同情せずにはいられなかった。 「アレン君、コムイ兄さんには、お仕置きしておいたからね?」 どうやら今年も、医務室で新年を迎えそうな兄を見下ろし、リナリーは深く吐息する。 「まったく・・・兄さんもやりすぎよね。いくら、アレン君がクロス元帥の弟子だからって!」 「リナ・・・!おマエもいい加減、気づいてやれヨ・・・・・・!」 なぜコムイがアレンを目の敵にするのか―――― その真の意味を、全く気づいていないらしいリナリーに、ラビが、乾いた笑声を上げた。 「アレン・・・お前、本当にカワイソウだな・・・・・・」 でも、と、ラビは、アレンの耳元に、囁きかける。 「俺を売った天罰だから、コレ」 「・・・・・・っ今年は絶対、幸せになってやる!」 流れる涙を拭いながら、アレンはリナリーにもらった春聯を握りしめた・・・が・・・。 「・・・ゴメンね。アレン君の部屋、壊しちゃったね・・・・・・」 リナリーが、気まずげに視線を逸らし、ラビが、火薬と壁の崩壊によって、無残な状態になったアレンの部屋を覗き込む。 「・・・・・・アレン、今日中に新しい部屋、探すさ」 そして、急いで春聯を貼れ、と、薦められ、アレンは、落とした肩を、更に落とした。 今年・・・彼に幸せが訪れるかどうかは――――・・・次の年が来るまで、わかりそうもなかった。 Fin. |