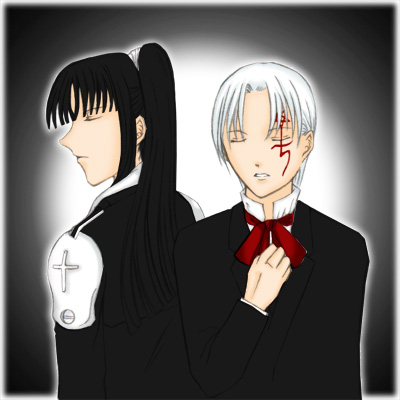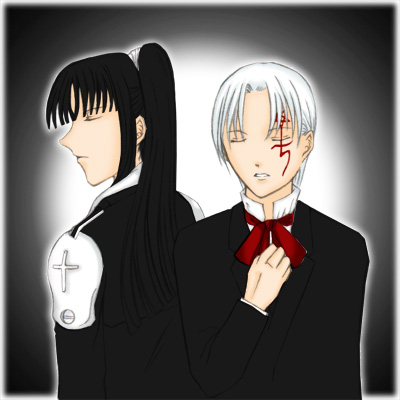「あ、やっと終わったんさ?」
「ったく、毎年毎年、おんなじ説教聞いてんじゃねぇのかよ?」
ミサが終わった後の、クリスマスパーティにと、ご馳走が用意された食堂に、ラビと神田は早くも出没していた。
「あれ?ラビもミサに参加してなかったんだ?」
「だって俺、クリスチャンじゃねーもん」
意外そうに目を丸くしたアレンに、ミランダの耳をはばかってか、ラビが小声で言う。
「えーっと・・・プロテスタントでもない、ってことだよね、それ?」
「ブックマンが宗教持ってちゃ、公平に記録することなんかできねぇさ」
当然のように言い切ったラビに、アレンは苦笑した。
「なんで・・・神様はこんな人たちを使徒にしたんだろ・・・」
「そんなことは、神に聞くんだな」
「適合しちまったもんは、しょうがないさ」
「・・・・・・神様って、どんな基準でチョイスしてるんだ」
はは・・・と、乾いた声を上げるアレンに、神田とラビが、一様に眉をひそめる。
「それを言うなら、お前の師匠が最たるもんだろ」
「クロス元帥に比べりゃ、俺たちなんて清廉潔白さ」
「あぁ、反論不可能ですね」
師への暴言を、あっさり容認したアレンは、
「清廉といえば・・・」
と、人であふれ始めた室内を見渡した。
「今日のミサを執り行った司祭が・・・変わった人だったんです」
「変わった・・・?あぁ、いつも来るオヤジだろ」
面識があるのか、神田が、人々に囲まれた司祭の姿を見つけ、指し示す。
「ヴァチカンじゃあ、ちょっとヤバイ位置にいるらしいけど、俺は嫌いじゃないさ」
「あぁ・・・やっぱり、ヤバイんだ?」
「そりゃー、総本山で、『異教徒だからって地獄に落ちるとは言えない』なんて言える人間は、そうそういないさ」
クスクスと、声を潜めて笑うラビに、アレンも頷いた。
「あの人、殉職した人たちを、『神のため』じゃなく、『守るべきものを守るために戦った』って言ってたよ。
僕、あの人好きだな」
「まぁ、あんな奴が受け入れられるには、あと100年はかかりそうだがな」
皮肉げな口調だったが、それは神田なりの肯定なのだろう。
「100年後かぁ・・・見てぇけど、さすがに俺、死んでんだろうさ」
「ラビなら、化け猫になって生きてそうですけど」
「誰が猫さ!!」
アレンの言葉に、ラビが大声を上げた途端、
「こら!静かにしなさい、アンタ達!」
ジェリーに叱られて、ラビは首をすくめた。
「なぁ?みんな、すげー暗くね?」
「あぁ、辛気臭ぇな」
問うような視線をよこす二人に、アレンは、かすかな苦笑を浮かべる。
「実は・・・」
哀しみに満ちた礼拝堂での事を話すと、神田もラビも、深く吐息した。
「無理もねぇ・・・。あんなことがあったんだ・・・」
そう言った神田が、しばし瞑目したのは、兄弟弟子への弔いだろうか。
ラビは、神田に留めていた視線を外し、それを、離れた所にいる少女に向けた。
「道理で、リナリーがしょげてると思ったさ」
見れば、リナリーはコムイの胸に、顔を埋めて泣いている。
その様を、じっと見ていたアレンに、ラビは、にこりと笑みを向けた。
「今はまだ、コムイに軍配があがってっけど、お前も望み薄ってわけじゃないさ!」
「・・・それ、慰めてるつもりですか?」
「100年後が見れねぇなら、せめて、一大抗争は最後まで見てぇじゃん?」
にっ!と、面白そうに笑ったラビに、アレンは本気で青ざめる。
「面白がらないでくれます・・・?こっちは命がけなんですから・・・!」
「はっ!だったら、せいぜいノアに活躍してもらうよう、祈るんだな」
「え?神田、それってどう言う・・・?」
訝しげに眉を寄せたアレンの肩を、ぽん、と、ラビが叩いた。
「狡兎死して良犬煮らる―――― 敵がいなくなったら、コムイは遠慮なくお前を抹殺すると思うぜ?」
「え゛?!」
嘘だ、と言おうとしたものの、否定することができない。
「天命を全うしたかったら、奴につけ入る隙を与えないよう、せいぜい気をつけるんだな」
ラビと同じく、面白がっている様子の神田の言葉に、暖かい室内にいるもかかわらず、アレンは本気で震え上がった。
|